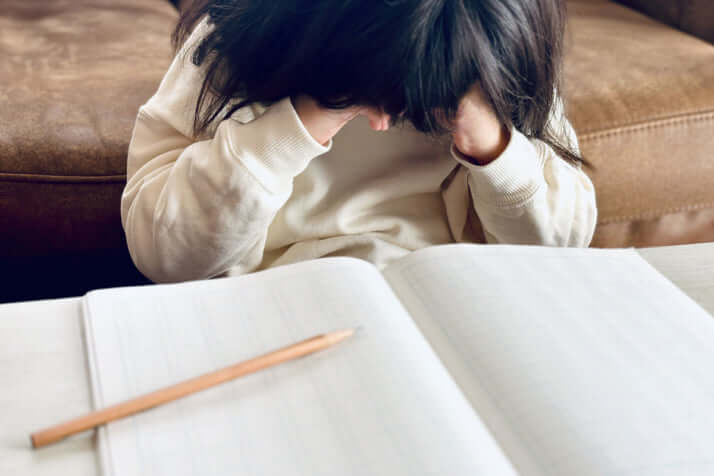高学歴の親こそやりがち…「中学受験」で子供のやる気を削いでしまうNG行動とは
東北大学加齢医学研究所の教授・瀧靖之氏の調査によれば、早生まれの子どもは中学受験において明らかなハンデを負っている。具体的なデータについては前編で取り上げるが、今回は、自身も早生まれの息子を持つ瀧氏が、実体験からオススメする「子どもの中学受験への関わり方」、そして「やってはいけない」NG行動を取り上げる。
(前後編の後編)
***
※この記事は『本当はすごい早生まれ』(瀧靖之著、飛鳥新社)の内容をもとに、一部を抜粋/編集してお伝えしています。
【写真を見る】衝撃…!「早生まれ」と「遅生まれ」では進学校の合格者数がここまで違う
早生まれなら、「親子で一緒に学ぶ」が正解
早生まれのお子さんの中学受験に親子で取り組むことは、とても良いことだと思います。もちろん、中学受験ではなくても、どんな段階でも親子で勉強に取り組んだ方がよいのですが、ここではとくに中学受験に対しての効果の一例を述べたいと思います。これは、私自身の実体験でもあります。
決して子どもの成績を管理するとか、勉強を上から目線で教えるという話ではありません。親御さんが、お子さんと同じように横に並んで対等な立場で問題を解くのです。私も2年半、息子の中学受験にフルで伴走しました。最初は自分の興味もありましたが、だんだんその奥深さに惹かれたということもありました。そこで非常に大きな気づきがありました。
一番のメリットは、子どもを怒れなくなること、それどころか敬意のような気持ちが生まれることです。小学校4年生くらいでは、まだ親御さんの方が圧倒的に解答できると思います。でも、学年が進むにつれて、算数も他の教科もどんどん難しくなっていきます。
つるかめ算も、方程式を使ってはいけませんし、例えば円周上の3人の旅人算を比で解くような問題は、経験のない親御さんには相当な難問です。また複雑な図形の問題など、一日考えても答えが出ないようなものも度々ありました。
国語も、びっくりするくらい長い問題文が出題されたり、100字を越えるような解答を要求されたりすることもあります。小説も心情曲線の把握が難しいような、子ども自身が人生で経験をしたことがないような難しい内容の出題も、近年増えてきています。
理科も社会も、高校受験のような難しい内容や多くの暗記もあります。そしてそもそも、暗記となると子どもにはかなわないかもしれません。自分が解けないと、怒れなくなります。ですから、お子さんの成績がふるわなくても、叱ることがなくなるのです。
むしろ、まだ小学生なのにこんな難しいことに立ち向かって頑張っているのかと、子どもに感動や敬意すらわいてきます。いかに中学受験の問題が難しいか、身に沁みてわかるようになりますから、お子さんの努力にも自然と目が向きます。
[1/2ページ]