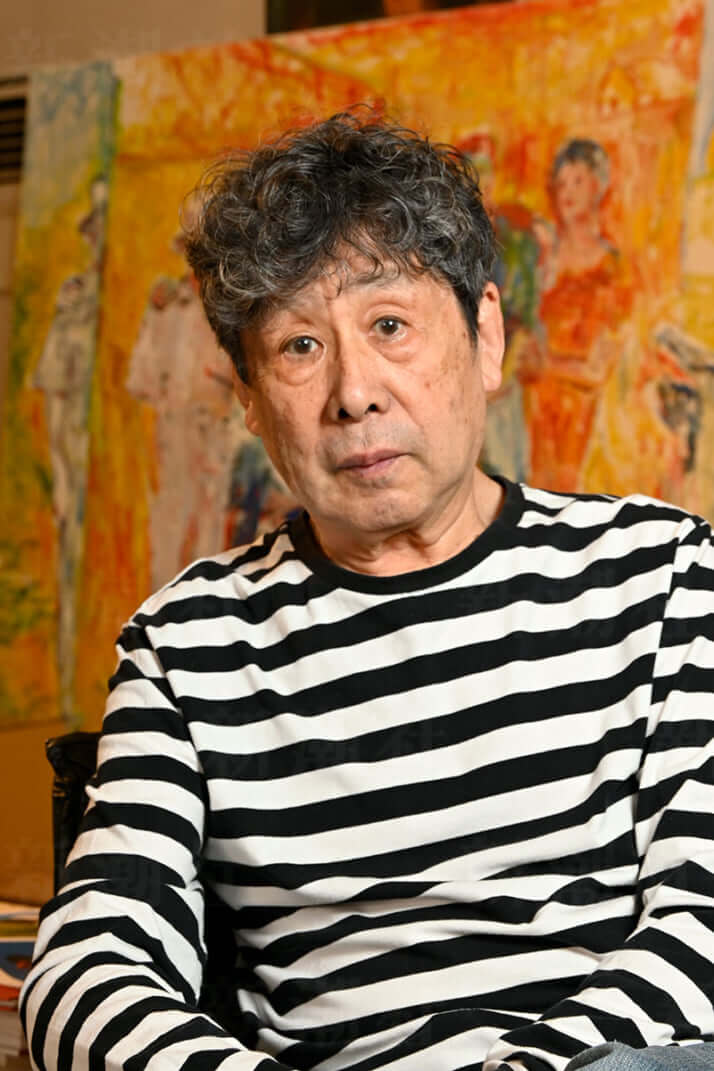三島由紀夫と黒澤明に「ステーキを食べるべき」と言われ… 横尾忠則が続けている“食習慣” 「僕が現在でも健康で長生きしているのは肉のせい」
この前、編集者のTさんがアトリエにお土産を持って遊びに来られた時、食べ物の話になって、そういえば僕は食べ物についてエッセイのようなものを書いた記憶はないんですが、毎週日曜日の夕食には妻の自家製のステーキを食べる習慣が2年ほど前からできてしまった、ということをTさんに語ったら、それ、早速書いて下さいと言われてしまいました。
速報「お酒の味がまずい」「春雨サラダが飲み込めない」 石橋貴明が公表の「食道がん」 著名人サバイバーたちが振り返る兆候
ステーキに興味を持ったのはかなり昔で、三島由紀夫さんに銀座のケテルスというドイツレストランに招かれた時、三島さんが、「ステーキは週に2度食べる、ステーキは創作に不可欠だ、物を創る人間はステーキを食べるべきだ」と話されたことが、ずっと耳に残こっています。まだあの頃は収入が少なかったのでステーキは高嶺の花で、せいぜい年に1回、あるいは3年に1回位で、僕には余り縁のない高級料理でした。
そんな三島さんはステーキをたらふく食った腹に短刀を刺して、割腹自殺をしてしまいました。もうステーキをやかましく勧める人もいなくなって久しく経った頃、家が近所ということで黒澤明さんを知ることになって、黒澤さんの家によく遊びに行くようになったのです。ある日、食道楽な黒澤さんが、「横尾君、芸術家は食が大事だ、美味いものを食わなきゃ芸術が衰退するよ。特に肉、ステーキを食うべきだ」とおっしゃり、黒澤さんも三島さん同様、ステーキ狂だったのです。世界の文学者と世界の映画監督から、世界に轟く作品を作る原動力にはステーキという秘密兵器のあることを明かされたのであります。
黒澤映画の黒澤組はロケなどに行くと毎晩のように肉料理が食えるとスタッフ達は大喜びという話をよく聞かされたものです。一度、黒澤さんの家へ夕食に招かれたことがありましたがその時は寿司でした。この日は黒澤さんと僕の共通の知人で、アメリカの映画研究家のオーディ・ボックと一緒だったので、日本食の寿司がでたのだと思いますが、大きいお盆に食べきれないほどの寿司が盛られていました。
黒澤さんは肉だけだと思ったら寿司も好物だったのです。黒澤映画の常連俳優で僕の年上の親友の土屋嘉男さんから聞いた話では、黒澤さんは何んでも朝からステーキを食べる人だったそうです。
黒澤さんの家に遊びに行くと僕はいつも4時間位ねばって、黒澤さんから映画論を聞くのが愉しみになっていました。そんな時も必らず食べ物の話、それも肉の話が出ました。黒澤さんの師匠の映画監督山本嘉次郎さんも食道楽で、たった一食の料理を北海道まで食べに行っていたという、そんな伝説の監督です。その弟子だった黒澤さんの食道楽もそこから遺伝しているのでしょう。
黒澤さんも芸術家は美味い物を食べなきゃいい作品ができないと、創造の秘密を何度も語られました。僕はどちらかというと食べ物に無頓着な人間です。美味いものを食うために飛行機で北海道へ、なんて狂気の沙汰としかいえません。そうか、僕の作品がもうひとつだというのは食道楽でないためかも知れない。そんなわけで三島さんと黒澤さんに習って、肉を食う、三島さんのように週2回のステーキ、黒澤さんのように朝からステーキ、そんな真似はとってもできないが、せめて、週1回はステーキということで、毎週日曜日の夕食は必らずステーキにしたのです。
また老齢になると肉を沢山食う必要があるという説もあるので、週1回のステーキ以外にもシャブシャブやすき焼や、牛丼などを妻が作ってくれる。肉を食うのも全て芸術のためということだから立派な内助の功であります。
幸い、わが家の肉は、全国で1等賞を獲った、僕の郷里の西脇にある黒田庄肉という黒牛の肉です。よく神戸肉と言われているものは、多くが西脇の黒田庄の黒牛のことを言っているのではないかと思っています。
西脇によく帰省していた頃、駅前に肉をテキと呼ぶ店があって必らずそこでステーキを食べる習慣がありました。本場の黒田庄肉を牧場から直接入荷して販売する肉の問屋のような店があることを知って、今では肉はそこから直送してもらっているので、わが家にはステーキの他にシャブシャブ用、すき焼用、ナントカ用と何種類も常に待機しているのです。またご贈答用には必らず肉を贈ることにしています。もう少し早くその存在がわかっておれば三島さんや黒澤さんにここの肉をお贈りしたのにと、気づくのが遅過ぎて大変残念に思っています。
僕が現在でも健康で長生きしているのは多分に肉のせいだと思っています。すると三島さんも黒澤さんも芸術の恩人であると同時に命の恩人でもあります。
肉がこんなに創造と芸術に貢献しているのは、ぐだぐだ説明をしなくても世界的な二人の芸術家の肉道楽の話を聞いただけで十分説得力があると思います。芸術のために肉を食い、肉のために芸術をする、そんな毎日でございます。