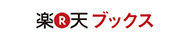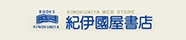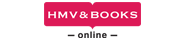「八ッ橋」はなぜ「阿闍梨餅」に取って代わられたのか 理由は「テクノロジーの進歩」にあり?
日々無数の新しい土産物が登場し続けている京都で、もっとも有名な銘菓といえばなんといっても「八ッ橋」だろう。
速報石破首相が杉田水脈氏を切れない“本当の理由” 「キーワードは、宗教団体を含む“岩盤保守”」
速報秋篠宮さまが「ハラハラ」しながら悠仁さまを見つめた瞬間とは 秘められたエピソードが公開
しかし明治以来、京都土産トップの座を誇ってきた「八ッ橋」を近年、猛追し、逆転する勢いの菓子がある。もっちりした生地で粒あんを包んだ半生菓子「阿闍梨餅(あじゃりもち)」だ。
このトップ争いの陰にはテクノロジーの進歩があると考察するのが、京都生まれ京都育ちの人気小説家・澤田瞳子さん。古都の身近な歴史を追ったエッセイ集『京都の歩き方 歴史小説家50の視点』より、その一部をご紹介しよう。
***
ありがたいことに京都の菓子は、どこに持参しても喜んでいただける。新製品の開発や新店舗のオープンも盛んなので、自分が最近、味見をして気に入ったものを差し上げることも多い。
一方で地元の者には予想外な菓子が、いつしか土産物として大人気になっていることも頻繁だ。その代表例が現在、京都土産トップの人気を誇る「阿闍梨餅」だろう。わたし自身この菓子は、学生の頃からよく買い求めていた。数が多いとちょっと重いのが難だが、大学研究室のお茶請けに使ったことも数知れない。ただそれは一つ100円(当時)という低価格と個包装で日持ちがいいという利便性に負うところが大だった。本店が我が家から比較的近く、いつでも自転車で立ち寄れたためでもある。それがどうだろう。今や本店は立派に建て替えられ、阿闍梨餅は京都駅でもデパートでも大行列しないと買えない菓子となってしまった。ううむ、かつては知る人ぞ知る、地元民のための商品だったのに。
一方で駅の土産物コーナーでは、京都土産の定番たる八ッ橋もいまだ根強い人気を保っている。粒あんにこしあん、京都らしい抹茶は言うに及ばず、季節の果物やチョコレート、ラムネなど味のバリエーションも豊富だ。ただし現在、八ッ橋コーナーの大半を占めるこれらは、1960年代に開発された「生八ッ橋」。それ以前は八ッ橋といえば、板状の固焼きの製品のみを指していた。この昔ながらの八ッ橋の発祥については諸説あるが、17世紀末頃に現在の京都大学近く、聖護院村で作られ始めたものと推測されている。
八ッ橋はかつては湿気を帯びやすく、日持ちが悪い菓子とされていたらしい。その欠点が明治期に改良されると、俄然、京都を代表する土産物として人気を博し始める。明治38年(1905)には七条駅(現在の京都駅)に八ッ橋の販売コーナーが誕生。その3年後に農業振興団体・京都府農会が行ったある全国講演会の記録を見ると、千数百人の参加者が見込まれた会の開催に際し、主催者は物販コーナーで書籍や絵葉書、特注扇子にハンカチ、そして京都の代表的菓子として八ッ橋を販売している。興味深いのはこの八ッ橋に対する説明で、「耐久美味且つ軽量なるものに付、土産に適当と認め直売せしむ」――つまり、日持ちがよくて美味しく、更に軽いので土産に便利と明記されている。なにせ鉄道は走っても、まだまだ荷物は自分で運ぶものだったこの時代、丈夫で軽い八ッ橋は大変重宝がられたわけだ。
それゆえだろう。この当時の記録を読んでいると、八ッ橋が思いがけないところにしばしば顔を出す。たとえば新聞「六大新報」は明治23年(1890)、真言宗の機関紙として創刊された日本最古の宗教新聞。日清・日露戦争の最中には、従軍した布教師の動向や戦地に寄贈した物品などの詳細を記事にしている。この新聞の日露戦争終盤の明治38年7月30日号では、旅順攻略に参加した第9師団・第11師団に、同行中の布教師を通じ、「京都名産八ッ橋5万枚」が届けられたと報じられている。
戦地に八ッ橋が送られる例はこの時だけではなかったらしく、第9師団に同行していた金子密禅なる僧侶は、この半年前にも「八ッ橋10缶」「味付海苔3缶」を受け取った礼を六大新報に寄稿している。八ッ橋と味付海苔がひとくくりで語られている点、八ッ橋がいかに日持ちがよく、運送に耐える便利な菓子と考えられていたかが推測できる。
ただ八ッ橋の保存性が高くなったのは、前述の通り、明治時代になってから。それ以前の八ッ橋は社寺の門前で売られていた饅頭や団子同様、その場で食べる土地の名物で、京都の土産として遠方まで持ち帰るものではなかったらしい。いや、八ッ橋に限らず、そもそも移動手段が徒歩のみだった近世まで、旅の土産とは腐敗しないものにならざるをえなかった。
江戸時代初期成立の笑話集『醒睡笑』に、京都に詳しいと吹聴する男が出て来る。彼は、「じゃあ、祇園と清水寺の間はどれぐらい離れているんだい?」と聞かれると、京都の絵図が書かれた扇を広げて眺め、「一寸ぐらいさ」と答えたという。つまりこの男は実際の京都はまったく知らず、町の様子を描いた扇の絵だけで知ったかぶりをしていたわけだ。男が手にしていた扇は当時、京土産としてメジャーな品だったらしく、この他に人形や針、紅(べに)なども江戸期の史料では名が挙がる。いずれも小さくて持ち運びがしやすい点に注目だ。
そう思って顧みれば、今日、わたしが「京都の土産を」と思い立った時にすぐに菓子類を選び得るのは、すべて交通網・運輸網の発達のおかげ。そしていささか重く、かさばる阿闍梨餅が代表的お土産の座を占められるのは、実に歴史と社会の推移の結果なのだ。
※本記事は、澤田瞳子『京都の歩き方 歴史小説家50の視点』(新潮選書)を再編集したものです。