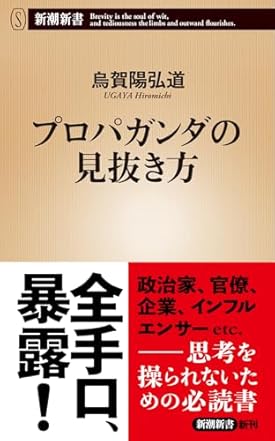「望月衣塑子記者」を一躍有名にした「記者会見」に先輩ジャーナリストが失望した理由
東京新聞の望月衣塑子氏は、日本の現役の新聞記者の中で、最も有名な人物の一人といえるだろう。自身がモデルとなっている映画が作られ、日本アカデミー賞まで受賞しているのだから。毛嫌いする人もいるが、「権力に立ち向かう」姿勢を支持する人も多くいる。
速報農水省の「コメ不足」説明は「ウソ」ばかり! 買い占めや転売のせいではないという重大な指摘
速報「大変お尋ねしづらい事柄ではありますが…」 悠仁さまの成年会見で記者が「質問せざるを得ないこと」とは
しかし、フリージャーナリストの烏賀陽弘道氏(62)は、現在の望月氏は「プロパガンダのツール」として機能しているのではないか、と指摘する。烏賀陽氏は元朝日新聞記者。権力と立ち向かうという姿勢そのものはもちろん支持している。また、かつての望月氏の著書には感心したこともあるという。
ではなぜ「プロパガンダのツール」だと言うのか。
烏賀陽氏の新著『プロパガンダの見抜き方』をもとに見てみよう(以下は同書を抜粋、再構成したものです)
***
優秀な調査報道記者だと思っていた
一般の間で東京新聞(中日新聞東京本社)の望月衣塑子記者が名前や顔を知られるようになったのは、望月記者が安倍晋三政権下、菅義偉(すがよしひで)官房長官の首相官邸会見に参加するようになった2017年6月6日以降のことである。
私が望月記者に注目したのは、それ以前のことだった。その著作『武器輸出と日本企業』(角川新書)を2016年7月に発売されると同時に買って読んだ。私はコロンビア大学院での専攻が国際安全保障論であり、特に核戦略を中心にした軍事論を定点観測の場にしている。そんな関係で軍事を扱った本には目を通すようにしていた。
彼女の著作は、日本企業が武器製造や輸出にどう関わっているのか、一冊を費やして述べた内容で、これまでに明るみに出たことのない「日本の軍需産業」の全容を描くことに成功している。
一読して、優れた調査報道だと思った。
私は望月記者をそうした調査報道の名手だと思っていたので、菅義偉官房長官の首相官邸会見に参加し、大胆かつ直接的な質問で記者自身が注目を浴びるようになったことを、非常に奇異に感じた。調査報道のあり方とは矛盾するからだ。
なぜなら、官房長官会見で100万回質問しても、調査報道で明らかになるような特ダネが出てくることはないからだ。理由は簡単で、記者会見には他社の記者がいて、質問の内容を聞いているからだ。
もしある記者が特ダネを握っていて、書く前に記者会見でそれを質問したら、他の記者は「あいつは特ダネを書こうとしている」と察知する。一社にだけ特ダネを書かれては困る(競争に負ける)ので、ただちに後追い取材を始める。その時点で、特ダネは特ダネでなくなる。
自分の特ダネをわざわざ潰してしまう馬鹿な記者はいない。特ダネであればあるほど、記者会見では聞かない。一社だけ単独で取材を申し込む。それは報道を業務とした経験がある人間なら当たり前のこととして理解しているはずだ。
だから望月記者が毎日官邸会見に出席し(官房長官会見は平日の午前と午後2回)記者会見での質疑が日常業務のようになっているのを見たとき、「東京新聞は何ともったいない人材の浪費をするのだ」と嘆いた。「この人事配置は誤りだ」とXで東京新聞を批判したこともある。会見での質問に時間を費やす限り、望月記者から『武器輸出と日本企業』で書いたような調査報道は出てこないことがわかっているからだ。実際にぱたりと出てこなくなった。
また望月記者自身が「文春オンライン」などに顔を出してインタビューで登場するのを見て、調査報道記者としては廃業するのかと思った。顔を知られていない取材者の方が調査報道には有利だからだ。
なぜそこに配置?
望月記者を官邸会見に配置した理由が知りたかったので、東京新聞に直接メールを出して聞いてみた。飯田孝幸・編集局次長名で次のような返答があった。
「望月記者に限らず弊紙の個々の記者の配置、取材活動などに関して社としての考え方などを対外的に説明することは原則、難しいと考えております」
望月記者は首相官邸を担当する政治部ではなく、検察・警察などを担当する社会部に籍を置いたまま会見に参加している。それは「会社の命令」によるのではなく「自発的な意思」によるという。
東京新聞社内が彼女の「官邸会見取材」をどう見ているのか、という問いに対して、望月記者はこう答えている。
「うちはわりと政治部と社会部の垣根が低いんです。『質問しにいっていいですか?』って聞いたら、『いいよ』と。でも、こんなことになるとは思っていなかったと思います。ご迷惑も多々かけていると思いますが、これだけ官邸や政権が、国民に対して、隠し事や改ざんまがいのことを続けている限りは、疑念をぶつけないわけにはいきません。読者の方から数多くの応援メッセージが来たり、購読者が増えたり、会社にとっても良い面もあるようで、批判があっても『頑張ってこい!』と背中を押してくれるのはとても有り難いことで、会社には大変感謝しています」(2017年8月17日付「文春オンライン」)
私も朝日新聞という「会社組織の記者」だったからこの回答には首肯できる部分がある。そして気になるのは、望月記者がOKを取った「上司」は誰か、だ。
私が所属していた朝日新聞社なら、直属の社会部長、官邸を担当する政治部長、そして両者の上司である編集局長あるいは次長である。
望月記者が官邸会見に参加し始めた2017年6月当時、東京新聞の編集局次長は、前職が政治部長だった高田昌也氏である(同年12月に定年、編集委員)。同氏がOKすれば政治部から異論は出ない。
この高田氏がキーパーソンなのだが、そのバックグラウンドは後編で詳しく述べる。
「反アベ」のヒロインとして
特ダネが出て来なくなる一方で、望月記者自身の知名度はぐんぐん上がった。これは望月記者と菅義偉官房長官の激しいやりとりが、テレビニュースや動画でインターネット上に流れ、安倍政権に不満を持つ層の拍手喝采を呼んだからである。
「新聞記者の存在がこれほどの注目を集めたことが近年、あっただろうか」
自らも長年毎日新聞記者を務め、新聞労連ジャーナリズム大賞選考委員の臺宏士(だいひろし)氏は著書『報道圧力 官邸vs望月衣塑子』(緑風出版)でそう記している。
ここからわかることは、望月記者の一連の活動は「効果的なプロパガンダには物語がある」というプロパガンダの定石にぴったりフィットしていることだ。
妙な誤解を封じるためにお断りしておくが、私は「望月記者が自分や東京新聞の宣伝のために官邸会見に参加した」と考えているわけではない。ここでは真実の判断を留保する。望月記者の説明ではそうではない(他人の頭の中を見通す超能力は私にはない)。東京新聞は人事配置の理由を説明しないと言っている。
人気コンテンツと化した官邸会見
望月記者本人の意思は別にして、望月記者と菅官房長官らの官邸会見でのやりとりは、テレビやネット媒体の格好の動画コンテンツとなった。官邸会見そのものが「劇」「ドラマ」に変貌した。その観客はスマホやテレビを見る大衆である。俗にいう「劇場化」である。
望月記者の官邸会見取材は、人気コンテンツになった。それはこの官邸会見が「物語」の要件を非常にうまく満たしていたからだ。
【舞台】内閣官房長官の記者会見――内閣官房長官は、国政を国民に説明することが仕事の「国政のスポークスマン」である。内閣という権力の中枢に質問をできる「窓口」でもある。しかしそこには国民誰もが自由に参加できるわけではない。その「知る権利の代理人」として「内閣記者会」に所属する新聞・テレビ・通信社の記者がいる。
【登場人物】望月記者と菅官房長官――安倍政権は戦後最大の保守・反動的な内閣としてリベラル側の批判を浴びている。それを擬人化したような悪人顔の菅義偉官房長官。無骨な語り口。きめ細やかなカスタマー対応に慣れた現代大衆には「ぶっきらぼう」「愛想がない」「不親切でわかりにくい」と映る。
それに挑戦するのが、望月衣塑子記者。母親であり妻。40歳代女性(新聞の読者層としては最若年)。既婚。夫は同業者。読者が同一視しやすい「普通さ」を持っている。
こうした望月vs.菅の組み合わせは、大衆にとって「わかりやすい対称」の構図である。それが証拠に、後に官房長官が、ソフトなイメージの加藤勝信氏に交代すると、この対称性は崩れた。望月記者も官邸会見に姿を見せなくなった。
権力に忖度しすぎて沈滞した記者クラブ系マスコミ。それを打破して国民の知る権利を代行しようとする望月記者。権力側はそれを妨害してできるだけ隠そうとする。会見を舞台に彼女は闘いを続ける――偶然なのか意図的なのかの判断は別にして、ここにはプロパガンダとしては絶好の「物語」がある。
わかりやすい「勧善懲悪」は受ける
日本の大衆は「権力者は隠れて悪いことをする」という物語が好きである。それを内部告発者や記者など「庶民」に近い非権力者が暴き、正す物語が大好きだ。「権力者vs.庶民」の上に「勧善懲悪(かんぜんちょうあく)」という二つの物語が重なっている。ここでは「権力=悪」「庶民=善」の構図が自動的に設定されている。
官邸会見でのやりとりが劇場化され、人気コンテンツになって以降は、望月記者をめぐる動きは急激にプロパガンダ性を帯びていく。
前述の臺記者の記述では、望月記者の著作が映画化される、その密着ドキュメンタリーがまた映画になる、講演会が盛況であることなどが望月記者の業績となっている。
「新聞記者の存在がこれほどの注目を集めたことが近年、あっただろうか」――そう誇らしげに臺記者は書くのだが、同じ記者である私は、何が良いのか、さっぱり理解できない。報道記者の業績は、すべからく「どんな事実を読者に知らせたか」だけで判断されるべきだからだ。「こんな事実が明るみに出たら、困る」という事実を読者に知らせることこそが、記者が権力者に与えることのできる最大の痛撃である。記者が注目されても権力は痛くも痒くもない。
望月記者が有名になったのは、彼女が報じたニュースの内容のおかげではない。菅官房長官と記者会見の場で攻防を繰り広げるという「取材のやり方」が可視化・劇場化されたからである。
Facebookには「東京新聞望月衣塑子記者と歩む会」」というコミュニティが立ち上がり、主に「リベラルびいき」「自民党嫌い」「安倍晋三総理嫌い」の中高年男性で賑わった。最高時1万8090人のメンバーがいたが、Facebook社が閉鎖した。続いて立ち上がった「東京新聞望月衣塑子記者と歩む会で出会った人たちの会」というコミュニティには、2024年5月現在も2万2000人が参加している。やはり主力は中高年男性である。
奇妙な映画「新聞記者」
望月記者の知名度がピークに達するのは、その著作『新聞記者』を原案にした同名映画(藤井道人監督)が、2019年6月に公開されたときである(2022年1月には、米倉涼子主演のドラマ版がNetflixで配信された)。
私はもともと映画ファンだ。まして自分の職業が映画になると無関心ではいられない。公開と同時に見に行った。そして二つの点にびっくりした。
まず公開規模である。内容的には都市部で単館上映が通常の地味な映画なのに、イオン系列のシネコンで全国に多館公開された。上映館数は全国約140館。
イオン系シネコンはショッピングセンターに隣接している。家族連れ・カップル向けの娯楽作品やアニメ映画を主に上映するので、同作のような大人向けポリティカル・サスペンスはふだんの上映作品の傾向とはかけ離れている。
言うまでもなく「イオン」は日本最大手の流通グループ企業だ。「新聞記者」はその子会社である「イオンエンターテイメント」が配給した。同社は「TOHOシネマズ」をしのぐ日本国内最多の821スクリーン数を持つ、最大の映画興行会社である。つまり映画「新聞記者」は日本最大規模の公開を実施したことになる(そのわりには興行収入は6億円と振るわなかった)。
もう一つは、フィクション映画なのに、望月記者自身がストーリーと無関係に繰り返し登場する点だ。映画を見た人は望月記者の顔を何度も見ずにはいられない仕組みになっている。私には、主演の女性記者役俳優より望月記者自身のほうが印象に残った。
なぜこんな映画が、ハリウッド大作のような全国のショッピングモールのシネコンでロードショウされたのだろう。
その答えは映画冒頭にあった。「イオンエンターテイメント」というロゴが大写しになるのだ。
***
「望月記者」「東京新聞」「イオン」という点と点を結び付けるものは何か。烏賀陽氏は一つの仮説を導き出していく。ここでも重要なのはプロパガンダを見抜く視点だ、と説く。その仮説については後編(「望月衣塑子記者」「民主党」「イオン」という奇妙なトライアングル 映画『新聞記者』の読み解き方)に詳しい。