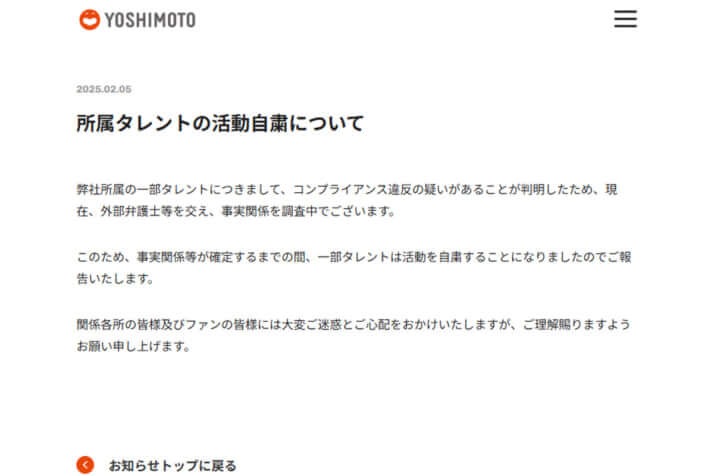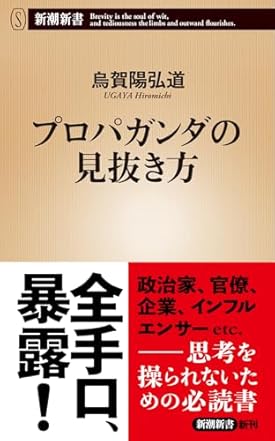高比良くるま、とろサーモン久保田……警察と記者クラブ「プロパガンダ」共闘の読み方
任意の事情聴取なのに実名?
吉本興業に所属する芸人がオンラインカジノに手を出していたという一件は、令和ロマン・高比良くるまの「告白」によって、より大きく報じられることとなった。これまでは吉本興業側の要領を得ない、あいまいな発表以外には、各新聞、テレビとも「捜査関係者」の話として、任意の事情聴取が行われていることを伝える短い記事を出すのみだった。
速報“脱法的”なスキームで「100万円以上浮くケースも」 維新議員のセコい「国保逃れ」 識者たちは「悪質」と断罪
速報「『非核三原則』は“平和っぽく気持ちよくなる”ためのものではない」 高市首相側近「官邸筋」の核保有発言を前首相補佐官が擁護
2月5日~6日の第一報段階では一般紙、通信社は芸人名すら出していない(読売新聞とスポーツ紙を除く)。ところが高比良の場合、当人が経緯を口にしたことで、堂々と報じやすい状況が生まれたのである。
賭博が違法なのは当然として、一連の報道を冷静に見た場合、日頃新聞社がお題目として掲げている「人権への配慮」がどこにあるのかという疑問も浮上するだろう。
出演番組の差し替えなどで吉本興業が実質的に「対象者」であることを認めた芸人はまだしも、15日の毎日新聞記事では、高比良と、とろサーモン・久保田かずのぶが事情聴取を受けていること、久保田は関与を否定しているという内容を伝えている。
任意の事情聴取、しかも一人は関与を否定している段階で実名報道という毎日新聞の記事は、一般紙としてはかなり踏み込んだスタンスなのは間違いない。
ただ、こうした報道は「捜査関係者」のゴーサインをもらわなければ不可能であるというのは業界の常識。
そのため、この一連の報道そのものが、警察と記者クラブ系マスコミが歩調を揃えた「オンラインカジノ撲滅キャンペーン」のためのプロパガンダと見ることも可能だ、と指摘するのは、フリージャーナリストの烏賀陽弘道氏だ。
烏賀陽氏は新著『プロパガンダの見抜き方』の中で、政府や企業、インフルエンサーらの情報発信のウラにある思惑を見抜く重要性を説いている。
今回の一件について烏賀陽氏の見方を聞いてみよう。
「まず前提として、逮捕や送検といった事実を警察に公表させ、報じることは、権力濫用を抑止するために重要だということを述べておきます。逮捕された人は留置・勾留されて自由を奪われます。公表させないと、独裁国家のように秘密逮捕が横行しかねません。いつ、誰が、なぜ逮捕されたか実態が分からない、という状況は人権の侵害です。だから『誰それがこういう容疑で逮捕されました』と警察が発表し、記者がそれを知っていることは人権保護と権力濫用の監視として重要なのです。
ところが今回の場合、逮捕していない、任意の事情聴取を受けた人物の名前が出されています。これについてはやり過ぎ、という印象を持ちます。
たとえば久保田さんが任意の事情聴取のまま起訴もされなかったとしたら、それは報道による人権侵害でしょう。選挙で選ばれた議員や首長、税金で生活する高級官僚などと違って、吉本の芸人は『芸能人』であって『公人』(パブリック・フィギュア)ではありません」
しかし結果として、オンラインカジノの違法性が周知されたのは事実。その意味では警察によるプロパガンダが成功しているのは間違いない。
「プロパガンダの定石のひとつに『恐怖アピール』があります。『自分たちの主張や方針に従わないと、これこれこういう恐ろしいことや苦痛・不利益が起きるぞ』と大衆を説得する手法です。世界の移民排斥派がよく使う『外国人移民に門戸を開くと、国を乗っ取られる』という言説もそのバリエーションです。
今回のケースに当てはめると『オンラインカジノに手を出すと、逮捕された時はもちろん、逮捕されなくても警察の調べを受けただけで名前を報道されることがある』という恐怖を大衆に与えることに警察は成功しています。俗に言う『一罰百戒』。1人が公開処刑されれば、他の100人はそれを見てオンラインカジノに手を出さなくなる。これを“Chilling Effect(冷却効果)”といいます。
ところが逮捕者が普通の人では、恐怖アピールが十分ではありません。マスコミが記事にしないからです。それが芸能人なら『ニュース』としてマスコミは飛びつく。自分の仕事がマスメディアに載ることは警察にとって『お手柄』なのです。マスメディアがニュースを報道して初めて、プロパガンダは成立します。
ここでは、警察はマスコミをうまく利用して『恐怖アピール』によりプロパガンダを広めることに成功しました。必ずしも、警察と記者クラブ系マスコミがズブズブの協力関係になくてもよいのです。警察はオンラインカジノを抑制したい。マスコミは大きなニュースを発信したい。両者の利害が一致したに過ぎません。
警察や官庁に記者が常駐する記者クラブは、警察や官庁がマスコミをプロパガンダに利用したいときの『受付窓口』として非常に便利な組織です。これを忘れてはなりません。結果として、現時点では芸人たちの人権はじゅうりんされています。記者クラブにいる新聞・テレビの記者たちは、自分たちが警察のプロパガンダのパートナーだった、というビッグ・ピクチャー(大きな構図)に無自覚だと思います。こうした記者クラブ側の無自覚ぶりが危険なのです」
それが犯罪抑止につながるのならいいのではないか?という疑問に対して、烏賀陽氏はこう指摘する。
「しかし、例えば大川原化工機事件のように、警察が逮捕してもまったくの冤罪だったというケースはどうでしょう。警察は『容疑者はクロだ』と記者に印象付けようとします。それに基づいた発表やリーク(自宅への夜回りなど非公式な取材での情報提供)をする。記者にチェックする目がなければ、そのまま警察の見立てが垂れ流されます。逮捕されたからといって、安易に社名や個人名を出して報道したら、警察のプロパガンダに加担することになる、という警戒心を常に記者は持たなければなりません。
報道各社が記者クラブをつくり、賃料も光熱費も払わずに警察や官庁に常駐することの言い訳は『権力の監視』です。が、警察はじめ権力を持つ側にとって、あくまでも記者クラブは『報道各社が一カ所にまとまっている』という便利な『プロパガンダの窓口』なのです。今回は、それが可視化されたケースだと考えておくといいのではないでしょうか」(同)
オンラインカジノが違法だということは広く伝わった。ギャンブル依存の恐ろしさも改めて強調されている。この流れで、パチンコやパチスロ、あるいは公営ギャンブルについての踏み込んだ議論も行われるようになるのだろうか。