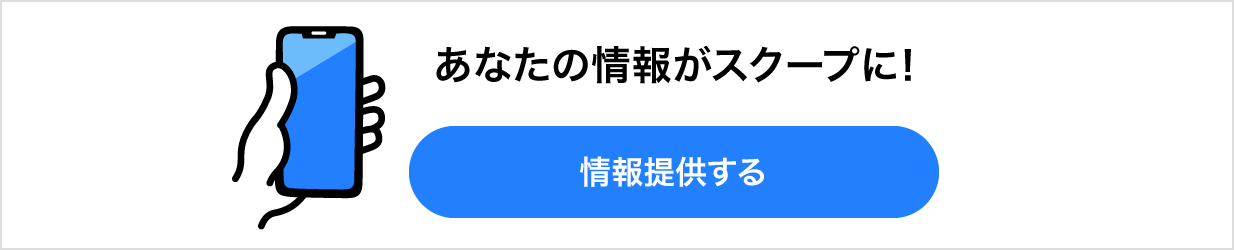農水省の「コメ不足」説明は「ウソ」ばかり! 買い占めや転売のせいではないという重大な指摘
農水省の思惑
「週刊新潮」に寄稿した記事〈2025年も市場の“奪い合い”激化でコメ不足が起きる〉(1月2・9日号)で現在の状況を“予見”していたノンフィクション作家の奥野修司氏はこう話す。
「通常、9月10月は残っている古米も新米と共に売られているものですが、昨年は古米がどこにもなく、新米の奪い合いになり、農協もなかなか確保できない状態でした。コメ不足が続き、価格が高止まりするのは昨年には予想できたはずなのに、農水省は備蓄米の放出を渋り続けたわけです」
政治部記者によると、
「日本の農家の約7割を占める兼業農家は自民党農林族の票田。彼らの利益のためには米価を維持しなくてはならない。そのため農水省は備蓄米の放出に慎重な立場を貫いてきたのです」
山下氏も言う。
「農水省はコメ不足を認めたくない。認めてしまうと備蓄米を放出せざるを得なくなり、放出したらせっかく史上最高水準になっている米価が下がってしまうからです」
そこで農水省が編み出したのが、「どこかにコメがスタックしている」という詭弁(きべん)である。
「普通、何か問題があれば事実を確認してから対応策を講じます。しかし今回は確認もしていないのに、業者が買い占めている、と言っているわけです。コメが不足していることを認めず、あるかどうかも分からない問題を“ある”と言い、業者で滞留しているコメを市場に出すために備蓄米を放出する、という論理を作り上げました。もし業者が米価低下で抱えている21万トンを吐き出せば米価は暴落します」(同)
しかも、農水省はコメがどこに滞留しているのかを調べようと思えば調べられるのだという。
「日本には米トレーサビリティ法というものがあり、生産者から農協、農協から卸売業者、さらにスーパーなどの小売りへと、搬出入した場所も含め全ての取引について帳簿をつけ、その記録を保存しなければならない、と定めているのです。農水省は全てのコメの流通・在庫状況が分かるのに、分からないと言っている。これは役人的なウソなのです」(同)
2月20日発売の「週刊新潮」では、農水省がかたくなに「コメ不足」を認めない理由について詳報している。
[2/2ページ]