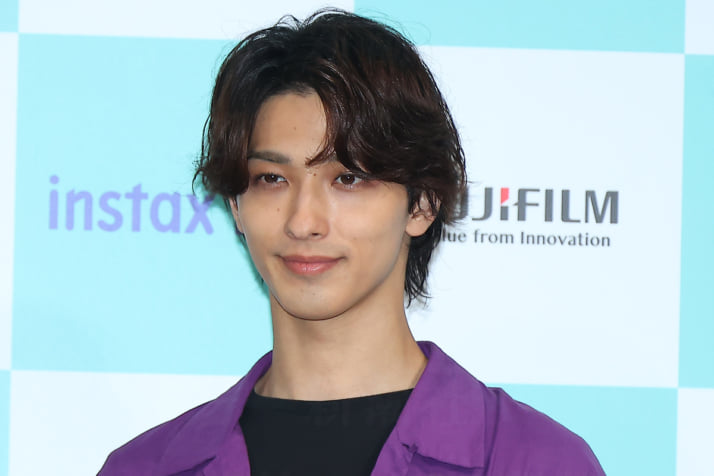【べらぼう】ビジネスマン必見…蔦屋重三郎が諸経費を「半分」にして中身を「2倍」濃くした画期的方法
吉原ガイドの出版元「鱗形屋」の自滅
板元(出版元)として自分で本を出したい蔦重こと蔦屋重三郎(横浜流星)だが、地本問屋(江戸独自の本を企画、制作して販売する板元)たちが認めてくれない。仕方なく、しばらくは吉原のガイドブック『吉原細見』の有力な板元でもある地本問屋、鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助)のもとで、「改」(最新情報を集めて古い情報を修正し、編集する仕事)として働くことにした。NHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺』の第6回「鱗(うろこ)剥がれた『節用集』(2月9日放送)。
【写真をみる】“生肌”あらわで捨てられて…「何も着てない」衝撃シーンを演じた愛希れいか
ほんとうは出版社を経営したいのだが、しばらくは編集の仕事を手伝うことに甘んじた、ということだ。ところが、じつは鱗形屋は、大火で板木や紙が焼けてしまったこともあって経営が火の車。大坂の板元が出版した『新増早引節用集』という字引の偽板(海賊版)を摺って販売していた。
蔦重はそれを知ってしまったが、告げ口はせずに様子を見ていたのだが、そうこうするうちに大坂の板元からの訴えを受けた長谷川平蔵(中村隼人)が、与力や同心らを引き連れて取り調べに現れ、鱗形屋は連行されてしまう。
鱗形屋が偽板を出していることは知っていた、と蔦重は平蔵に漏らした。それなのに放置していた理由を問われると、鱗形屋がいなくなって自分が取って代わることを、どこかで期待していたからだろうと打ち明け、「うまくやるってなあ、堪えるもんですねえ」と、苦しい本音を吐露した。
バカ売れする蔦重の『吉原細見』
いずれにしても棚から牡丹餅。第7回「好機到来『籬(まがき)の花』」(2月16日放送)で、蔦重は鱗形屋に代わって『吉原細見』の板元になると宣言し、売れるガイドを制作するために工夫を凝らすことになる。結論を先にいえば、蔦重によるあたらしい『細見 籬の花』は、ほかの板元が出したものを抑えてバカ売れすることになる。
前述のように『吉原細見』とは吉原のガイドブックで、どんな見世(女郎屋)があり、各見世にはどんな女郎がいて、それぞれの揚げ代(遊ぶのにかかる費用)がいくらで、という情報がみな掲載されていた。見世の格や女郎の階級なども、一目見てわかるように記号化されていた。
しかし、見世の廃業や新規開業、女郎の廃業や新規出しなども多く、情報はすぐに古くなってしまうので、毎年正月と7月の2回、改定を加えた新版が出された。蔦重による新版が出されたのは、安永4年(1775)7月だった。
これを制作するにあたって蔦重が重ねた工夫は、現代においてビジネスに携わるすべての人に、よいお手本になるのではないだろうか。その前に、すぐれた『吉原細見』を制作するうえで、蔦重の立場がいかに有効であったかを確認しておきたい。
吉原で育ち吉原で貸本屋を営んでいた利点
蔦重は吉原に生まれ育ったが、それだけではない。若いころから貸本業に勤しんでいたと思われるが、そのことが吉原ガイドの制作にも販売にも大いに生かされた。
当時、本を購入するのは経済力がある人にかぎられ、貸本屋から借りて読むほうが一般的だった。このため貸本屋は、得意先を足繁く回るものだった。蔦重の場合は吉原が拠点だから、女郎屋や、客と女郎の仲立ちをする引手茶屋を日常的に訪ね、女郎たちのほか、そこで働く人たちとの関係がかなり密になっていたことだろう。ちなみに、女性の識字率が高くなかったこの時代に、吉原の女郎たちは客とのコミュニケーションの必要もあり、ほぼ全員が読み書きできたのである。
こうして女郎屋や引手茶屋に出入りしていれば、良い情報が次々に入ったと思われる。最新情報を入手するためにも、このうえなく有利な立場にいたはずだ。だからこそ、鱗形屋も蔦重を「改」に起用したのだと思われる。また、『吉原細見』は吉原のガイドブックなのだから、吉原の女郎屋や引手茶屋がたくさん仕入れたに違いない。蔦重は最初から、その販路を押さえていたというわけだ。
しかし、蔦重の『細見 籬の花』が売れた要因は、それだけではない。むしろ、そこから先の工夫に蔦重の真骨頂があった。
[1/2ページ]