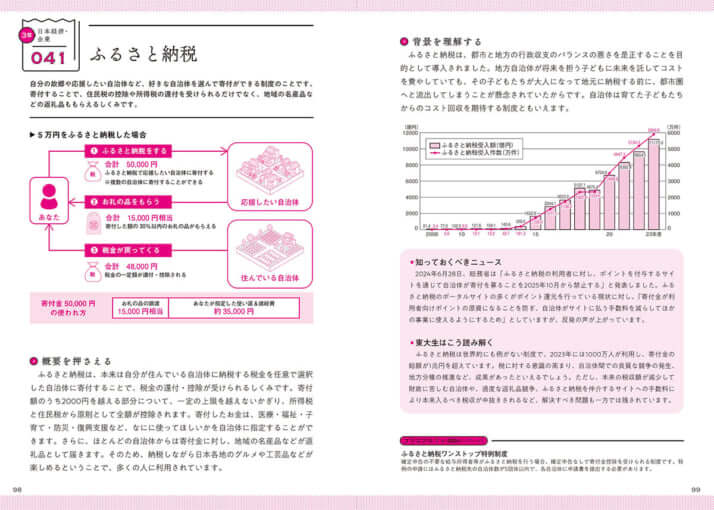世の中の動きに鈍感な人は試すべき…東大生が伝授する「ニュースに強くなる」ための“シンプルな方法”とは
「日常の解像度が高い」とは
多くの東大生を見てきて感じたことは、頭がよくなるポイントとは「日常の解像度」を上げることです。
例えば、「英語を話せるようになりたいのなら、外国人の恋人をつくればいい」という説があります。元武蔵野大学中高の校長先生だった日野田直彦さんも『東大よりも世界に近い学校』(TAC出版)で、「その人のことをもっと知りたい、好かれたいと願って、頼まれなくても必死になるでしょう」と書いています。
モチベーションが高まる面もありますが、僕の友人で実際に外国人の恋人ができたことで英語が上達した人は、
「英語に対する関心が高くなると、日常生活で触れる英語にも自然と意識が向かい、机に向かっていない時も英語の勉強につながっていた」
と振り返っていました。これが、「日常の解像度が違う」ということです。
あらゆることにアンテナを張り、自分でも問いをつくり続ける
東大生はあらゆることにアンテナを張っています。たとえば、みなさんがコンビニで牛乳を買ったとします。もし、東京に住んでいる人が牛乳を買ったなら、その原産地は「群馬県」や「栃木県」「千葉県」など、関東地方の近隣の県名が書かれていることが多いです。
「北海道産の牛乳が多いと思っていた」という人が多いのではないでしょうか?
確かに、群馬県や栃木県にはあまり牛乳のイメージがありません。では、なぜ、ここで牛乳がつくられているんでしょうか?
実は、その答えは小学生の社会の教科書に載っています。「近郊農業」といって、野菜は早く食べたほうが鮮度がいいため、消費地の近くでつくって移動にコストや時間をあまりかけないようにするのです。
同様に牛乳も賞味期限が短く鮮度が大事です。北海道でつくった牛乳を東京まで運ぶとしたらそれだけで時間も労力もかかります。だから、牛乳は消費地の近くでつくられる場合が多いのです。
なにかを食べるときに、「これはこの地域の特産品なんだよなぁ」「これも近郊農業の一環なんだよなぁ」なんて考えて、社会とのつながりを意識すると、なんとなく世界が広がっていくような感覚を掴むことができます。
このように、目の前のことをそのまま受け入れないで、「なぜだろう?」「それは本当だろうか?」と自分で問いをつくり、答えを探す姿勢によって、日常的に目にするすべてのことから学びを得ることができます。これが、僕が多くの東大生を見て感じる、「知識や思考力を身につけるコツ」です。
[2/3ページ]