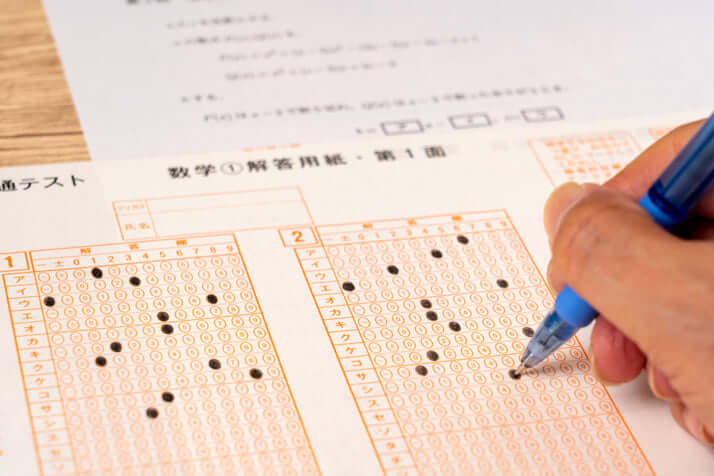新聞を読むだけではNG? 東大生が解説する「時事問題」の本質 試験で差がつく「解ける」「解けない」の決定的な違いとは
大学入試のみならず、公務員・資格試験でも問われる「時事問題」。対策として「新聞を読め」とは言われるものの、読んだとしても苦手意識を克服するのに苦労する人も多い。もしかすると、それは“本質”から逃げていることが原因かも? 『東大生が読み解く ニュースが1冊でわかる本 2025年版』(TAC出版)を上梓した現役東大生で、株式会社カルペ・ディエム代表の西岡壱誠さんは、試験に時事的な問題が出る“理由”を考えることが大切と説く。「解ける人」と「解けない人」との決定的な違いとはいったい――。
(前後編の前編)
***
【写真を見る】自分の生活とは「関係ない」と思う時事問題も、論点を理解すれば?
今年の共通テストで出題された「時事問題」
1月下旬に大学入試の共通テストが行われ、2月1日からは都内の私立中学入試が本格的にスタートしました。2月下旬には国公立大学の入学試験も行われます。この時期になると、「今年はこんな問題が出た」「あの問題は世相を反映した良い問題だ」ということが話題になります。
今年の共通テストでは、例えば「公共、政治・経済」ではふるさと納税(第3問)や、新型コロナ禍やロシアのウクライナ侵攻にともなう国際政治経済のあり方を問う問題(第4問)が出題されるなど、大手予備校では「時事的な出題が多かった」という講評が出されました。
東大でも増える時事問題
こうした問題は社会(地歴、公民)に限らず、国語や英語の長文などで出題されることもあります。つまり、試験で点を取るためには、テキストを読み知識を得るのと同じくらい、新聞などのニュースで時事的な教養を得ることが求められているとも言えるでしょう。
東京大学は、その最たる例です。東大入試には、国語も英語も社会も理科も、数学においてさえ、その当時の世相を反映したような問題が出題され、世間を賑わす場合が多いのです。
例えば東大入試で有名な出題に、「円周率が3.05より大きいことを証明せよ」という数学の問題(2003年)がありますが、これは当時の「ゆとり教育」をめぐる議論のなかで、「円周率を3.14ではなく3と教えていいのか」という論点があったことを反映しての出題だといわれています。数学だろうが理科だろうが関係なく、出題内容には「ニュース」が見え隠れしている場合が多いのです。
[1/3ページ]