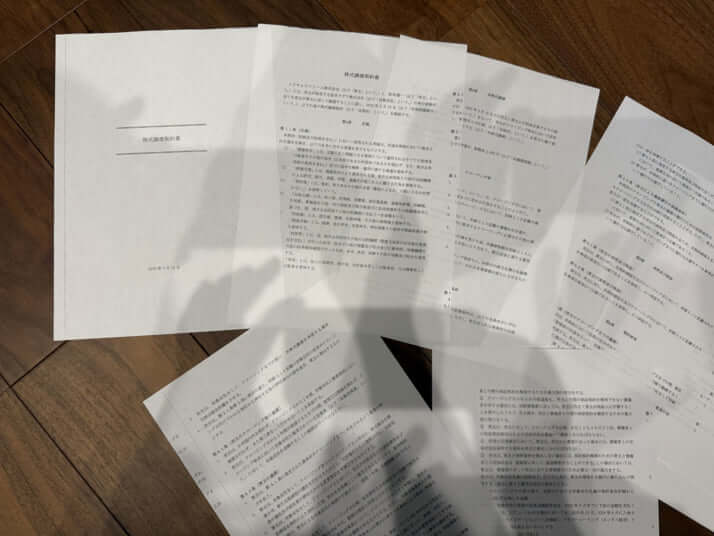「会社の未来を託したはずが」M&A後に待ち受けていた地獄…元経営者の告発に買収側の「言い分」とは
「債務超過のゾンビ企業も、束になれば生き残る道がある」
F社は仲介企業T社を介し、業種の異なる複数の会社をM&Aしている。そうした会社の多くが“被害”にあっているとA氏は訴えるが、まずは、短期間に事業内容の異なる複数の会社を買収した意図を尋ねた。
「M&A市場では、すぐに買い手が付く売り案件がある一方、長く買い手が見つからない会社もたくさんあります。そうした会社は、個々には体力が無く、場合によっては魅力もありませんが、束になれば生き残る道も見出せるという判断の下、業種や業績を問わず買収を進めました」(F社代表取締役)
買収された会社は「後継者不在」を理由に事業継承の手段として、M&Aに応じた例が多い。しかし実際にはそうした会社の多くで事業が行き詰まっている。売り手側の意図と反する事態となっている理由については――。
「後継者が不在というだけで業績に関しては順風満帆だったにも関わらず、私共が引き継いでから急激に業績が悪化し行き詰まったという事例はありません。複数のトラブルを抱えていることは事実です」(同)
A氏の会社をはじめ、事業の行き詰まった理由は、取引先への支払いや、従業員への給与など必要な運転資金が十分に供給されなかったことにある。では、そうした事態を招いた理由は何だったのか。
「前述の通り、私共の買収の特色として、他の買い手からは見向きもされないほど業績が痛んでいた会社ばかりを引き受けました。ほとんどの会社が、売り上げや自己資本にまったく釣り合わない負債を抱えている、いわゆる債務超過の会社であり、もともと運転資金に事欠いていました。“買収したんだから親会社として無条件に供給をするべき”と正論を振りかざされればそれまでで、私共の力不足も大いにあります」(同)
とした上で、複数の会社の買収を進めた理由をこう説明した。
「どの会社も単体では債務超過でゾンビのように生きている状態ですが、日々または月々、大なり小なり売り上げは入って来ます。そして支出のピークは、会社ごと、業種ごとに異なります。こうした入と出のピークのずれを利用して、全体を一つの財布に見立てて資金繰りをすれば、個々では無理な運転資金もうまく回るようになるという狙いがありました。この目論見が思うように機能させられなかったことと、それを補うための親会社としての自己資金の確保が追い付かなかったことが、私共の失敗であり、今後その埋め合わせをしていかなければなりません」(同)
次ページ:「M&Aの買い手として、会社の資産状況を判断材料にするのは当然」
[2/3ページ]