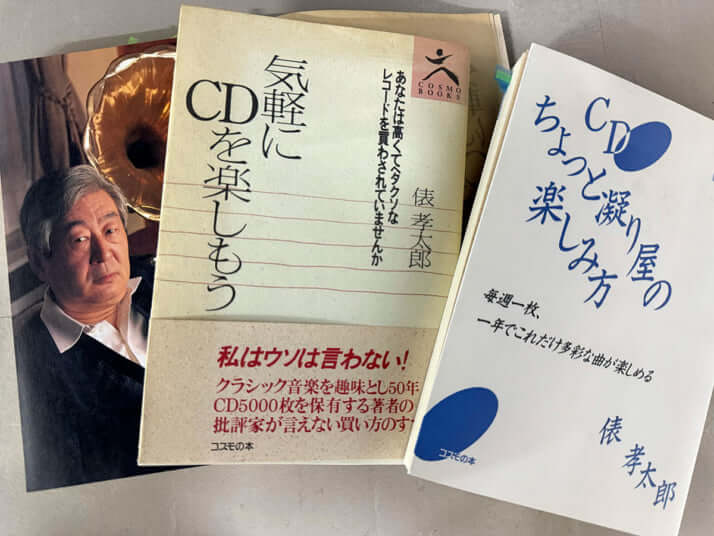「昭和天皇崩御」、「大平総理の内閣葬」では“クラシック通”として活躍 「俵孝太郎さん」知られざる“もう一つの顔”
昭和天皇崩御で特別番組の選曲を
もうひとつ、クラシック愛好家としての俵孝太郎さんを語るとき、忘れてならないのは、1989(昭和64)年1月7日の、昭和天皇崩御です。
〈昭和天皇が崩御されたとき、私はフジテレビの特別番組に、開始から終了まで、一昼夜あまりを、通して出演したが、それとともに、番組の中で演奏する音楽の選曲についても、スタッフの相談に乗った。〉
特別番組のため、スタジオに新日フィルに待機してもらい、ナマ演奏の準備がされていました。しかし首席指揮者の小澤征爾は、その日、日本にいるとは限りません。そこで、小澤指揮の、バッハ《G線上のアリア》だけ、10日ほど前に事前収録されました。涙を流しながら指揮していた映像を、ご記憶の方も多いでしょう。
〈このとき小沢が、“フジテレビのためにではなく、天皇陛下のために指揮するのだから、ギャラはいらない”といって、指揮料を固辞しとおしたことは、関係者以外だれも知らないが、記録しておいていいことだと思う。〉
そのほか、ナマ演奏では、山本直純の指揮で、モーツァルトの交響曲第40番などが演奏されましたが、番組終了時の曲は、俵さんも選曲に苦労されたようです。当初、山田耕筰の交響曲《勝鬨と平和》の美しい第2楽章を候補にしたものの、〈曲名が、昭和時代を諷したものと受けとめられてはまずい〉と見おくりに。ベートーヴェン第9の第3楽章は〈どうしてもフィナーレに結びつけて聴かれる〉と、これも見おくり。結局、別番組のために収録されていた、朝比奈隆指揮の、ブルックナー第7番の第2楽章になったのでした。
このように、俵孝太郎さんは、単なるCDコレクターの枠を超えて、まさに現代史の裏側でも、音楽にかかわっていたのでした。
「いい音楽はひとり歩きするもの」
俵さんは、まだ「Jクラシック」などということばのないころから、邦人クラシック・アーティストの“応援団”でもありました。長年、タワー・レコードのフリー・マガジン「イントキシケイト」にコラム「俵孝太郎のクラシックな人々」を連載されていましたが、昨年12月に出た号の第169回でも、ピアニスト園田高弘をあげ、〈邦人演奏の歴史的遺産の発掘・集大成を!〉と訴えていました。おそらくこれが絶筆か、それに近かったのではないでしょうか。
最後に、俵さんの音楽愛好家としての功績のひとつを。それは、北原白秋作詩・信時潔作曲のカンタータ《海道東征》を、あまり知られていない時期から高く評価していたことです。この曲は、神武天皇の長征を中心に日本建国神話を描く大作で、1940年、皇紀2600年奉祝曲として作曲されました。俵さんは、「せめてまずは、初演時の8枚組SPをCD化してほしい」と訴えていました。わたしも、若いころ、俵さんの話で聴くだけで、いったい、どんな曲だろうと興味津々でした。
〈敗戦後の日本では、神話に対する抵抗がある。それに迎合しているのか、音楽家には左翼が多いのか、それはともかく、この曲は完全に埋もれてしまった。(略)「海道東征」の抹殺は、日本の左翼の偏狭と野蛮を示すものでしかない。〉
その後、曲のみならず、信時潔(1887~1965)の再評価が進み、2000年代に入ってから、本格的に演奏されるようになりました。いまではCDも数種類、出ています。壮大な神話の世界を描く、素晴らしい一大交響音楽です。ぜひ聴いていただきたい名曲ですが、その陰には、俵孝太郎さんの復活への思いがあったのです。もっともご本人は、しばしば口にされていたように「いい音楽は、ひとり歩きするものです」と、平然とされているでしょうが。
あらためて、俵孝太郎さんのご冥福をお祈りします。
[4/4ページ]