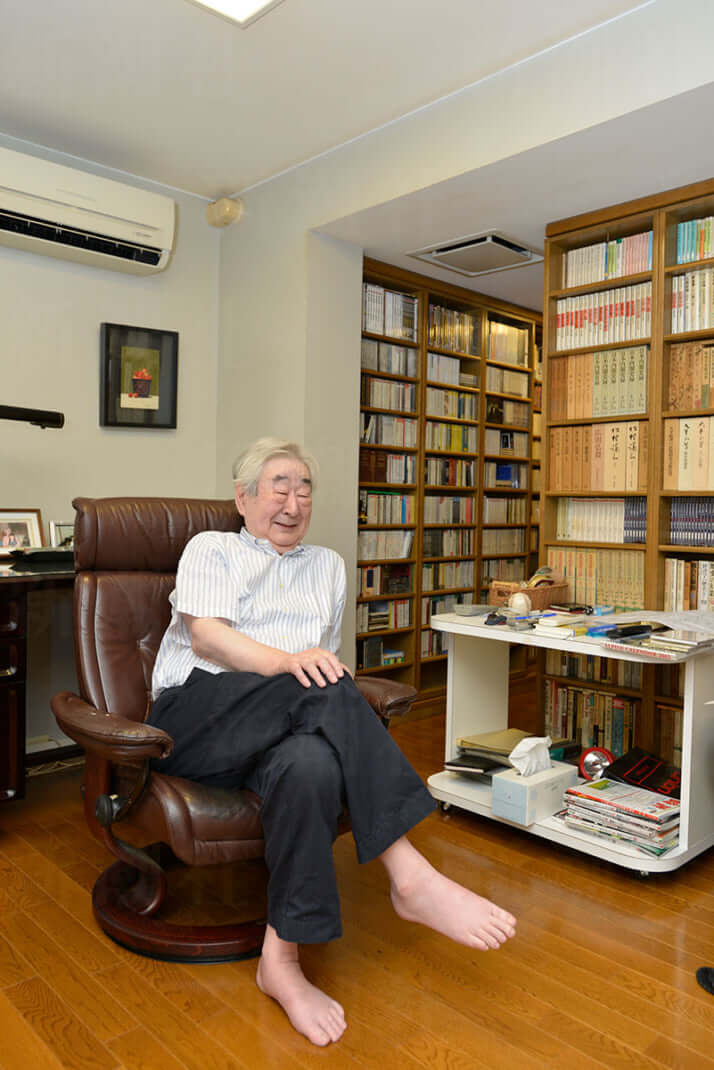「昭和天皇崩御」、「大平総理の内閣葬」では“クラシック通”として活躍 「俵孝太郎さん」知られざる“もう一つの顔”
独特かつ見事な解説
日本でCDが一般に定着しはじめたのは、1980年代前半~半ばころですが、俵さんは、いち早く、音盤蒐集をLPからCDに切り替え、徹底的なCDコレクターとなりました。
その経験をもとに書かれたのが、1991年10月刊『気軽にCDを楽しもう』(コスモの本)です。カバー惹句に〈あなたは高くてヘタクソなレコードを買わされていませんか〉とあります。この本は、前半がCDの効率的な買い方と蒐集の心構えです。〈おたく族呼ばわりを恐れるな〉〈懇意な専門店と中古店をつくれ〉〈余暇時代にこそ教養主義復活を〉など、俵さん一流の“箴言”がつづきます。
そして、こんな厳しいアドバイスも登場します。
〈かつての音楽評論というか、楽曲解説というのはひどいもので、雄麗と優麗と幽麗の、三匹の幽霊さえ飼っていれば、すべての曲は説明できるといわれたものだ。(略)それはあんまりだということになると、小川のせせらぎを聞いてそぞろ歩く気分とか、月光に濡れて野原をさまよう情景とか、トンチンカンな説明が出てきたり、おとぎ話式の物語になったりした。/これでは読まされるほうはあまりにバカバカしく(略)、そんな百害あって一利もないものは、無視するに限るのである。〉
後半は、〈レコード・ライブラリーをつくる50万円3年計画〉です。理想的なクラシックCDの集め方を、驚異的な詳しさでアドバイスしてくれています。
まず、毎月1万円を、CD購入にあてよ、夏と年末のボーナス月には別途1万円をプラスせよ、こうすれば最初の1年間で14万円の予算が組める。2年目はボーナス月に2万円プラス、3年目は3万円プラス。こうして3年間で計50万円の予算となる、というわけです。
〈普通の月は一万円、サラリーマンの小遣いからでも、酒を呑んだりゴルフに行ったりするのを慎めば、出せないという額ではない。CDを聴きはじめたことによって、飲み屋のツケをためることがなくなれば、ボーナスからの一万円も軽いだろう。〉
有無をいわせぬ論法で、では具体的に、どんなCDを、いくらで、どういう順番で買っていけばよいかが、微に入り細に入り、解説されるのです。
たとえばベートーヴェンの交響曲9曲は、1曲ごと買うのはムダで、(執筆時点で)全集が32組出ている、そのうち1万円で買えるものが6組ある……〈朝比奈とカラヤンは外税の一万円〉……その特徴は……といった具合です。こんなガイドブックが、いままで、あったでしょうか。
こうして3年かけて完成する、俵さんいわく〈空想のレコード・ライブラリー〉は、巻末一覧にまとめられていますが、そのままクラシック音楽史にもなる、見事なリストです。
実は、いま読み返すと、具体的なCDアドバイスもさることながら、消費税は〈先進国はおろか発展途上国でもいまや標準的な税制である〉とか、〈いまどき、風前のともしびのレコードの再販制度を杓子定規に守って、メーカーが指定した価格で売っている店〉は少ない、どこも会員制度やクーポンで事実上割り引いているとか、いかにも政治評論家らしい解説があり、痛快です。
[2/4ページ]