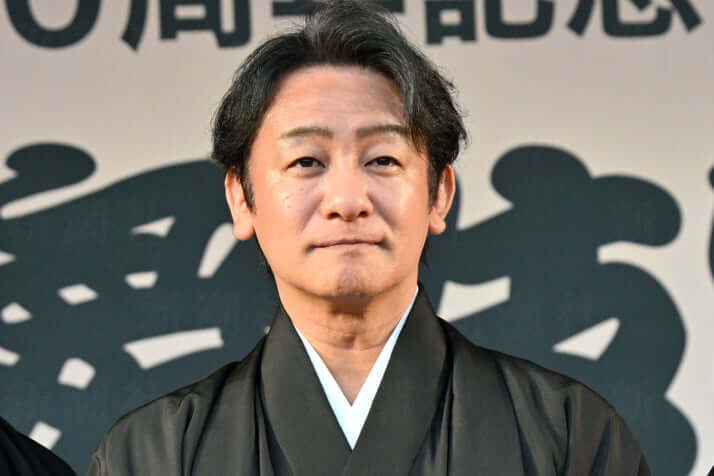【べらぼう】蔦重を甘い罠にかけた 片岡愛之助「鱗形屋」の哀れな最後
蔦重の錦絵出版計画
第3回「千客万来『一目千本』」(1月19日放送)で、主人公の蔦屋重三郎(横浜流星)は、吉原の女性たち120人あまりを生け花に見立てた画集『一目千本』を、自身が版元として出版。これが大当たりして吉原に客が戻った。NHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』の話である。
【写真】作中の“何も着てない”衝撃シーンを演じた「元宝塚トップスター」ら
ところが、続く第4回「『雛(ひな)形若菜』の甘い罠(わな)」(1月26日放送)では、さらに吉原を盛り上げ、自分の事業も発展させようともくろむ蔦重が、文字どおりに「甘い罠」に引っ掛かるところが描かれた。
蔦重が企画したのは錦絵の出版だった。錦絵とは多色刷りの木版画のことで、錦のような彩りなのでその名がある。一般にイメージされるカラーの浮世絵はすなわち錦絵で、鈴木春信が明和2年(1765)に完成させた。蔦重は平賀源内(安田顕)の示唆をヒントにひらめいて、吉原の女性たちを錦絵にし、彼女たちに呉服屋が売り込みたい着物を着せれば、着物の宣伝を兼ねて呉服屋が制作費を入銀(本の出版前に事前に納める金銭)してくれる、と思いついた。
だが、蔦重が呉服屋と交渉しても、なかなか色よい返事がもらえなかったが、錦絵が得意な地本問屋(地本とは江戸生まれの本)の西村屋与八(西村まさ彦)が、自分のところ売るし、ほかの本屋でもあつかうように交渉すると提案してきたので、蔦重はよろこんで同意した。実際、西村屋の協力を得たとたん、呉服屋たちも入銀に応じるようになり、事は順調に運びはじめた。
美人画の第一人者に描かせた連作錦絵
絵師は磯田湖龍斎に決まった。鈴木春信の影響を強く受けながらも、春信よりふくよかで肉感がある画風で、美人画の第一人者としての地位を確立した絵師である。こうして誕生した色鮮やかな『雛形若菜初模様』は、安永4年(1775)から天明元年(1781)ごろにかけて、約140点が出版された連作錦絵で、湖龍斎の代表作になった。
「若菜初模様」とは正月にはじめて着る着物の柄のことで、「雛形」は衣裳の見本を意味する。実際、絵には流行の着物をまとい流行りの髪型をした花魁が描かれ、それ以外の生活スタイルに関しても、まるでカタログのように描写されている。
史実についていえば、『雛形若菜初模様』に蔦重が、どのようなかたちでどの程度かかわったのか、明確なことはわからない。ただ、初期に刷られたものなかに、西村屋の屋号「永寿堂」と一緒に蔦重の屋号「耕書堂」の印があるものが10点以上確認されている。
このため、ドラマの時代考証等を担当している鈴木俊幸氏は《吉原が西村屋に働きかけて実現した企画であろうし、その橋渡しをしたのが蔦重であったろう》と書き、また女性たちを描かせる順序などについても《調整と協力依頼を継続的に行い、吉原における販売を手掛けたのも蔦重であったはずである》としている(『蔦屋重三郎』平凡社新書)。
[1/3ページ]