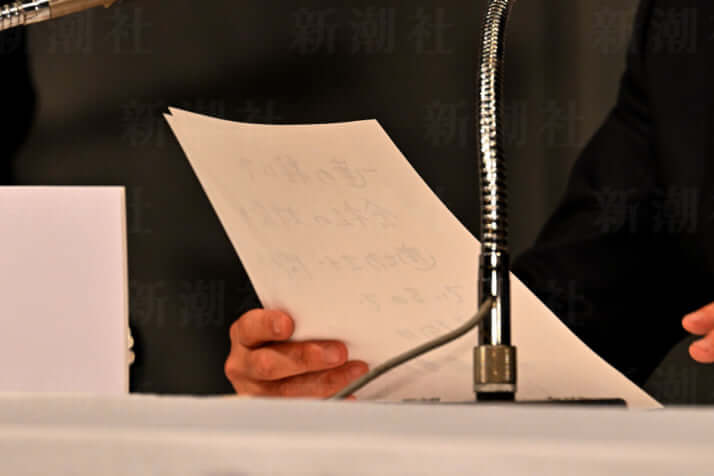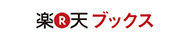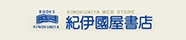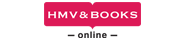「致命傷会見」フジ・港社長が理解していなかったリーダーの心得 決断が他人の人生を左右する
なぜこんな人が、私の上司なんだろう
フジテレビが揺れ続けている。
1月17日に行われた記者や取材方法を限定しての社長会見は猛烈な反発を生んだ。
続き、23日に開かれた社内の説明会では経営陣総退陣を求める声も上がったという。
そして27日に行われた、オープン過ぎる記者会見では、社長、会長が辞任すること、10時間以上対応したこと、一部記者らのレベルが低過ぎたことなどが奏功して、一定の同情を集めることには成功した。
とはいえ、依然として厳しい目が同局には向けられている。今後は、事態の解明や改革に加え、日枝久・取締役相談役の進退も焦点となっていくだろう。
たった10日ほどでの怒涛の展開。フジテレビ社員からすれば、17日の会見でなぜあそこまで下手を打ったのか、という思いは拭えまい。
〈「なんでこんな人が、私の上司なんだろう」
そんなストレスを感じながら、日々仕事をしているビジネスパーソンは、多いのではないだろうか。
無理もない話で、管理職や要職にある人であっても、まともなリーダー教育を受けたことがある人などほぼ皆無だ〉
これは『なぜこんな人が上司なのか』(桃野泰徳著)という本の冒頭部分である。著者の桃野氏は中堅メーカーなどで最高財務責任者(CFO)などを務め、経営再建に携わるなどの経験を積んできた人物だ。
同業者や世論の猛反発、株主の怒り、スポンサー企業の撤退、そして当事者・中居正広の引退……そのすべての原因とまでは言えぬまでも、事態を致命的に悪化させたのが、17日の港浩一社長の記者会見だったのは間違いないだろう。社員からすれば、まさに「なぜこんな人が……」という気持ちだったのではないか。
ただし、これは多くの企業にとっても切実な問題だ。
港社長はコネやゴマすりで社長にまで昇りつめたわけではない。極めて優秀なテレビマンだった。黄金期のフジテレビを代表する数々の番組に関わり、とんねるずなどをスターに押し上げた功労者とされてきた。自身が番組などに登場することも珍しくなかったが、おおむねそれも好意的に受け止められてきた。ある時期のテレビ界を代表するヒットメーカーだったのだ。
また、プロデューサーとしてプロジェクトを束ね、成功させてきた実績もある。
出世の要因の一つがこうしたキャリアだったというのは衆目の一致するところである。
問題は、この成功体験やキャリアが、桃野氏が指摘している「リーダー教育」の役目を果たしているのか、という点だろう。ヒット番組を作った、ヒット商品を作ったといった功績によって出世する人は珍しくない。むしろ功績を評価しない組織には問題がある。
しかし彼らの能力、あるいは培ったノウハウは、リーダーとして適切に振る舞うことにどれほど貢献するのか。これはプロ野球でもよく議論になる「名選手は名監督となりうるのか」とも共通する問題である。
リーダー教育不在の国、日本
冒頭の桃野氏の文章は、こう続く。
〈そもそもリーダーとはどういう存在か、リーダー自身がまともに考えたことすら無いのである。そんな経営者や管理職の下で仕事をしていれば、ストレスがたまらないほうがおかしいだろう。
「そんなことはない、俺はちゃんと管理職研修を受講した」
そう思う人もいるだろうか。
例えば陸上自衛隊では、数十人の部下を任される小隊長になるまで概ね1年間、幹部候補生学校で教育を受ける必要がある。この教育を修了する頃、候補生たちは部下全員にメシが行き渡ってから初めて箸を持ち、部下の誰よりも後に風呂に入る「リーダー像」が心と体に焼き付いている。「管理職研修」で果たしてそこまで、リーダーの定義やあるべき姿について考えることができただろうか。
結局のところ、世の中に存在する経営者や管理職と呼ばれる人の大半は、まともなリーダーであるはずがないのである。
そしてそんなリーダーが率いる会社や組織が壊れていく様を、私は経営再建の現場で数多く見てきた。部下の心を壊し、仕事の妨げになっているリーダーたちと向き合ってきた〉
現場で必死に働き、成果を出してきたという実績だけではリーダーは務まらない、とはずいぶん厳しい指摘のようにも見える。そもそも実績すらない人は人望を集めづらい。ヒットメーカーがトップに立つこと自体は決しておかしなことではない。
しかしながら自衛隊のような幹部教育システムのある企業はほとんどないのもまた事実。
人の人生を左右するという自覚があるか
一連の騒動について桃野氏はどう見ているのか、日本の企業に足りないものは何か、改めて見解を聞いてみた。
「報道で知る限り、フジテレビ・港社長の立ち居振る舞いは個人の利益の最大化を目指しているものであり、部下や関係者からの“幸せ搾取”をしているように見えました。
プレイヤーとして優秀でも、リーダーとして無能であるという意味で、反面教師としては最高の教材となったのではないでしょうか。
組織は単なる人の固まりではありません。そのことを文字通り、国の命運と部下の命を預かりながらたたき込まれているのが幹部自衛官です。だからこそ、候補生教育から始まり、一生を通じてリーダー教育を学び続けるのです。
しかし拙著で書いている通り、民間企業でそんなことをしている会社はまずありません。
言い換えれば、民間企業の多くのリーダーたちは、自分の利益にしか関心を持てるわけがないインセンティブの中で仕事をしているということです。そんなリーダーや上司に、本当についていきたいと思えるでしょうか。多くの会社では、そんなエセリーダーに社員の人生を預けて、“組織ごっこ”をしているのです。
多くの人の人生を左右する存在だということをリーダーとなる人は強く認識してほしいと考えます」
社員のみならず、非正規で働くスタッフ、番組関係者など数多くの人にすでに大きな影響を与えている。公的な存在であるテレビ局にとっては、スポンサーはもちろん一般視聴者も十分ステークホルダーだ。
その人生に影響を与えうる立場だという自覚が、経営陣にあっただろうか。