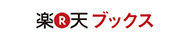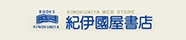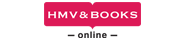政治家の「パワハラ」は「ブラック霞が関」を強化する 追及パフォーマンスの副作用とは
変わらない「ブラック霞が関」状態
6月11日に放送された「クローズアップ現代」のタイトルは、「悲鳴をあげる“官僚”たち 日本の中枢で今なにが?」。霞が関の官僚たちのブラックすぎる労働環境についてのレポートを見て、そのキツさに衝撃を受けた方もいれば、「まだこんな状態なのか」とあきれた方もいることだろう。
番組に出演していた元厚生労働省官僚の千正康裕(せんしょうやすひろ)さんが、官僚たちの置かれた苛酷すぎる状況を詳述した著書『ブラック霞が関』を発表したのは2020年のこと。それから4年近くがたち、民間企業が「働き方改革」を進める中、指導する立場の官庁では相変わらず残業を強いる状況が改善されていないようだ。
官僚の仕事量を増やし、残業が避けられない原因の一つが、国会対応の業務である。その実態を同書から見てみよう(以下、『ブラック霞が関』から抜粋、再構成しました)。
***
速報母グマを駆除された「子グマ」が「冬眠できない」“衝撃”の理由 「街中を徘徊する幼獣」に襲われないためには
速報高市首相に3000万円寄付した謎の宗教法人「神奈我良(かむながら)」の実態とは 専門家は「実態が不透明な法人が大金を捻出しているのは不可解」
国会審議前日の夕方から夜にかけて、質問者の国会議員から省庁に対して質問内容が通告される。自分の部署が担当する内容に関する質問であれば、そこから急いで答弁メモを作成し、関係部署とも調整を済ませ、上司の決裁をとり、必要な資料を整えて、翌日早朝の大臣の出勤に間に合わせる。国会本番の前に大臣と官僚の間で行われる答弁方針を決める勉強会(「答弁レク」という)に使うからだ。当然、国会質問が頻繁に当たる部署もあれば、ほとんど当たらない部署もある。
国会審議が当たる部署というのは、世間の注目度が高い重要政策を担当している部署である
忙しくても、自分がやっている仕事が社会の役に立つ意義のあるものだと思えば、乗り越えられるし、プロジェクトが終わった時には、達成感と成長の実感を持てるものだ。実際に、ニーズの高い法律改正のような仕事をしていて精神を病んで休職に追い込まれるケースは少ない。一番きついのが、国会対応、野党合同ヒアリングなどである。
先ほど説明した通り、国会審議は、ぶっつけ本番のアドリブではない。質問者の問題意識を答弁する役所側に事前に伝え、それに対する方針を官僚と大臣が議論して、どのように答えるのかを決めて本番に臨むのだ。
そう聞くと、「なんだ、出来レースの茶番なのか」「大臣は官僚のメモを読むだけか」と思う方もいるかもしれない。しかし、そうではない。どんな優秀な大臣でも、幅広い役所の隅々まで細かいことを把握するのは不可能だ。事前に質問者の細かい問題意識を理解した上で、それに対する具体的な答えを準備しないと、全てが「ご指摘の点については、実態を把握した上で検討してみたいと思います」というような抽象的なやりとりになってしまい、議論が前に進まないのだ。
事前に質問者の国会議員の問題意識を官僚が聞き取って、過去の経緯や各方面への影響なども考慮しながら、役所としての方針を答弁メモに落とし込んでいく。そのメモの内容をベースに、大臣と議論をして官僚が作った答弁書を、大臣の指示で前向きに書き換えたりしている。そうやって大臣が理解した上で方針を指示して、修正した最終版の答弁書を持って大臣は国会で答弁しているのだ。
国会質問によって政策を動かしていくためには、この大臣と官僚の議論が実はとても大事だ。この過程で大臣が理解した上で方針が決まり、政策が前に進んでいくからだ。
揚げ足取りや政府の失点を狙うのではなく、質問の機会を通じて政策を前に進めようとする国会議員は、野党議員であってもこの事前の通告を丁寧に行う。こうした野党議員の指摘を受けて政策を見直すことも、決して珍しいことではない。質問の背景には実際に困っている国民がいるので、大臣も「痛いところを突かれた」と思うと、部下の官僚に対応を指示するのだ。
前日夜の質問通告が国会待機と深夜残業の元凶
質問内容を質問者の議員が省庁に事前に伝えることを「質問通告」という。「通告されていないので、すぐに答えられない」と総理や大臣が答弁している姿をテレビで見た方もいるかもしれない。この質問通告のタイミングは与野党の申合せで原則2日前の正午までに行うこととされているが、その期限が守られることはほとんどなく、前日の夕方から夜にかけて通告されることが多い。内閣人事局が全省庁を対象に行った「国会に関する業務の調査・第3回目 (調査結果)」(2018年12月28日)によると、質問通告がすべて出そろった時刻の平均は、前日の20時19分である。
国民の負託を受けた国会議員からの質問になるべく丁寧に答えようと準備するのは当たり前だが、事前通告が前日の夕方から夜にかけてなされる限り、深夜から明け方までの対応が必要になり、官僚の睡眠時間は削られ続ける。中には、役所が気づいていない鋭い質問によって政策が動くこともあるが、単なる揚げ足取りのような質問もあるし、そもそも「待機児童対策について」とか「新型コロナウイルス感染症について」など、項目しか通告してこない国会議員もいる。
そういう項目だけの通告の場合、あわせて「問合せ不可」という指示を役所にしてくることが多い。具体的に何を議論したいのか、質問者の議員に確認することもできない。そうなると様々な質問を想定して大量の想定問答を徹夜で作成することになる。何が精神的にきついかというと、こういう作業のせいで本来やらなければいけない政策を考える仕事が進まなくなることだ。
夕方から朝まで寝ずに国会答弁を作成した後、日中は本番でどんな質問が出ても対応できるように官僚は国会に同席する。夕方、役所に戻ってくると、フラフラだ。しかし、元々やらなければいけない仕事は何一つ進んでいない。そういう日々を続けると、自分の時間を国民のために使えている実感がなくなり、どんどん疲弊してくる。
野党合同ヒアリングで答えられない官僚
国会以外にも、国会議員が官僚に説明を求める場面はたくさん存在する。個別の国会議員が説明を求める「議員レク」、文書で資料を求める「資料要求」、そして各政党の会議への出席依頼だ。これらも、国会議員や各政党が政策を議論するための説明だから、民主主義のプロセスとして大切な仕事だ。とはいえ、不祥事や政権を追及するようなテーマの時の野党合同ヒアリングは、精神的にかなりきつい。
2000年代半ばからこうした会議はテレビカメラ入りで行われるのが通例となり、テレビで放映されるようになった。最近はインターネットでも動画配信される。議論が国民から見えるようになったのはよいことだが、テレビが入るとなると追及する議員側も厳しく追及する姿勢を見せたいという事情もあり、時にはパワハラに近いような追及も見られる。
もちろん、野党が必要とする回答や情報を政府が出さないから、より追及が激しくなるというケースもあると思うし、政府は説明責任を果たすべきとも思う。ただ、官僚の判断で勝手に野党に新しい回答をすることは許されていない。善し悪しはさておき、政権の立場からすれば、追及のネタを提供するなと考えるのは当然だろう。従って野党に新しい回答や情報を提供するためには、大臣など役所にいる政治家の幹部の了解が必要となる。
つまり、野党合同ヒアリングに出席している官僚は、ゼロ回答をしなければならない前提で追及の矢面に立つことになるので、要領を得ない説明を繰り返すことになる。
野党が不祥事などを追及する会議に、回答の権限を与えられていない官僚を出席させて、「厳しく追及している姿を国民に見せる」以上の意味があるのかは疑問である。回答する権限のある政治家の幹部が説明すべきだろう。政策がテーマなら詳しい官僚が出て行って説明すればよいが、森友学園、加計学園、桜を見る会の問題などは政権の姿勢を追及する話なのだから政治家同士で議論すべきと思う。
***
官僚を問い詰める姿は「絵」になる。また官僚、官公庁をチェックするのも政治家の役割である。しかし官僚を疲弊させることは、決して国益につながるものではないことを少なくとも政治家は肝に銘じるべきではないか。