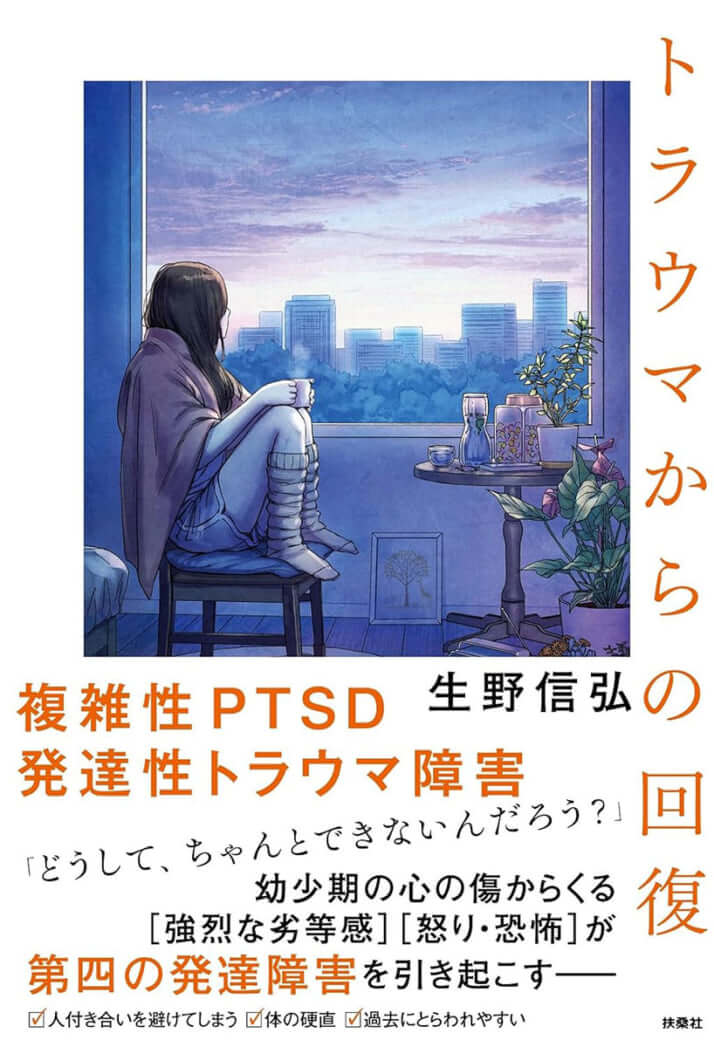急増する「大人の発達障害」 “幼児期のトラウマ体験”で傷ついた人を助ける“意外な存在”とは
自分が自分の親になる
実は、慢性的にトラウマ体験を受けてきた人の多くは、成人後も親、あるいは他者に対する「依存欲求」がまだ残っています。
成人後に養育者との関係を断ち切り、折り合いをつけていると表面上は思っていても、心の底では依存欲求がくすぶっているというパターンもあります。ただ、この場合の依存欲求というのは「今の自分が高齢となった親の愛情を求めている」のではなく、「過去の自分が親の愛情を求めていた」と自覚する必要があります。
幼少期に親から「よしよし」してもらいたかった、感情を受け止めてもらいたかった、でもそれはもう叶わないことなのだ……。その事実を受け入れ、依存欲求を断ち切り、自分で自分のアイデンティティを作っていくのです。
そうしたプロセスのなかで、辛かった過去の自分に会いに行き「自分が自分の親になる」ことが求められます。クリニックの治療では、具体的なトラウマ体験の出来事を聞き出すことはありません。一方で、子ども時代はどんな気持ちで過ごしていたのか、本当は何を求めていたのか、何に傷ついていたのか、といった傷つきへの自覚を促します。
そして、自分がその子の親だったら何をしてあげるのか、どんな言葉をかけてあげるのかを考え、今の自分が過去の自分を助けてあげるのです。
***
本記事は『トラウマからの回復』(扶桑社)より、一部を抜粋/編集してお伝えした。本書では、実際にクリニックに訪れた社会人女性「ハナさん」と医師とのカウンセリング風景などを通し、「複雑性PTSD」、「発達性トラウマ障害」の症状や診断基準を詳しく解説している。