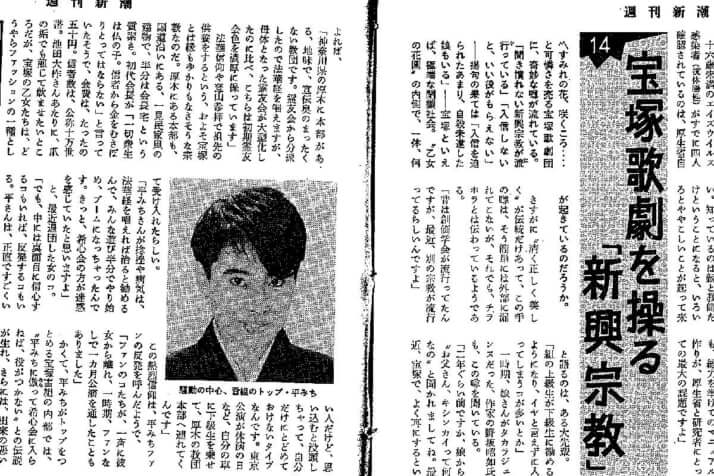【宝塚歌劇団】新興宗教、イジメ裁判、美人局…「美しくも清くなかった」黒歴史を元週刊誌記者が証言
OGが蜷川演出に耐えられた理由
平みちは、もともと花組で、雪組に異動になったのが1983年。このとき、彼女と入れ替わりで雪組→花組へ異動になったのが、1期上の先輩、高汐巴である。
「その高汐は、花組でトップをつとめ、1987年に退団します。2年後、彼女は一種の“暴露本”とも思える書籍を出版するんです」
それが、『清く正しく美しく』(日之出出版)なる回想記だった。もっともご本人は“暴露”などしたつもりはなく、あくまで現役時代の思い出を普通に綴ったつもりだったのだが、一般人には驚きの内容だった。
「音校時代の異様な習慣が赤裸々に描かれていました。《阪急電車に乗る際は最後尾の車両》《ハンドバッグは禁止。阪急デパートの紙袋しか持ってはいけない》、守らないと《本科生の円陣の真ん中に中腰で座らされ》て罵声を浴びる。歌劇団員になっても先輩の世話で疲れ果て、舞台本番でようやくホッとして居眠りをする……」
そんな宝塚の空気の重さを、逆の形で証明した新劇があった。先の演劇記者が回想する。
「それは、1982年に日生劇場で初演された、清水邦夫作の『雨の夏、三十人のジュリエットが還ってきた』です。これは、戦前のたった5年間、福井のだるま屋百貨店(現・西武福井店)に存在した《だるま屋少女歌劇部》がモデルの芝居です。この演出が蜷川幸雄だったのですが、なんと、少女歌劇OG役30名全員に、本物のヅカOGを起用したのです。主演級だけは、淡島千景、久慈あさみ、甲にしき、汀夏子といった現役女優でしたが、ほかはすべて、いまでは芸能界とは縁のない一般OGが招集されたので話題となりました」
問題は、のちに「靴や灰皿を投げつける」「聞くに堪えない言葉で怒鳴る」との伝説までが生まれる、蜷川幸雄の過酷な稽古だった。いくら元ヅカガールとはいえ、すでに現役を離れてかなりたつ“オバサマ”たちが、蜷川スパルタ演出に耐えられるのか? 初演前に崩壊するのではないかとさえ噂された。
「ところがヅカOGたちにとって、“灰皿が飛んでくる”蜷川演出など、屁でもなかったのです。たしかにスパルタ稽古でした。『もっと泣け!』『バカ!』『ブス!』の連続です。しかし彼女たちは嬉々として怒鳴られていました。いくら罵られてもいっこうにめげない。宝塚時代のイジメに比べたら、蜷川演出など、どうってことなかったのでしょう」
さて、宗教に凝ったり、先輩のお小言やイジメだったら、まだ思い出話ですむ部分もある。だがこれが、裁判沙汰や犯罪にまで発展するとなると、話は穏やかではない。
[3/4ページ]