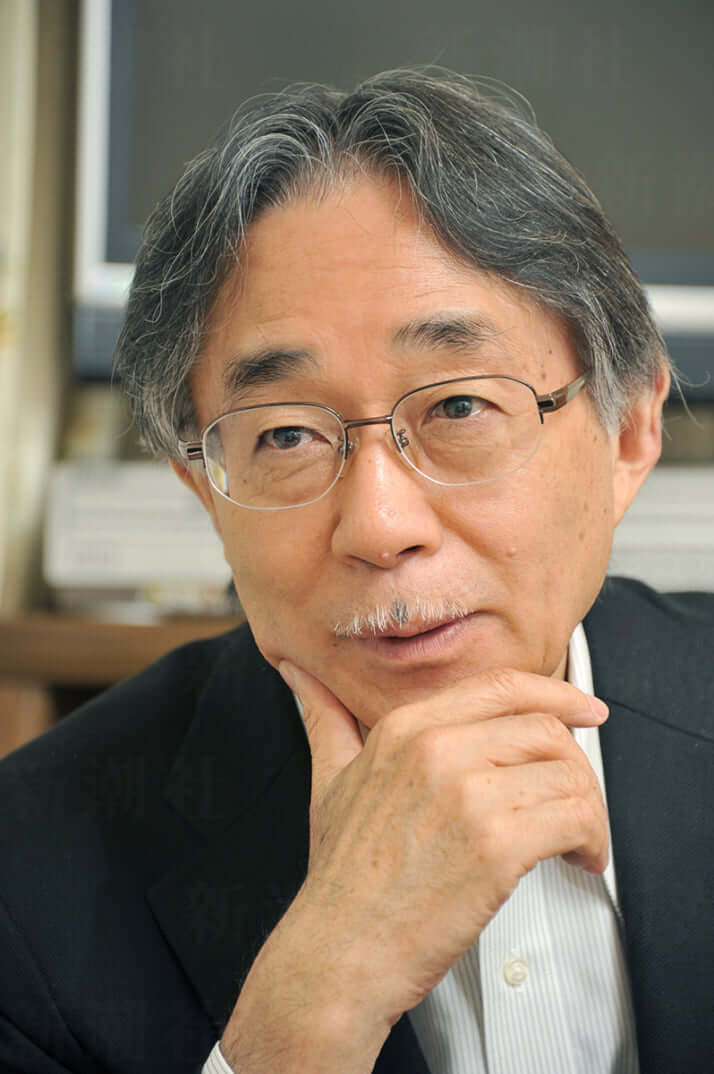抗がん剤治療をせずに「ステージ4から4年」「腫瘍縮小状態を維持」 当事者が明かす「がん共存療法」
取材中止も…
上記のような、いわば私の決意表明に共感や励ましの言葉を贈ってくださる人もいた。だが、私のそれまでの緩和ケアの取り組みをテーマに予定されていた講演の主催者からは、週刊新潮の記事を読んだ講演参加予定者であるがん治療医から不快である旨の連絡があったと、講演内容に関する懸念を伝えられた。私は、主催者に迷惑が掛からないように配慮すると返事した。その他にも何人かの知人から、記事に対する批判や非難があると知らされた。予測していたことだったので、知人には謝辞を述べて、それでも、私は揺るがないと返事した。
同じ頃、私がステージ4の大腸がん患者であることを公表してから依頼を受けて始まった複数のメディアの取材は、記事にすることは結果的にエビデンスもない代替療法である「がん共存療法」を肯定することになるとの指摘もあり、記事にするための社内合意が得られなかったと、どれも取材半ばで、丁寧に取材中止を伝えられた。
「がん共存療法」は、私の個人的実体験に基づいて組み立てた療法である。拙著の中でその理論的背景も含め詳述したが、エビデンスがない以上、全て、まっとうな反応だと思った。それぞれの申し入れに、素直に分かりましたと応答した。
そのような冷ややかな、しかしまっとうでもある意見に応えるために、私に残された道は、とにもかくにも、「がん共存療法」のエビデンスを得るための臨床試験を実現することだと考えた。でも、どうすればよいのだろう。
悶々とした日々
まず、私は、全国的規模で在宅医療に先進的に取り組んでいる、医療法人社団悠翔会の理事長である佐々木淳医師に相談してみた。
佐々木理事長は、私がステージ4の大腸がん患者であることや高齢であることで、それまで取り組んできた24時間対応のクリニックの運営の限界に直面した21年秋、親身に相談に乗ってくれた。そして、私が院長であったケアタウン小平(こだいら)クリニックを22年6月から継承してくれたのである。
その佐々木理事長は、悠翔会の倫理委員会の承認が得られれば、クリニックの外来で臨床試験に取り組めるのではないかと言ってくれた。うれしかった。しかし、訪問診療を前提に開設した手狭なクリニックの外来で臨床試験を行うことは現実的ではないとも考え、謝意を伝えながらも、少し検討させてほしいと返事を留保した。
進むべき道に揺らぎはなかったが、どう具体化するか先の見えぬ悶々とした日々が続いた。そんな22年7月半ば、天啓のような二つの朗報が飛び込んできた。
[3/8ページ]