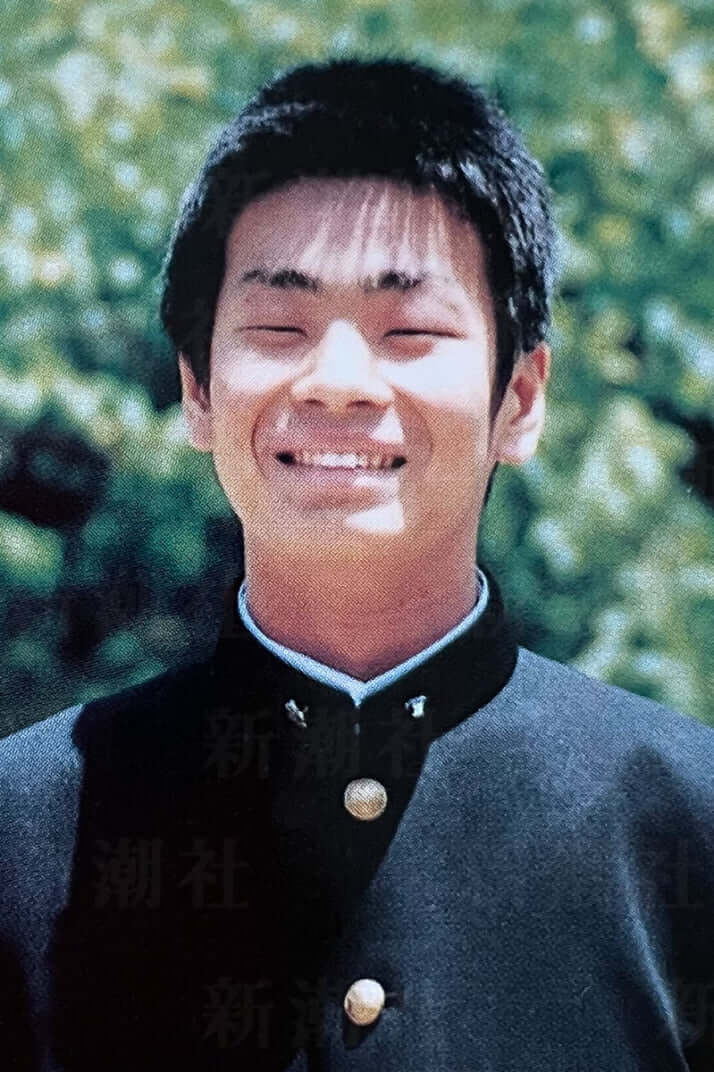奈良地裁に山上被告の減刑嘆願署名を送った女性の告白 母親は「生長の家」の信者 性自認で葛藤した人生 「いきなり死刑が執行されれば彼は無念に違いない」
男性に見られない悩み
大学を退学すると、いわゆるフリーターになった。バンド活動に明け暮れながら、様々なアルバイトを経験した。世の中はバブル経済の絶頂期で、生活に困ることはなかった。
その一方で、自分が女性であるということに違和感を覚えることが増えた。アルバイト先で「ひょっとするとこれは天職かもしれない」と思えるような仕事に出会った。そういう職場では上司も斉藤さんを評価し、好意を示してくれた。それを「気持ち悪い」と受け止めてしまう。
「私は背が低いことがコンプレックスでした。そして上司に『小さくて可愛いね』と言われると、悪意ではないのは分かっていても、気持ち悪いと感じていました。悪意はなく、純粋に好意ですから、セクハラとは思いませんでした。とはいえ仕事上の関係なので、『小さくて可愛いね』という言い方は不適切です。何より『可愛い』というような、『それは本当の私ではありません』という点を褒められると、どうしても不快な気持ちになってしまうのです」
好景気なのでバイトを辞めても、次のバイトはすぐに見つかる。とはいえ、天職かもしれないと思った職場を辞めることは辛かった。斉藤さんは「自分が男性として働ける職場であれば、働きやすいのではないか」と考えるようになった。
「30歳になると男性ホルモンの注射を始め、溶接工の資格を取って工場で勤務しました。同僚には恵まれましたが、男性としては見てもらえませんでした。女性から男性へのトランスジェンダーでも、体のつくりや顔の輪郭が原因で、男性に見える人と見えない人に分かれます。特に10代でホルモン注射を始めた人と、私のように30代で始めた人では全く違うのです。子供と一緒に自転車に乗っているお母さんが、私がトランスジェンダーだと気づいて、『あ、恥ずかしい人間』と子供に言ったこともあります。そういうことは日常的にありました」
嫌韓・嫌中
そしてバブルが弾けた。工場は無理な納期の仕事でも受注し、深夜までの残業が常態化した。夕食のため工場でコンビニ弁当を口にした工員が、朝礼で「時間の無駄」と叱責された。斉藤さんも無理な勤務を続けていると、手が震えるようになった。溶接工としては致命的な問題で、慌てて整体クリニックを受診すると、「今の生活を止めない限り、治ることはありません」と言われた。
その後はアルバイトを転々としていたが、生活は苦しくなっていった。そのため斉藤さんは40代の半ばで一度、実家に戻った。2000年代のことだ。再び両親と共に暮らしてみると、年老いた父親は優しくなっていた。だが、それよりも驚いたのは、母親だけでなく父親も右傾化していたことだった。ちなみに、多くの識者が「2000年代からネット右翼というネットスラングが定着した」と指摘している。
「私が子供の頃は、母の右翼的な考えを巡って夫婦喧嘩が絶えなかったはずなのに、なぜか父も右翼になっていました。理由は分かりません。母に取り込まれたのか、そういう本か雑誌を読んでしまったのか……。しかも母だって昔はもっと、日本の防衛問題とか、天皇に対する敬愛の念とか、それなりに高尚な議論もあったはずなのです。ところが家に帰ってきてからは、単なる嫌韓・嫌中の発言が桁違いに増えていました。タクシーの運転手さんにも『韓国人や中国人は泥棒が多い』と話しかけたりして本当に嫌でした」
[4/6ページ]