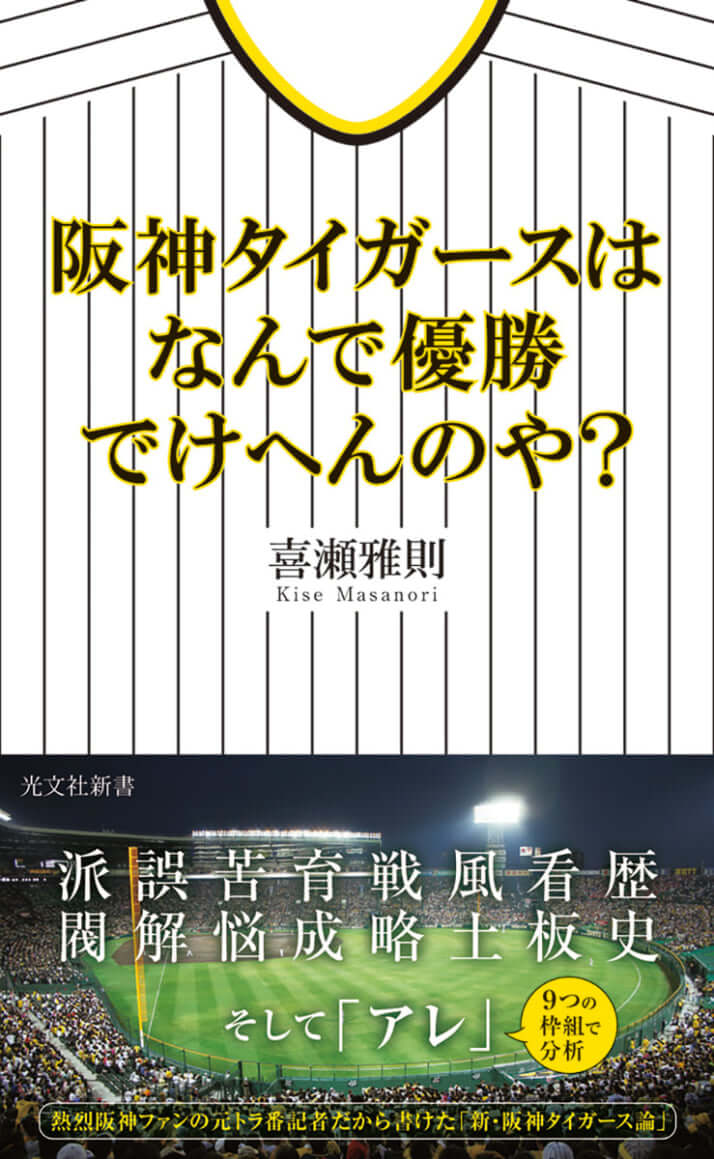阪神が優勝できなかった本当の理由…ドラフト指名の“失敗”を恐れて「暗黒時代」を招いたスカウト戦略
近鉄の4位指名は「中村紀洋」
しかも、萩原の“評価の基準”が『甲子園』に寄りかかっていたと指摘する菊地が、さらに挙げた問題点は、近鉄の4位が大阪・渋谷高の中村紀洋だったことだ。
日米6球団、23年間で通算安打2106本、404本塁打を放つ大打者に成長した中村は、大阪府立渋谷高での2年夏、甲子園に出場している。当時から「4番・サード」で、2番手投手も務めていた。公立高で、激戦区の大阪を勝ち抜いた原動力であり、その潜在能力たるや、計り知れないものがあったはずだ。
ただ、甲子園での実績やネームバリューでいえば、その時点では萩原が“上”だ。
「でもスカウトという立場から言えば、萩原誠を1位で推薦しちゃダメなんだよ。やっぱり中村じゃなきゃ、おかしいんですよ。スカウトは同じ地区で、萩原と中村を同じくらいの数は見ているはずなんですよ。中村は近鉄の4位でしょ? 中村の評価をしていなかったということは、関西担当のスカウトがダメでしょ、という、そういった話が出てこないとおかしい。そういうのは反省してかなきゃいけないところだと思うんですよ」
その中村を「ミスター大阪」と断言していたスカウトがいた。
当時、近鉄のチーフスカウトだった河西俊雄は、かつて阪神のスカウトとして、市和歌山商・藤田平、大阪学院高・江夏豊ら、高卒選手の秘めた能力を見抜き、ドラフトでの上位指名にこぎつけていた。その名うての目利きが、中村の「打」を高く評価していた。その年、近鉄は上位指名3人が投手。つまり、野手の最上位となる「4位」が中村だったのだ。
「阪神に行きたくない8カ条」
1991年には、大阪に萩原と中村という高校生野手の逸材がいた。さらに、その大阪の隣・兵庫県には、即戦力の評判を取った関西学院大の遊撃手・田口壮がいたのだ。
甲子園球場のある西宮市生まれ。県立西宮北高から関学大に進むと、22年秋季リーグ終了時点でも依然として関西学生リーグの「最多安打記録」である通算123安打をマークした。
1985年の日本一メンバーで、遊撃のレギュラーだった平田勝男もその年で32歳。その平田の後釜になり得る有力候補がお膝元にいる。ところが田口は、ドラフト直前「阪神に行きたくない8カ条」を打ち出した。
「何年か前から監督とフロントの間でゴタゴタが多すぎる」
「僕の実力も知らないのに、指名の前からショートのポジションを空けて待っている姿勢自体も問題じゃないですか」
希望が叶わなかった場合には社会人に進む可能性も示唆してまで、阪神への拒否姿勢を明確に打ち出したのだ。
田口が入団を熱望したオリックスの担当スカウトは、1970年の阪神ドラフト1位で、関西学院大出身の元投手・谷村智啓だった。
「あれはな、俺、別に何もしてへんで。ただ、日本ハムが(競合覚悟の指名に)来るっていうてて、たまたまクジが当たっただけのことや。それも、運やん。2枚のうち、1枚とかしか、当たらへんやん。だから、その選手の運命やで」(谷村氏)
最終的に田口での競合を回避した阪神は、萩原を単独指名している。ライバル球団に手を引かせるために、古巣の“内情”を熟知した谷村は、その“裏舞台”で汗を流したのだ。
「阪神ファン」公言で“逆指名表明”
日本一の翌年となる1986年から1991年までの6年間で最下位3度。1987年からは5年連続Bクラス。しかも、直近のチーム打率は2年連続でセ・リーグ最下位、チーム防御率も3年連続でリーグ最下位という、驚愕の数字が並んでいた。
だから、91年のドラフト指名における補強ポイントは、大学・社会人の即戦力だったはずだ。地域性を加味しても、田口は絶対に獲るべき選手でもあった。
ところが、そこに世間の空気を一変させるような“風”が吹く。
石川国体終了後、つまり高校生としての公式戦をすべて終えた萩原が「阪神ファン」であることを、堂々と公言したのだ。
「小さいころから阪神ファンだったので『阪神を希望します』と言おうと思っています」。社会人の大和銀行にも内定していたが「タテジマのユニホームを着るのが夢でした」。
それが、高校生ができる最大限の“逆指名表明”でもあった。
大阪生まれの大阪育ち。1985年の日本一の時には小学6年生で、大阪桐蔭高で甲子園を制覇した4番打者。それこそ、阪神との縁だらけだ。
球団事務所には「萩原を獲れ」というファンからの電話が鳴りやまなかったのだという。当時編成部長の横溝桂が、萩原のもとへ指名前の挨拶に訪れ「球団の内外からも是非、獲得してくださいと要望がきています」。そんなエピソードを披露した上で、萩原に指名を確約したのだ。
「そんな子は、1位でいったれや」
こうなれば、相思相愛の萩原を2位で固め、それ以外ならプロには行かないと表明させればいい。そうすると、競合覚悟で1位に田口を指名できる。
外したら萩原を1位に上げればいいだけで、うまくいけば田口、萩原の地元勢の両獲りすらできる。それこそが、阪神の“最上のドラフト戦略”だろう。
なのに、直前になって阪神は軌道修正。萩原の単独指名という安全策に出たのだ。
ちなみに萩原に次ぐ2位で、阪神は日本石油の遊撃手・久慈照嘉を指名している。1992年の新人王にも輝いた逸材をリストアップできていたのだから、むしろ、外れた時の備えはできていたのだ。
しかし、田口は阪神に対して拒否姿勢、一方で萩原は「行きたい」と熱望している。
「ええやっちゃ、萩原。甲子園でも打ったやん」
「そんな子は、1位でいったれや」
こうした“世間の声”に、阪神は敏感なのだ。
さらに、田口を強行指名して入団を拒否され、萩原を他球団に指名されてしまうという最悪のシナリオに陥った時の、世間からのマイナスの反応を過大に恐れてしまうのだ。
「チームの芯になる高校生を育てないとアカン」
田口は、日米通算1601安打。メジャーで2度の世界一に輝き、オリックスでは外野手としてゴールデングラブ賞5回。中村紀洋も本塁打王1回、打点王2回、ベストナイン5度、三塁手としてゴールデングラブ賞も7度。しかし、萩原誠は8年のプロ生活で通算38安打に終わった。もちろん、後付けとは分かってはいるが、田口、萩原、中村がいた関西で、その3人とも獲れる可能性がありながら、阪神は萩原“だけ”を確実に獲りに行くという、弱気な指名戦略を取ってしまった。
2008年から2018年まで球団オーナーを務めた坂井信也が「チームの芯になる高校生を育てないとアカン」という方針を掲げ、2010年からの4年間、阪神はドラフト2位の枠を「高校生」に絞り込んだ時期がある。
2010年 東海大相模の投手・一二三慎太
2011年 聖光学院の右腕・歳内宏明
2012年 青森・光星学院の内野手・北條史也
2013年 鹿児島実の外野手・横田慎太郎
ただ、4人とも期待通りに育て切れなかった。一二三は2年目から野手に転向したが、プロ6年間で1軍出場なし。歳内も阪神での8年間で通算2勝止まり。独立リーグの四国アイランドリーグプラス・香川でのプレーを経て2020年途中にヤクルトへ移籍も1勝にとどまり、2021年限りで現役を引退している。
北條は、1位指名の大阪桐蔭・藤浪晋太郎と、春夏の甲子園でいずれも決勝で対戦。準優勝に終わったが、その攻守にわたる活躍ぶりは光った。
2023年にプロ11年目を迎えたが、2016年の122試合出場が最多。レギュラーを取り切れず、2022年も32試合出場、打率1割8分6厘に終わっている。横田は2016年に「2番・センター」で開幕スタメンの座をつかんだ。身長1メートル87の大型外野手への期待は高まったが、翌年に脳腫瘍の診断を受け、志半ばで2019年に現役引退を余儀なくされた。
「高校生を2位指名」という命題
この中で、菊地の担当エリアだったのが一二三と北條だが、一二三は大阪・堺市、歳内は兵庫・尼崎市と、いずれも関西出身の選手だった。他県に野球留学した上で、甲子園に出場した経歴を持っている。
「担当としては、一二三も歳内も4位くらいの評価をしているわけですよ。それがパーンと上がって、いきなり『菊地さん、2位で行きましょう』とかね。えっ、とこちらはなるわけですよ。ちょっと違うなと。要するに、関西の人間で甲子園に出て、数字を残した選手がいつの間にか“上”になる。関西の球団だから関西重視でいいし、まして甲子園重視でもある程度はいいところはあると思う。同じ文化、関西っていうところで考えてもね。でも、なんか、それで自動的にひょいっと上がっていくんだよな。それに対して『違う』と突っ込んでも『他にいない』と言われたら、もうこっちは『分かりました』なんですよ」
ただ、高校生2位というのは、育成の重要性を踏まえ、いい素材の選手がいるなら、他球団に先駆けて獲れという、オーナーから与えられた“大局的な指針”のはずだ。
なのに、低めの評価の選手を繰り上げてしまう。忖度が働いてしまうのか、「高校生を2位指名」という命題に捉われるあまり、勝手な縛りを自分たちでかけてしまっているのだ。
もちろん「生え抜きの高卒」が多いから、育成がうまいというイコールの図式では決してない。ただチームの根幹を担う部分に、たたき上げの選手を多く組み込んでいるチームの名前を見ると、結果が伴っているというのも。また浮き彫りになってくる。
なぜ、阪神では“高卒野手”が育たないのか――。その積年の課題を、今連載の「後編」で追ってみたい。
※喜瀬雅則著『阪神タイガースはなんで優勝でけへんのや』(光文社新書)の第3章「戦略」から再構成しました。
[2/2ページ]