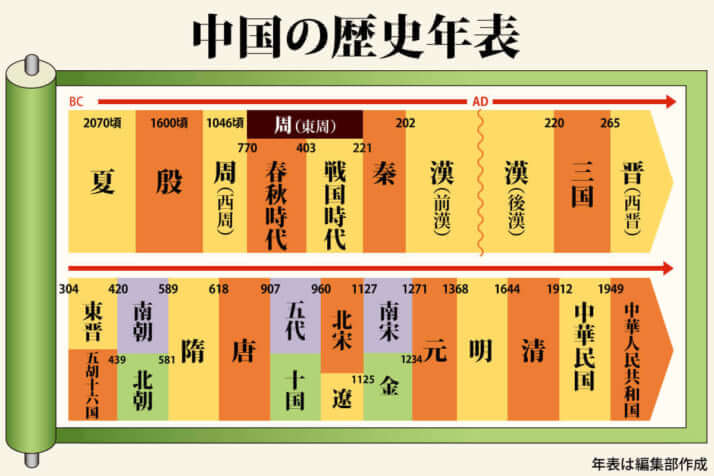日本で熱狂的に歓迎され、朝鮮半島で徹底的に排撃された「異端の学問」とは
多くの共通点を持つ隣国ながら、なかなか分かり合えない日本と韓国・北朝鮮。その原因のひとつとして挙げられるのが、「儒教」に対する姿勢の違いである。
儒教の一派「朱子学」を信奉していた朝鮮半島に対し、その朱子学を批判する「陽明学」が大流行した日本。そこに両国の価値観の違いが如実に表れているというのだ。
では、朱子学・陽明学とは、どのような学問なのか。京都府立大学教授の岡本隆司さんの著書『悪党たちの中華帝国』では、陽明学を創始した王守仁(おうしゅじん)の生涯をたどりながら、朱子学と陽明学の違いを詳しく解説している。同書から一部を再編集して紹介しよう。
***
朝鮮王朝の体制教学は「朱子学」である。この点は同時代の中国とかわらない。というよりも、文明の中心たる「中華」明朝を思慕し、その制度に倣(なら)って自国の体制を作り上げたのが、朝鮮王朝である。しかも単なる模倣にとどまらない。「中華」の精粋をかぎりなくつきつめることで、本物の「中華」にかぎりなく近づこうとした。
その「中華」文明の精粋こそ、朱子学にほかならない。朱子学を純粋醇正(じゅんせい)に受容することが、「小中華」たらんと期す朝鮮にとって、矜持(きょうじ)を賭した営為だったのである。そのため朝鮮国内では、朱子学・朱熹の定論をどう解釈するかが、とりもなおさず「正統」「異端」をめぐる激烈な論争を生み出し、政争にまで発展した。
朱子学の中ですら然(しか)り。ましてや朱子学とは別の旗幟(きし)を立てた王守仁の「陽明学」ともなれば、激烈厳正な排撃の対象とならざるをえない。
朱子学を「正統」としてその遵守を絶対に譲らない「小中華」の自負心は、さらには朱子学を往々にして軽んずる中国に対する優越意識にも転化する。朝鮮史上第一の大儒・李珥(イ・イ)にいわせれば、陽明学を容認した中国は下記のような評価となる。
「朱子の害は洪水猛獣の災禍よりもひどい、と述べているのだから、王守仁の学問も知れたもの、明朝は何とその王守仁を孔子廟に従祀したというのだから、中朝の学術もたかが知れたものである」(『栗谷全書』巻31「語録」)
李珥のように純粋敬虔(けいけん)な朱子学者、標準的典型的な両班(ヤンバン)が、ここまで極言するのは、隣の中国のように陽明学が朝鮮に流布しては困るからであった。
逆にいえば、朱子学を「正統」として尊崇する朝鮮人を恐れさせるほど、16世紀の中国社会は「異端」の陽明学がはびこっていた。
「読書」から「講学」へ
陽明学は当時の中国で、流布という以上に、いわば熱狂的に迎えられ、爆発的な広がりを見せた。そこには教義ばかりにとどまらない要因がある。
先だつ朱子学も、教義そのものにくわえ、「四書」や語録などの経典ガイドを考案工夫して、入りやすく学びやすくした。それでも朱子学は、いわば「書物主義」である。外在的なテキストを読んで、外から知識を取り入れた人が、はじめて自ら「道」「理」を体得できるのであって、これを「読書」といい、士大夫を「読書人」とも言い換えた。現代中国語でも「読書」といえば、学術研究の意味である。
「読書」には、書物を閲覧できる能力・時間が欠かせないし、必然的に経済的な余裕も必要で、貧困の下層階級にはとても望みえない。朱子学はそうした点、やはり一般の庶民に背を向けた学術だった。
ところが陽明学は、心・良知が重要である。知識は内在する心に直結し、ただちに外的な行動に転化せねば意味がない。あくまで「知行合一」である。いくら書物を読み知識を得ても、博覧強記なだけでは「道」「理」の体得体現にはならない。朱子学300年の経験をへて、その「読書人」の実態をみてきたからいえることでもある。
そのためことさら「読書」を尊ばない。反読書・反書物がその一大特徴であり、下層の民衆にも門戸を開いていたという意味でもある。
それなら、本を読まない陽明学は、何をするのか。「講学」であった。口頭の講義・討論で、ゼミナール形式の学習法、あるいは耳学問にもあたる。自分が感得、体得した知識、ひいては「道理」をプレゼンして、他者とぶつけ合うことで自分を高めてゆく、そうした勉強法が陽明学では主流になった。
文章・書き言葉では、著者の本音まではなかなか見えない。そこは古今東西、あまり事情はかわらないだろう。そのため朱子学でも、講義・ゼミナール方式の学問実践が行われていた。そんな講義録・言行録も著名である。朱子の『朱子語類』、あるいは朱子に先だつ宋学の面々なら『近思録』といったたぐいで、「四書」の一つ『論語』も、孔子の語録であった。
陽明学の講学は、それをいっそう実践的なライヴ形式でオープンにしたものである。これなら字の読めない人々でも、聴講できるから参加しやすい。庶民が力をもってきた世相、そしてその庶民に寄り添った紳士・郷紳の出現・増殖という当時の社会情勢にも棹(さお)さしていた。講学のサークルが各地で生まれ、相互にネットワークを形成し、それをくりかえすことで、陽明学は爆発的な拡大をとげてゆく。
拡大の果てに
「聖人学んで至る可し」が宋学・朱子学のテーゼだった。「学」べば聖人になれるとは、「読書」して「学」ばないと聖人にはなれない、との意味でもある。まず「読書人」でなくてはならない。そこに科挙の存在理由もあり、士大夫エリートの支配の正当性も存した。
ところが陽明学は、「満街(まちじゅうの)人、すべて聖人だ」と言い放っている。「読書人」に限らない「満街人」の広がりをもってきたといってよい。そこに明代庶民の力量の一端もうかがえる。
やがて中国大陸の「満街」のみにとどまらなくなった。陽明学は「華夷」の結界を超えても広がってゆき、そこにたとえば、先に引いた朝鮮両班の感慨・発言が位置する。
あくまで朱子学を「正統」とすれば、「読書」しない陽明学が「異端」に映って当然だった。庶民すら「聖人」扱いする「異端」の流布は、朱子学・科挙を通して「正統」な地位をえた自分たちの存在を脅(おびや)かすから、本能的に身構えざるをえない。
では、なぜ「異端」が流布するのか。半島の両班からみれば、かつて朱子学を生み出した中国は、「聖人」を僭称(せんしょう)する「小人」の横行する地と化していたからである。それでは「中朝の学術もたかが知れたもの」、以後の朝鮮半島は「異端」を圧服しつづけた。陽明学が存在しなかったわけではない。しかしその信奉者は、あたかも隠れキリシタンのような世を忍ぶ存在と化している。
それに対し、隠れキリシタンの本場、日本列島では陽明学は大きな歓迎を受けた。17世紀の近世以降、日本の著名な漢学者たちは陽明学に志し、名を残している。
日本列島は朱子学も陽明学も普及した。科挙もなければ「正統」の観念も乏しい。大陸の士大夫・半島の両班のような存在もなかった。それこそ「満街」に「小人」ばかりの国だからであろう。
陽明学の帰趨はこのように大陸・半島・列島、東アジア各地の社会の個性を示すメルクマールだったといってよい。
※岡本隆司『悪党たちの中華帝国』(新潮選書)から一部を再編集。