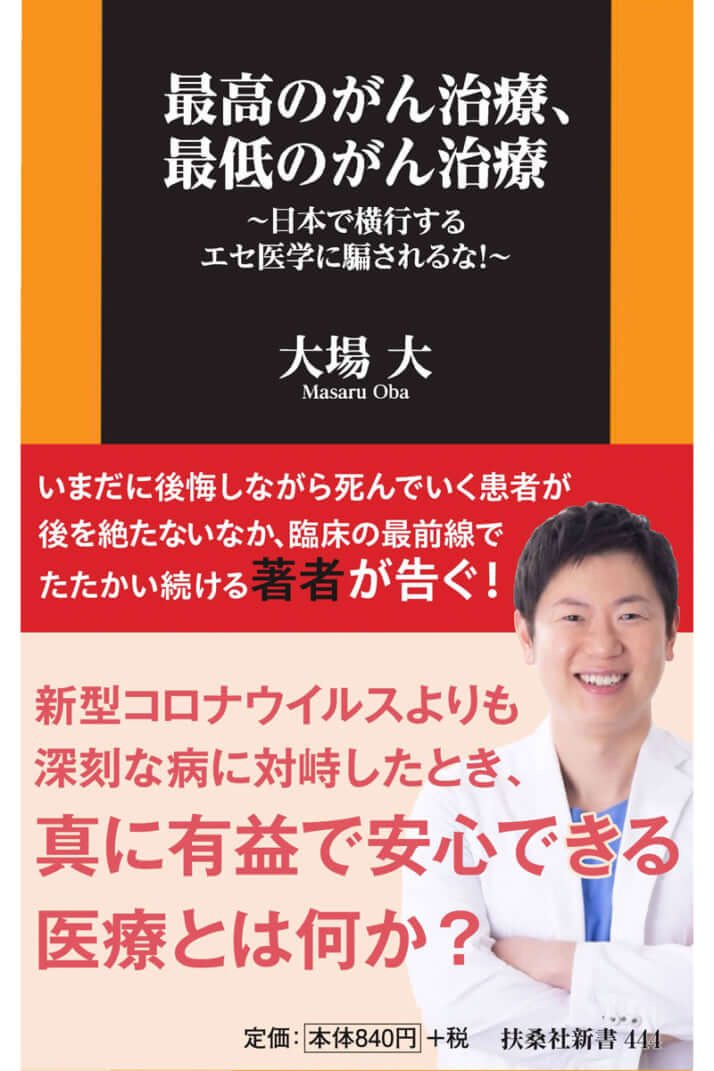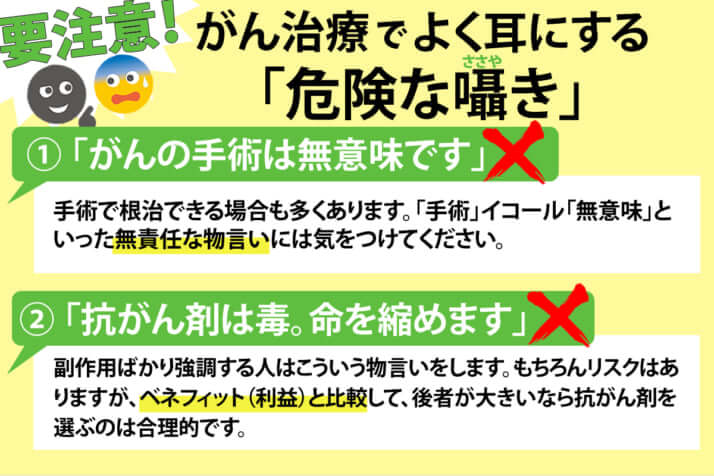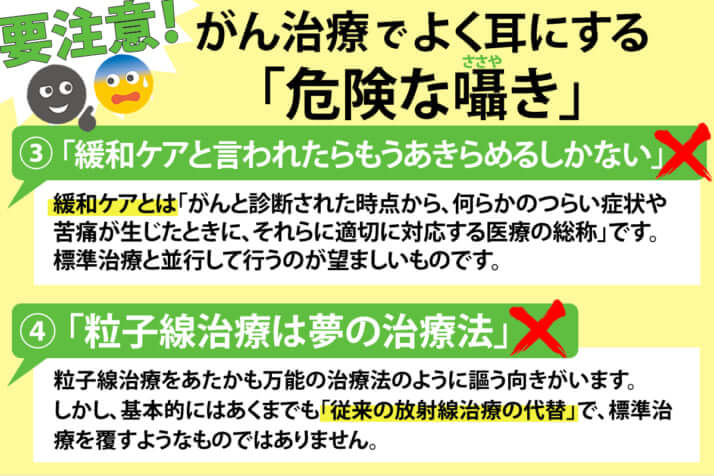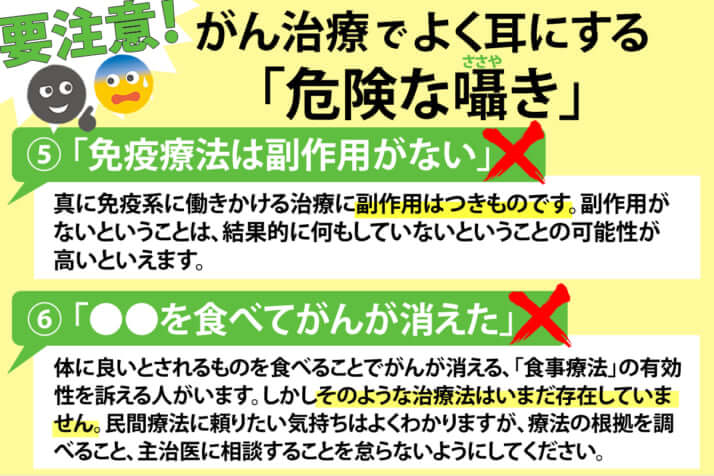がんの「ステージIV」イコール「末期」ではない 専門医が教える「最高の治療」「最低の治療」(1)
この数年、医学や健康に関する報道の多くは、新型コロナ関連のものとなってきた。しかし、日本人の死因のトップは現在でも悪性新生物(腫瘍)、すなわち「がん」であることを忘れてはならない。昨年のデータでは、がんによる死亡が38万人超で、新型コロナは約1万7千人である。
長年がん治療に携わり、またがん関連の情報を積極的に発信し続けている医師の大場大さん(東京目白クリニック院長)は、新著『最高のがん治療、最低のがん治療 ~日本で横行するエセ医学に騙されるな!~』(扶桑社新書)で、患者や家族が知っておくべき知見を紹介している。大場さんは、積極的に他院のがん患者の相談を受けて、セカンドオピニオンを提供することにしているという。
大場さんの言うところの「最高の治療」「最低の治療」とは何か。
3回にわたってご紹介してみよう。
1回目の今回は、「ステージIV」について。
どうしても絶望的になってしまいがちだが、がんの種類によっては治るチャンスもあり、希望が持てるようになっているという。「ステージIV」イコール「末期」と受け止めないでほしい、と大場氏は訴える(以下は、『最高のがん治療、最低のがん治療 ~日本で横行するエセ医学に騙されるな!~』の一部を再構成したものです)。
***
大腸がんについて知っておくべきこと
一般論でいうと、がんの再発とは、治ることから遠ざかる不運な出来事です。そして、最初にいくらベストが尽くされたとしても、どんなに優れた外科医に手術をしてもらっても、再発してしまうことは時折みられます。
再発リスクが高いときには、手術の前もしくは後(周術期)に、全身治療である抗がん剤を使用することが推奨されます。このような抗がん剤治療のことを「補助化学療法」と呼びます。要するに、再発リスクをできるだけ減らすことで、治癒する確度をより高める戦略の一つだといえるでしょう。
ところが、例外的な疾患もあります。とくに大腸がんの場合がそうです。
現在、大腸がんの罹患数は、国内で年間15万2千人以上、男女合わせた全体で1位となっています(国立がん研究センターがん情報サービス)。また、女性の場合、死因の1位のがんであることがあまり認識されていないようです。欧米先進諸国との比較では、75歳未満で年齢調整をした死亡率をみると日本がトップであることもあまり知られていません(第75回がん対策推進協議会「がん対策の年齢調整死亡率・罹患率に及ぼす影響に関する研究」資料より)。
他で日本人に多い肺がんや胃がんとは異なり、実は進行したステージIIIの大腸がんでもしっかり手術を行えば10年生存率が70%を超えている予後が比較的良い疾患だといえます。にもかかわらず、なぜ死亡数が年次推移でみると増え続けているのか。カギは、転移しやすい臓器が肝臓であること、ステージIVでも治るチャンスがあるにもかかわらず、治療戦略が病院や医師によって大きな格差があることが挙げられます。
抗がん剤治療の飛躍的進歩によって転移を抱えていても、2~3年とQOL(生活の質)を維持しながら元気に過ごされている患者さんはたくさんいらっしゃいます。筆者が研修医だったころは、有効性をいまひとつ実感できない抗がん剤がわずか一つ二つしかありませんでしたから、最新の『大腸癌治療ガイドライン 医師用2022年版』(金原出版)の内容をみると隔世の感があります。それでも、進歩した抗がん剤のみでがんを治すことは今でも難しいわけです。ではどうしたら治せるチャンスが生まれるのか。それはエキスパート肝臓外科医がどれほど関われるかによります。
不思議なことに、大腸がんは、なぜか肝臓を好んで転移しやすい特徴があります。次いで肺にもしばしば転移します。しかし、だからといって決してあきらめてはいけません。 再発しても切除が可能であれば、何度も「治癒のチャンス」があるということです。
このような大腸がんのふるまいを知らない医師は意外と多いのです。そのため、手術で治せるかもしれない転移なのに「もう治らない」と漫然と抗がん剤が投与され続け、治せるチャンスが主治医によって奪われている患者さんが世の中にはたくさんいます。この残念な状況には、医師のモチベーション不足が大きく影響していると考えます。
転移したら終わり、ではない
ちなみに、筆者が東京大学医学部附属病院に勤務していたとき、過去17年間に大腸がん肝転移の手術を受けた371人の患者さんのデータを解析したところ、5年生存率は54%、10年生存率は41%でした(Ann Surg Oncol 2014; 21: 1817-24)。
そして、ぜひ知っていただきたいことは、大腸がん肝転移の手術後にも再発してしまうことはしばしばあります。同じ肝臓の場合もありますし、肺やその他の部位に再発することもあるでしょう。それでも、再発したら終わりではありません。繰り返し手術が可能だった患者さんが全体のなかで半数もいらっしゃるという事実です。そのようにがんと前向きに、その都度、繰り返し手術が可能であれば、最終的に4~5割の患者さんは本当に治っていくのです。もし大腸がんが転移してしまったとしても、個別のケースにもよりますが、治るチャンスを絶対にあきらめてはいけないと繰り返し申し上げておきます。
2021年に初めて、がん診療連携拠点病院に認定されている「各施設ごと」の5年生存率が公表され、その格差がメディアで物議を醸しました。もちろん、国立がん研究センターの閲覧サイトには解釈に対する注意書きがされており、施設ごとに治療している患者の背景が異なるため、単純に数字のみを比較して「その施設の治療成績の良し悪しを論ずることはできません」とあるのには一定の理解はできます。実際に、がん専門のセンター病院では、比較的年齢も若くて、心臓病や糖尿病などの基礎疾患リスクの少ない、ある意味エリート患者さんが選り好みされているフシは否めません。すでに患者選択バイアス(偏り)が存在しているのは事実でしょう。新規抗がん剤の治験対象もそうだといえます。少しでもリスクを有する患者さんは治験には入れないわけです。
話を元に戻しますと、転移しても治癒ポテンシャルのある一定の患者集団を包有しているはずの大腸がんステージIVの5年生存率について、このデータの施設ごとの成績をみると、患者背景のバイアスを差し引いてもかなりの格差があることがわかります(2013~14年のケース)。
地域の基幹病院でも5年生存率が10%にも満たないどころか0%の施設も少なくありません。転移した大腸がんはステージIVでも治せるポテンシャルのある特有の疾患であることは先述した通りです。あきらめないで治癒を目指すためには、主に肝臓への転移、肺への転移を切除することが主軸となります。ただし、「切除できる・できない」は医師間、施設間で考え方の差異があり、職種を超えたチーム医療の成熟度が患者さんの予後に直接反映するわけです。もちろん、同じステージIVでもグラデーションがあって、それぞれの転移様式や腫瘍条件によって治癒ポテンシャルの度合いも変わってきます。
大腸がんの転移が肝臓や肺にみられても、主たる病気は大腸がんですから、大腸外科医が主治医であることがほとんどでしょう。その際、肝臓外科医や呼吸器外科医にしっかり相談していないことがほとんどです。あるいは、ステージIVだから抗がん剤でしょ、という理由で、安直に消化器内科医や腫瘍内科医に預けられてしまうケースも少なくありません。患者を紹介された腫瘍内科医は、「手術ができる・できない」を外科医たちと議論するより、自分の業績となりやすい新規抗がん剤の治験にエントリーさせたほうがよほど話が早いわけです。抗がん剤としてはいくら良い治療成績が生み出せたとしても、患者さんにとっては治癒するチャンスが永遠に失われてしまうことになりかねません。
神経内分泌腫瘍治療の進歩
ステージIVでもあきらめてはいけない他の疾患には、神経内分泌腫瘍(neuroendocrineneoplasm; NEN)という特殊な悪性腫瘍があります。肝臓にパラパラと転移してみつかるケースが多いです。原発臓器として消化管が主ですが、最近ではとくに膵臓のNENが増えている実感があります。アップル創業者のスティーブ・ジョブズ氏も肝転移を有するNENが原因で帰らぬ人となってしまったのは有名です。あとは、卵巣がんや腎臓がんの転移、条件が許せば胃がんの肝転移なども可能性はありそうです。乳がんの患者さんで、肝臓や肺に一個だけ転移があって、何年も抗がん剤治療を続けている方をたまに目にしますが、あれも切除してしまってもいいのではと個人的には思います。免疫チェックポイント阻害薬のような薬物治療の進歩によって転移巣を制御できる割合が高まってきたことで、ひょっとしたらというケースは、以前より確実に増えてきています。
ステージIVの患者さんでも手術を含めた集学的治療によって長期生存できる方、場合によっては治癒まで達成できる方が一定数います。「ステージIVのがん」とは「末期がん」とイコールではないこと、条件によっては治癒のチャンスもあることは知っておいてほしいです。
以下は、転移した大腸がんを治すための三つの必須ポイントとなります。
(1)エキスパート肝臓外科医に必ず相談、もしくは紹介してもらうこと(肺転移の場合、肝臓外科医を呼吸器外科医に置き換えてください)。
(2)一度の肝切除で解決しないことがしばしばあるため、再発しても決してあきらめないこと。
(3)専門的な抗がん剤治療(化学療法)を、安全かつ有効に組み合わせること。
昨今の著しい抗がん剤の進歩に併せて、診療ガイドラインの普及や副作用対策(支持療法)の進歩もあり、治療選択レベルの標準化が進んでいることは喜ばしいことです。一方で、抗がん剤治療はがん患者さんをマネジメントする手段のひとつであり、それが目的化されすぎることで、個々の患者さんの治癒ポテンシャルを奪ってしまうケースも少なくありません。その代表的な疾患としてあげられるのが大腸がんです。転移・再発の5割以上のケースで肝臓にみられるのですが、他のがんの転移であれば、治療の目的は緩和的な意味合いとなることが多いかもしれません。しかしながら、大腸がん肝転移の場合、その治療戦略はまったく異なってきます。手術の介入によって、治癒ポテンシャルを有する疾患です。さらには、著者の論文ですが、肝切除後に高い再発リスクはあるものの、それが再度切除することが可能であれば、治癒ポテンシャルは失われないままであることを示したエビデンスがあります(Surgery 2016; 159: 632-40)。
昨今、さまざまなバイオマーカーの登場やゲノム診療などによって、「個別化」と称される医療がもてはやされていますが、一人でも多くの治癒ポテンシャルを有する大腸がん患者さんを見逃さない努力も、重要な個別化医療のひとつであると考えます。それを可能にするのは、決して、一つの診療科、一人の主治医のみで大腸がん患者さんを抱え込むのではなく、肝臓外科医、呼吸器外科医などを交えた多職種連携によるチーム医療(multidisciplinary team; MDT)が必要となってきます。
ある地域がんセンター病院で「もう治せませんよ」という診断のもとで緩和的な抗がん剤治療を受けていた、大腸がん肝転移の患者さんのCT画像を、世界中のエキスパート肝臓外科医に見せたところ、実に6割以上の患者さんが、手術できるポテンシャルがあったという結果も報告されています(Br J Sur 2012; 50: 1590-601)。国内においても、地域や病院が違えば、程度の差はあれ、それに似た状況があるような気がします。本当は治せたのに、身近な主治医の独断で治らない大腸がんになってしまっている可能性があります。
この話は何も大腸がんに限った話ではなく、進歩した有効性の高い抗がん剤の登場によって、他のがんでも同様な場面が増えてきています。