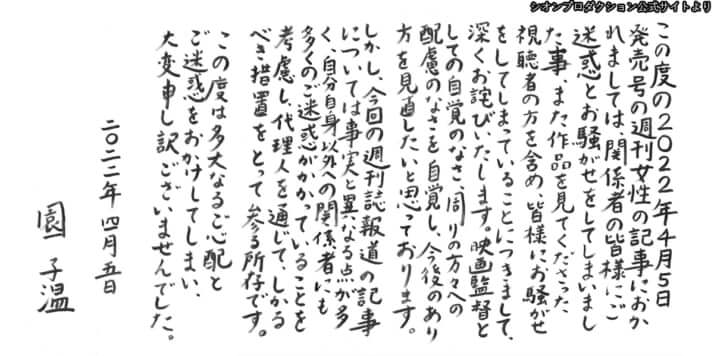園子温、榊英雄監督を勘違いさせた日本映画界の土壌……関係者は「未だにこんな人がいたなんて」
荻野目慶子の悩み
互いに才能を認めた上での関係であったのかもしれない。深作監督がその後の映画で起用したのが荻野目慶子だった。芸能記者は言う。
「荻野目はそれ以前に妻子ある映画監督と不倫していたのですが、彼女から別れ話を切り出すと、その監督は彼女のマンションで自殺してしまった。当時は“魔性の女”などと報じられましたが、業界では彼女に同情する声もあったんです。女優が観客を引きつけるには、ある種の魔性の部分がなければ大成しません。事件から1年後に出会ったのが深作監督でした。萩原健一主演の『いつかギラギラする日』で、彼女は34歳年上の監督に押し倒された」
撮影中、毎日のように深作監督から誘われたことを、荻野目は自著「女優の夜」(幻冬舎)にこう書いている。
《スタッフ、キャストは全員、監督より遥かに若い人達だったが、撮影が進むうちに、目に見えて疲労していった。けれども監督はそんな状況の中でも毎夜、私と一緒にいることを望まれた。このスケジュールの中で皆なと同じ時間を過ごし、自ら駆け回って大声で指示を与え一時(いっとき)も休んでいないことを考えると、それは驚異的なエネルギーだった。/そのエネルギーを拒否すべきだっただろうか。/拒否すれば、不調和を生むだろう》
現場の雰囲気が悪くなることを考えての上だったというのだ。
50年以上を経てから監督との不倫関係を告発した女優もいた。
有馬稲子の悲痛
2010年、日本経済新聞の連載コラム「私の履歴書」で、映画監督との7年にわたるドロドロの不倫関係を語ったのは女優の有馬稲子だ。コラムでは監督の実名は挙げていなかったが、《森本薫の戯曲『華々しき一族』を原作にした映画》の監督とあるから、1953年公開「愛人」の市川崑監督だと関係者にはわかった。
《「妻とうまくいっていなくて別居している。きちんとしたら君と結婚したい、春までには……」、春の約束は、夏になり、秋を迎え、また春になり7年の月日がたつことになってしまった》(日経新聞)
彼女は堕胎までしたと明かすのだ。なぜ、このような文章を綴ったのか、彼女は「週刊新潮」(10年4月29日号)にこう答えている。一部を抜粋しよう。
《私としては、いずれこのことは忘れられるのではと思っておりました。今年は忘れられるか、消えてくれるかと思いましたが、消えてくれません。それは単にひとつの、通り過ぎる“色恋沙汰”だったからではなく、その後の私の人生を支配し続けたということにあるかと思います。例えば、彼は、私が最初の結婚の相談をしたとき、反対しています。たとえ彼の思惑は何であれ、“それはよかった。幸せになってくれ”という男気がなぜ彼にはなかったのでしょう。それは道ならぬ恋をしている大人の、最低限の誠意だと思うのです。又次の回の、実際に結婚が決まった時も、“3月に1度でいいから会ってくれ”と、とんでもないことを言っています。これだけは口にするべきではないでしょう。このひどさは今思い出してもカッとなるほど腹立たしいものです。恋をするなら男には覚悟が必要だと思います。その覚悟もなく結婚するという言葉で私を釣っていた、その勝手さが今もって許せないのです。(中略)確かに若い私が安易に結婚を夢みたことはおろかだったでしょう。しかし恋の成就がなかったとわかった後も、それが情熱を傾けるに足るいい恋のままだったら、芸の肥やしにもなりましょう。しかしあの方はそう思う手がかりも足がかりも壊してしまった。連載の14回目の最後に書いた私がこうむった肉体的な(精神的なことより肉体的なことの方が立ち直れないという意味ではずっと後遺症として大きいのです)痛みは大げさでなく、私のその後の人生のすべてを支配することになりました》
悲痛な叫びである。榊監督と園監督の話に戻ろう。映画関係者は言う。
「榊監督の評判はかなり悪かったそうです。もともと役者でしたが、芝居は荒々しい感じしかできず、繊細な芝居ができないので、よく監督から怒られていました。その反動でしょうか。自分が監督になると、無名の女優には高圧的な態度に出て、手当たり次第に手を付けているという噂はありました。売れている俳優に対してはへぇこらするタイプなのにね。園監督のセクハラもずいぶん前から有名な話でした。彼らは昔の感覚でずっと仕事をしていたんでしょうね。反省してもらわないと困ります」