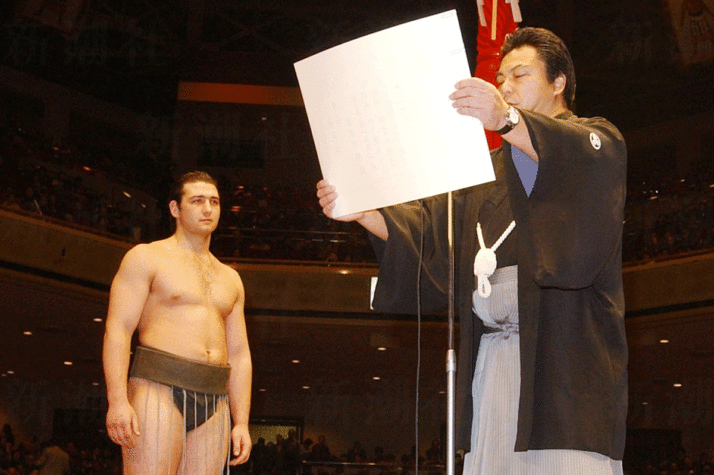「関取になるまでパスポートを取り上げられていた」 琴欧洲が明かす相撲部屋の過酷な慣習(小林信也)
「私は相撲を体験するため日本に来た。親方は入門するため来たと思ってた」
カロヤン・ステファノフ・マハリャノフがブルガリアから来たのは2002年、19歳の夏。少年時代はレスリング選手で欧州ジュニア・チャンピオンにも輝いた。大学の相撲大会で自分より小さな選手に負け、相撲に興味を抱いた。ドイツの相撲選手権で優勝した時、大会会場で日本人に声をかけられ、佐渡ヶ嶽部屋を紹介された。「日本に行って相撲部屋を体験してみないか」、夏休みを利用して日本に行けるならラッキーだと思い、誘いに応じた。まさかそれが生涯の旅になるとは考えもしなかった。
「部屋に着いたらパスポートを没収されて、関取になるまで返さないと言われた」
話が違うと叫んでも通用しない社会だと、カロヤンはすぐに悟った。
「ビックリした。相撲部屋の仕組みが全然わからなかった。ボクシングみたいにひとりの選手にコーチやトレーナーがついて強化するのかと想像していた……」
相撲部屋はスポーツの常識とまるで違った。
「自由がない、食事がない、先輩が言うことは間違っていても逆らえない。新弟子はちゃんこを食べるのも最後だから、汁をすくっても中身が全然ない。冷や飯に水をかけて食べた。味もない、おかずもない。ご飯に牛乳をかけて食べた」
なぜやめて帰ろうと思わなかったのか?
「パスポートがないから、帰るに帰れなかった。だまされたようなものだけど、親方がよかった。当時は先代の佐渡ヶ嶽ですね。元横綱の琴櫻です。先代の目を見て、“オレについてこい”と言われて、信頼できる人だと思った」
19歳の青年はすぐに覚悟を決めたという。
「成功するしかなかった。後がないのは意外と楽。前に進むしかない。割り切った。稽古して番付を上げるしかない。稽古は楽だった。私生活の方が大変。兄弟子から厳しくしつけられた」
相撲人生で最高にうれしかった瞬間はいつ? 聞くとすぐ答えが返ってきた。
「十両に上がって関取になった時。あのうれしさは忘れません。1年半、生きるか死ぬかだった。番付発表の日、大部屋から個室に移って、パスポートを返してもらった。前の日まで琴光喜の付け人だった。その日から付け人がついた……」
[1/3ページ]