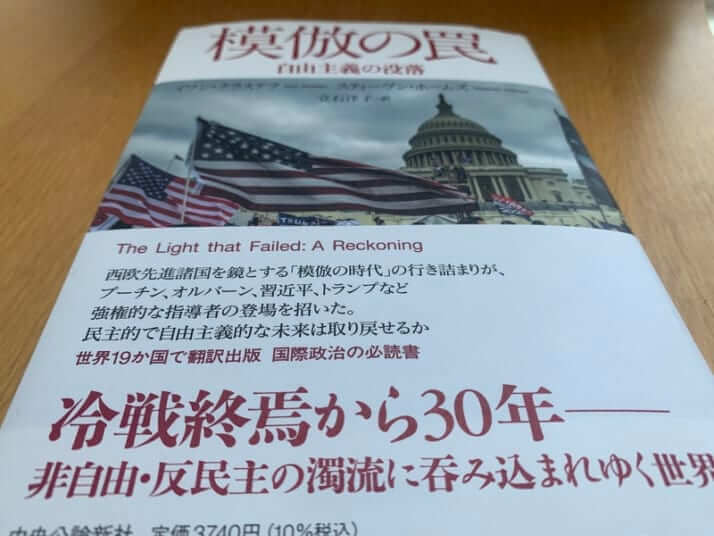【ブックハンティング】「模倣」で読み解くポピュリズムと権威主義
1965年にブルガリアに生まれた政治学者のイワン・クラステフは、首都ソフィアの「リベラル戦略センター」理事長、オーストリア・ウィーン「人間科学研究所」の常任フェローという肩書を持つが、研究者としてよりもむしろ、政治コラムニスト、文明批評家として、欧州で最も注目を集める人物である。
ある政治現象を、一見突飛なものと比較しつつ、特徴を浮き彫りにする。古今東西の文化や芸術になぞらえ、スラブ文学に特徴的なブラックユーモアを交えて描く。
その手法の鮮やかさは以前から欧米の研究者やジャーナリストの間で有名だったが、『アフター・ヨーロッパ』(2018年、庄司克宏監訳、岩波書店)、『コロナ・ショックは世界をどう変えるか』(2020年、山田文訳、中央公論新社)と、邦訳が近年相次ぎ、日本でも広く知られるようになった。
このようにアカデミズムの本流からやや離れて評論活動を展開してきたクラステフが今回、米アカデミズムの中心であるシカゴ、プリンストン、ニューヨーク各大学の教授としてリベラリズムや旧東欧の自由化を研究してきたスティーヴン・ホームズとともに著作を編み、それが早速翻訳された。『模倣の罠 自由主義の没落』(立石洋子訳、中央公論新社)である。
ポピュリズムや権威主義を国家間関係の文脈に位置づける
同書については、邦訳が出る前の昨年4月3日に、『「トランプ」「プーチン」「オルバン」の台頭:世界の潮流を「模倣」で読み解く』(上)(下)で紹介したが、今回邦訳に目を通して、現代世界の一大潮流に発展したポピュリズムと権威主義的政治を理解するうえでやはり不可欠な文献だと、改めて認識した。
ポピュリズムや権威主義は、ナショナリズムと結びつきやすいこと、国内の選挙制度との関連でしばしば論じられることから、一国内の出来事として受け止められ、分析されがちだった。
本書の斬新さは、これを国家間関係の文脈の中に位置づけ、影響し合う存在としてポピュリズムや権威主義の特徴を浮き彫りにしようとしたところにあるだろう。
その作業のキーワードが、邦訳の題名にもうたわれた「模倣」である。
ポピュリズムや権威主義政権が足場を固めていくうえで、他国を「模倣」する姿勢や行為が、いかに作用したか。彼らはいかに互いに模倣し、あるいは模倣を拒んで、自らの立ち位置を定めていったか。
ハンガリーのオルバン・ヴィクトル政権、ロシアのウラジーミル・プーチン政権、米国のドナルド・トランプ政権を例に挙げつつ、その過程が検証される。
「模倣」が「屈辱」を生み出したハンガリー
同書はまず、旧東欧で民主化の牽引役を果たしたハンガリーで、オルバンが築いた権威主義体制を考察する。
1989年の民主化後、旧東欧諸国は懸命に西側諸国の真似をしようとした。しかし、その結果2000年代に起きたのは、若い人材の西側への大量流出と、リーマン・ショックに続く金融危機だった。
「模倣」が生み出したのは「屈辱」だった――。
2010年にオルバンが2度目の政権に復帰した背景にはそうした幻滅があったと、同書は位置づける。
オルバンは以後、西欧の全面的な模倣という卑屈な立場を脱却し、都合のいい部分だけ自ら選択的に模倣する戦略を採った。それが、多様性を否定し、報道の自由や司法の独立を攻撃する非自由主義的な体制に結びついた。
同書はこれを、米社会学者キム・シェッペレ(キム・レーン・シェッペル)の言葉を借りて「フランケン国家」と呼ぶ。フランケンシュタインの怪物のようにつぎはぎであり、「つまり、西洋の自由民主主義の要素を巧妙に縫い合わせて構成された非自由主義的な突然変異体」だというのである。
「模倣の民主主義」を導入したプーチン
西欧型の自由民主主義の模倣を試みて挫折したハンガリーとは異なり、ロシアは最初から、これを模倣する気などなかった。ソ連崩壊を陰謀の結果だと受け止めた人々は、「自由主義の偽善」からの解放者として振る舞うプーチンを喝采で迎えたのだった。
同書によると、プーチンの狙いは民主主義を模倣することでなく、「模倣の民主主義」を導入することにあった。選挙を管理、操作、設計することによって、権力を維持し、政治的権威への信頼を保とうとしたのである。
今懸念されるのは、「西欧がプーチンのロシアに似始めていること」だと、同書は指摘する。西欧がロシアのモデルとなるのでなく、ロシアの権威主義政権を西欧側が模倣する。「それはクレムリンに一瞬の微笑みをもたらすかもしれないが、世界の安定と平和を支えるとは考えられない」と、同書は警告している。
模倣される立場を拒否したトランプ
旧東欧やロシアとは逆に、米国は一貫して「模倣される」立場にあった。
にもかかわらずトランプが権力を掌握したのもまた、「『模倣の時代』に生じた幻滅と憤り」が背景にあったと、同書は指摘する。米産業界には「模倣されることへの恐怖」が強いが、それは模倣が「取って代わられることへの恐怖」につながるからであり、このように模倣される立場を拒否したのがトランプだったという。
トランプや産業界は、かつて戦争で打ち負かしたはずの日本やドイツが、模倣を通じて米国の経済的地位を脅かすまでに成長したことを、問題視している。しかも、今度は中国もやはり米国に挑戦するに至った、と考えているという。
皮肉なのは、そうした「模倣を拒否する態度」を模倣するケースが出てきていることである。一例は、トランプをモデルとして権力を握ったブラジル大統領ジャイール・ボルソナーロだという。
同書は「『自由主義の模倣の時代』は終わった。しかし、『非自由主義の模倣の時代』は始まったばかりなのかもしれない」と綴る。
なお、同書は最後に、中国の習近平体制にも触れている。中国は自由主義や民主主義を学ぶことなく、技術を身につけた。模倣することを拒むとともに、模倣されることも望まない。「模倣者」ではなく、巧妙な「盗用者」となることによって、中国はアイデンティティーの崩壊を免れた、と評価している。
問題解決型ではなく問題提起型
同書は、ポピュリズムや権威主義を巡る模倣の様々な形態を紹介しつつ、模倣される対象だった自由民主主義が輝きを失っていく過程も描写している。日本を含む民主国家が依拠してきた理念の脆弱さを突きつけられ、考えさせられるところが多い。
ただ、同書で用いられている手法は、先行研究から出発して着実な一歩を積み重ねる実証的な研究でもなければ、現代世界を包括的に記述するものでもない。著者ら自身も序章で「私たちの目的は、現代の反自由主義の原因と結果を包括的かつ決定的に説明することではなく、その物語のある特定の側面を強調し、説明することにある」と説明する。
また、論理構成がやや拙速で、分析での実証不足や単純化された説明がうかがえるのは、訳者の立石洋子が解説で指摘している通りである。
立石はまた、ポピュリストや権威主義者ら「非自由主義者」の側にばかり問題があるのか、と問いかけている。「トランプの支持者だけでなく、トランプを批判する人々のなかにもそのような(筆者補足:対話を拒否する)態度が見られたことが両者の対話を困難にした」との指摘であり、忘れてはならない視点だろう。
同書はすなわち、クラステフのこれまでの著作に似て、自由な発想と多少皮肉を込めた分析を元に、現実政治への新たな見方を提示しようと狙っている。問題解決型ではなく、問題提起型なのである。
それが一定の理論に発展するきっかけとなるか、単に刺激やヒントを与えるにとどまるか。判断は読者に任せたい。