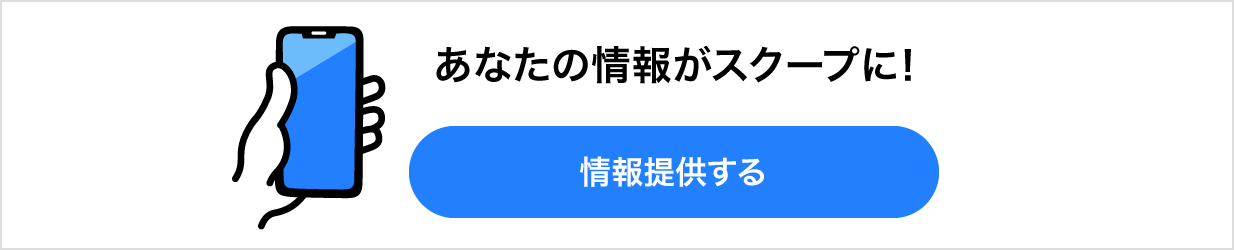「葬式や偲ぶ会はしないで」 橋田壽賀子さんが生前語った死との向き合い方
「安楽死という道があってもいい」
「おしん」や「渡る世間は鬼ばかり」など数々の名作ドラマを世に送り出した脚本家の橋田寿賀子さんが4日、亡くなった。95歳。橋田さんは昨年、「週刊新潮」に対して、終活を始めた理由や、安楽死制度について語っていた。
(週刊新潮 2020年1月2・9日号より)
***
速報「俳優を辞めて自分の中に穴ができて、それを埋める作業を…」 成宮寛貴が明かす“空白期間” 水谷豊に送った手紙の内容とは【インタビュー】
日本では認められない安楽死を求めてスイスに渡った女性。19年6月、NHKスペシャルが取り上げて大きな反響を呼んだが、実際、安楽死を希(こいねが)う人は増えている。脚本家の橋田壽賀子さん(94)もその一人である。
その女性、小島ミナさんは、徐々に全身の機能が失われる多系統萎縮症を患い、理想の死を求めてスイスに渡った。Nスペでは、本人も家族もテレビカメラの前に素顔をさらし、そのうえ、死の直前から直後までもカメラでとらえていたのが衝撃的だった。享年51。
これに橋田さんは、
「小島さんは生きるのが辛いと感じつつ、家族の愛情も感じていたはず。それでも、大変な負担を背負ってスイスに行くほど彼女の意思は固く、ご家族もその意思を尊重されたのでしょうね。私は小島さんほど切実ではないし、安楽死の具体的な準備をしているわけでもありません」
こう言いながらも、
「選択肢として安楽死という道があってもいい、とは常々考えています」
と思いを語る。2019年2月には、「あのとき死ねていればよかった、という思いもある」というほどの経験をしたそうだ。
「ベトナムでクルーズ中に下血して、4日間、輸血を受けました。その後、日本からお医者さまに来ていただき、山王病院に入院しました。搬送費用は保険で賄えましたが、なんと2千万円。船上で食べすぎて、指を突っ込んで吐いたとき食道と胃を傷つけてしまったんですね。下血が止まらず身動きもとれず、“もうやめてください”と何度も頼みましたが、全然通じないし、通訳さんも訳してくれません。ジェット機で搬送中のことはなにも覚えていませんが、麻酔で意識がないまま死ねれば満足だったと思いますね。意識があるなかで苦しい思いをして死ぬのは嫌なんです」
加えて、「人に迷惑をかけてまで生きたくない」と強く訴える。
「私はもう作家として役立たずだし、80歳で南極に行って以来、たった一つの楽しみだったクルーズも面倒に感じるようになりました。家族もいませんから、私に生きていてほしいと思う人も、私がこの人のために生きたいという人もいません。仕事がなく、楽しみもなく、会いたい人もいないのなら、多額の医療費を無駄にしてまで生きるよりは、安楽死したいのです」
終活をスタート
そう思うようになったのは、80歳手前で狭窄症を患ってからだという。
「2度の手術をして動けるようになりましたが、また悪くなったとき、人に迷惑をかけてまで生きたくないと思いました。それを機に本を寄付したり、遺言を書いたりと、終活を始めたんです。“延命治療はしないでほしい”“葬式や偲ぶ会はせず、死んだことを誰にも知らせないでほしい”などと書いています。やっぱり遺言は元気なうちに、自分の手で書いてないとダメ。たとえボケても、遺言があれば当人の意思を大事にしてもらえますからね」
批判も受けるという。
「“役に立たない人間はみな死ねということ?”というご意見をいただくこともありますが、そういうことではないんです。大事なのは本人の意思で、治る見込みがなく、本人も精神的に辛いのであれば安楽死が認められる、というシステムが日本にもできたらいいな、と思うのです」
「死ぬ瞬間までは元気でいたい」
その希望は、生きることの価値がわかっているからこそ、なのだろう。
「生きているうちは、生きるための努力が大切。私は毎年人間ドックを受け、お医者さまに通い、筋肉を作るために毎日お肉を200グラム食べ、月水金には1時間程度、トレーナーさんのもとで運動をしています」
そうする理由は、
「死ぬ瞬間までは元気でいたいし、自分の体は自分で動かしたいから」