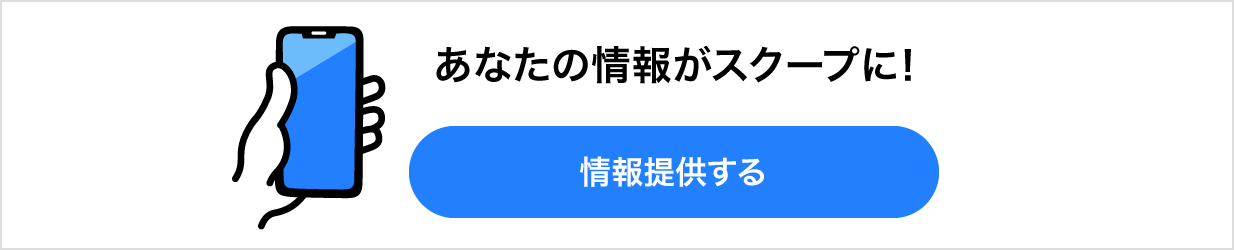舘ひろしが振り返る石原プロ“豪快”伝説 渡哲也に傾倒した理由、裕次郎との間の“微妙な距離感”
「俺は武田信玄になった」
裕次郎さんは文字通り“太陽”みたいな人で、まず怒ることがないし、他人の悪口は絶対に言わない。誰かが陰口を叩くと、「おい、その話やめようや」と言う。豪快な面ばかりがクローズアップされますが、社員はもちろん、誰のことも思いやる繊細な心を持ち合わせていた。そうしたスターの風格は、石原プロという会社にも投影されていました。
たとえば、石原軍団名物の炊き出し。あれは「西部警察」のロケから始まったんです。撮影現場で出されるのが冷めた弁当だけじゃ士気が下がるので、最初は豚汁を作った。そのうちに、ぜんざいはどうか、カレーもいけそうだ、とレシピが増えていってね。その後、阪神・淡路大震災が起きた時に、そして、東日本大震災の時にも、炊き出しは得意だから被災地に向かおう、と。“売名行為”と言われるかもしれないとの心配もありました。でも、それよりも被災地の人たちに元気になってもらいたい、その一念で行くことにしたのです。
その代わり、被災地の負担になってはならない。宿泊先は空いている公民館を借り上げて、水は宝酒造さんのご厚意で提供してもらい、火はガスボンベを持ち込む。トイレも一回ごとにビニール袋に包んで捨てられるキットを2台用意して、1週間は風呂ナシです。
映画製作会社がなぜ本気でボランティア活動をするのかと思いますけど、そこが石原プロなんですね。渡さんは焼きそば係で、僕はぜんざい係。誰が作る料理が一番うまいか競ったり、とにかく真剣なんですよ。炊き出しを仕切っていた小林専務は、撮影用のカメラを買う資金で餅つき機を買いましたからね。映画作りとは無関係かもしれないけれど、人を喜ばせる姿勢は同じなんじゃないかな。
そういった“非日常”をたくさん味わった経験は、間違いなく俳優としての糧になっていると思います。「西部警察」といえば圧巻の爆破シーンですが、どの俳優と比べても、爆破に立ち会った回数では僕が一番でしょう。そんな非日常体験を自分のなかに蓄え、取り入れていく。それは俳優にとって最大の財産かもしれないですね。
ただ、「西部警察」の爆破は本当に凄かったですよ。地方ロケで民家を爆破するときに、小林専務から「ひろし、もっと下がってろ」と指示されて、「はいはい、大丈夫ですよー」と生返事をしながら、一応、パトカーのドアの陰に隠れたんです。その時の爆破が半端じゃなくて、ドカーン!という轟音と同時に空が炎に包まれた。つまり、自分の視界が全て火の海に覆われまして……。小林専務に「いや、いまのは激しかったですね」と声をかけたら、「うーん、サービスじゃ!」って。その後に気づいたんですが、僕が身を潜めていたパトカーのドアに直径5センチくらいの穴がぽっかり空いていた。
結局、石原プロは何事も真剣に突き詰めるんです。先に石原プロでは芝居のレッスンなど一切なかったと言いましたが、爆破にしても、専務が求めたのは“人間が必死になった時の表情”でした。本当の大爆破だからこそ、演技だけでは出せない表現に辿り着けたのだと思います。
あの頃は、裕次郎さんや渡さんのように、豪快に遊び、型破りで、粋な生き様を教えてくれる俳優が石原プロ以外でもいました。その代表格が勝新太郎さんです。
勝さんは裕次郎さんと親交が深く、お互いを“兄弟”と呼び合っていました。勝さんとは、裕次郎さんの晩年にハワイで運転手を務めた際に、別荘でご一緒させてもらいましたが、
「裕次郎、俺はうれしい。俺は何もかも無くしたけど、兄弟がハワイに別荘を構えて、スターとして頑張っているのがうれしいんだ」
としみじみ語っていたことを思い出します。
勝さんといえば、黒澤明監督の「影武者」での降板劇も印象深いですね。僕が小林専務と京都に陣中見舞いに行くと、勝さんはホテルの自室に通してくれた。居間の壁には武田信玄の絵が所狭しと貼られていて、全身全霊をかけて戦国武将になり切ろうとしていました。
後に、勝さんは当時のことをこう語っていました。
「俺はな、武田信玄になったんだ。それなのにだよ、甲冑を身につけて撮影現場で集中していたら、監督が“勝さん、ちょっといいか”と手招きする。武田信玄になっていた俺が、監督に手招きされて“ヘイ、ヘイ”と馳せ参じたら、俺の武田信玄が壊れちゃうんだ。だから降りたんだ」
これが、僕が勝さんから直接聞いた降板の理由です。
俳優の真価は生き様
やはり、スターとしての輝きや魅力は、非日常的な体験の積み重ねから生まれてくるのだと思います。
正直なところ、裕次郎さんにしても、渡さんにしても芝居が上手いわけじゃない。まぁ、ふたりよりは僕の方が少し上手いかなって……(笑)。それでも、子役から始めたり、劇団員見習いを振り出しにこの世界に入った俳優にはとても敵いません。だからこそ、石原プロでは「芝居をするな」と言われました。俳優の真価は芝居の良し悪しではなく、生き様なんだ、と。渡さんからも「おい、ひろし。小芝居はするなよ」とよく言われたな。
いまは演技が達者な俳優が重宝されて、能動的な芝居が求められます。でも、僕にはそれができない。むしろ大事にしているのは先輩方と同じく、“受け”の芝居。共演者の芝居を受け止めて、画面を支えるということです。
「西部警察」を見ていると、ラストシーンで裕次郎さんと渡さんがトレンチコートをなびかせながら夕暮れの波止場を歩くでしょう。ストーリーがどれほどくだらなくても、最後にあのふたりの姿を見ただけで視聴者は納得してくれる。なんだか「いいものを見たなぁ」と思わせる説得力がある。さらにテレビの画面とは違い、映画館のシネスコサイズのスクリーンでは、中央にいる俳優の左右に空間ができます。それを埋めるのが映画スター。裕次郎さんや渡さんはスクリーンに登場しただけで観客の目を釘付けにする存在感がある。ヤクザ映画で、ある俳優さんが見得を切る芝居を見たことがありますが、後ろに控えた下っ端のチンピラ役に目が行ってしまう。セリフがなくても、表情や立ち姿、タバコの吸い方だけで、ひとりの俳優が銀幕を背負う。昔のスターにはそれだけの迫力がありました。
いま公開中の「ヤクザと家族」という映画で、僕は初めてヤクザの親分役を演じています。親分役でイメージしたのは、やはり渡さんですね。俳優にとって重要なのはファーストカット。最初に登場する場面で観客を圧倒することができればいいと思ってます。とりわけ僕は、薄っぺらな格好良さが好きで、芝居をしなくても存在感だけで銀幕を背負いたいと思う。
自分で事務所を立ち上げて、俳優としても新たな船出になりますが、石原プロが大切にしていた伝統は受け継いでいきたい。石原プロで学んだことを糧に映画作りにこだわり、携わっていくつもりです。それこそが、裕次郎さんや渡さんへのレクイエム(鎮魂歌)になると信じています。石原プロの伝統という意味でも、コロナが収束して改めて事務所開きをする際には餅つきをしたいし、撮影現場への差し入れは、石原プロ定番の“おはぎ”と決めています(笑)。
[2/2ページ]