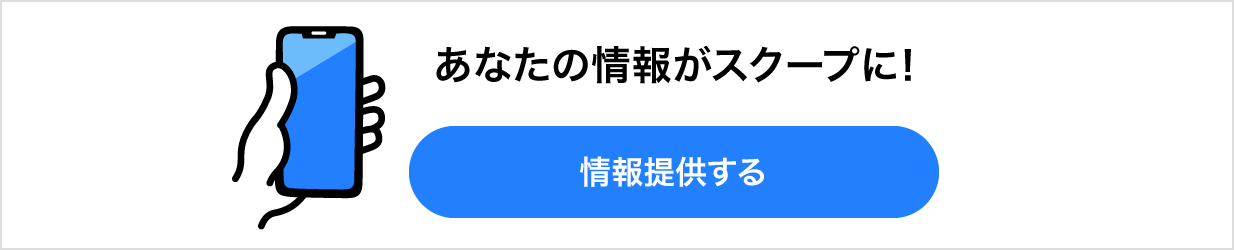「板東英二」の副業への執念と破天荒さ、背景には凄絶な生い立ちが(小林信也)
握りしめた母のもんぺ
板東に会いたいと願い、何度かコンタクトをしたがなかなかご縁がなかった。その後、どうやら体調が芳しくなく、外部との接触を断っていると知った。
私は、資料を頼りに板東の行動の原点を追いかけることにした。手がかりはすぐに見つかった。板東には、『赤い手』(青山出版刊)という、1998年10月に出版された自伝的小説がある。
読み始めてすぐ、それが板東英二の筆舌に尽くしがたい少年時代の体験を綴った物語だとわかった。すべてを笑いに換えて生きているのは、それしか前を向く手がなかったからだろう。振り返って心の傷に目を向けたら、救いのない思いに体が支配される。前を向くには、今日の食い扶持を案じる必要のない、確かな収入が不可欠だった。
〈「英坊、立ち上がるのよ!」
母の声に慌てて起き上がり、再び汽車を追う。……、どうか、どうかあともう少し、速度を上げないで……。心の中で祈りながら、英二は右手を差し出して必死に追いすがった。〉
表紙を開いた片袖にそんな文章が記されている。動き出した列車に乗りそびれ、追いかけた時の記憶だ。
板東は戦争中の40年、満州国に生まれた。終戦後、母と3人の兄姉と命からがら引き揚げてきた。満州から博多へ、8カ月に及ぶ帰還の旅は、常に死と背中合わせだった。道中、一番幼い子をやむなく置き去りにする親の姿も何度か見た。いつ自分もそのように捨て置かれるかわからない。恐怖に怯えながら、6歳の英二は片時も〈握りしめた母のもんぺを離さなかった〉と綴っている。
引き揚げ船内でコレラが流行り、死んだ大人や子どもが海に捨てられる。
〈「もしかしたら自分だったかもしれないなあ……」
海上に漂う毛布にくるまれた遺体を見ながら、英二はぼんやりと感じていた。〉
日本に戻ってからも、赤貧の少年時代が続いた。
粘り強い投球と、破天荒な笑いの彼方には、そのような痛切な歴史が隠されていた。
[2/2ページ]