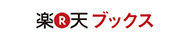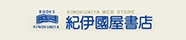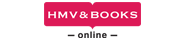読書家・柳亭小痴楽が語る「時代小説」の魅力 「高校中退の私でも楽しめる柔らかさ」
初めて読んだ時代小説は
2019年に真打に昇進し、落語界の次代の担い手として期待されつつ、大の読書家としても知られる柳亭小痴楽氏。自身の本棚をさまよいながら、愛してやまない時代小説との出会いを思い返します。
***
速報「俳優を辞めて自分の中に穴ができて、それを埋める作業を…」 成宮寛貴が明かす“空白期間” 水谷豊に送った手紙の内容とは【インタビュー】
私が時代小説を手に取るようになって、どれくらい経つだろう。小さい頃から小説自体は大好きだったが、時代小説の読み始め……。
改めて考えてみると、すんなりと思い出せない。なんだか無性に気になり本棚と睨めっこをしてみた。いい加減で神経質な私の本棚は、ジャンル別に分けられ、ジャンル毎に作者名のあいうえお順に並べられていて、未読の本はその上に積まれているという具合で、神経質の中にいい加減が仲良く同居している。
本棚と向き合ってみると面白いもので、時代小説を初めて読んだ日は覚えてないが、初めて読んだ本はちゃんと覚えている。和田竜さんの『のぼうの城』だ。友達に薦められて、文庫の初版で買ったのでちょうど10年前ということになる。それと同時に『のぼうの城』の物語まで段々と思い出してきて「あぁ、主人公の成田長親、愛らしかったなぁ。その家老の丹波守、カッコ良かったなぁ」と、ついついエッセイを書く手が止まり『のぼうの城』を読み返してしまう。
今でこそいろいろな時代のフィクションや史実を元にした作品を読むようになり、作家さんの書き方や描写の癖、漢字のこだわりや使い方を楽しめるようになってきたが、一番最初がストレス無くサラッと読ませてくれる和田竜さんで、本当に良かった。
“まともに学校に行かなかった”私でも…
何を隠そう私は高校中退の中卒で、ドロップアウトまでの小中学生時代もまともに学校へ行ってなかった。お昼頃に起き、手ぶらで本を一冊ポッケに入れて、授業もろくに受けず、学校の傍(そば)の喫茶店で本を読んで、放課後から登校して友達と遊ぶ毎日だった。そんなどうしようもない人間にもちゃんと楽しめるような柔らかさがあったから、時代ものにもハマれたんだろう。そうでなければ、子供の頃に歴史の授業で初めに「昔の人、皆おんなじ名前に見える!」と感じて、社会の授業に参加するのが億劫になり、「豊臣秀吉」「坂本龍馬」「織田信長」誰が先輩? というレベルの歴史の知識しかない20歳の私のままだった。
そんな私が今では時代小説の書評までやらせて頂いている。世の中本当に分からない。
私が時代小説を好きになれたのは六代目古今亭今輔師匠のおかげでもある。楽屋で私が貴志祐介さんの本を読んでいたら「僕もその作家さん好きだよ」と話しかけてくれて、他にお薦めを聞いた時にいっぱい出てきたのが司馬遼太郎さんの作品だった。言われるがままに読んでみたのが『国盗り物語』。それはどっぷりハマってしまった。
何事もハマる時というのは何がきっかけか分からない。音楽だとザ・ブルーハーツは、甲本ヒロトさんの声がきっかけで大好きになった。落語で一番最初に聴いたのは八代目春風亭柳枝師匠。こちらも声と軽さだった。
何かがピタッとハマった瞬間を感じられた、そんな時こそが生きていて楽しいと思える時なんだと思う。