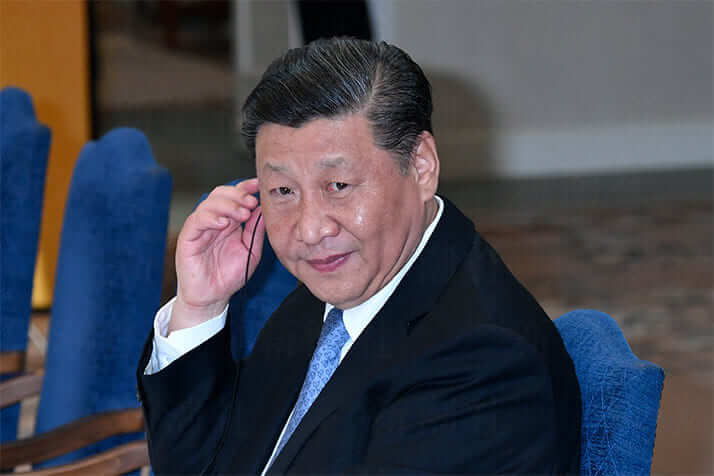中国はコロナで5年早く「最強国」になる?ますます「不寛容さ」が際立つ奇妙な現象
英国シンクタンク「経済ビジネス・リサーチ・センター(CEBR)」は昨年12月下旬、「中国は当初の予想よりも5年早い2028年までに米国を追い抜いて世界最大の経済大国になる」との予測を示した。CEBRが予測を変更したのは、中国が世界各国と比べて新型コロナウイルスのパンデミックに巧みに対処したからである。
速報韓国の「王宮」「世界遺産」で中国人が「排便テロ」行為 観光ビザ免除に「60%以上の韓国国民が反対」
中国は世界で最初に新型コロナの打撃を受けたものの、極めて厳格な措置を講じることで感染拡大を抑制し、経済活動の停止につながるロックダウンを繰り返すことはなかった。その結果、昨年の経済成長率は主要国の中で唯一プラス成長となる見通しである。
これに対して米国は、感染者数や死者数の多さから見て世界最悪の打撃を被っており、いまだに「出口」が見えない状態が続いている。
CEBRは「ここ数年、米中が経済力とソフトパワーの面で争いを繰り広げてきたが、パンデミックの発生は、明らかに中国に有利に働いた」と指摘する。
世界経済に占める中国のシェアは、2000年時点はわずか3.6%だったが、最近では17.8%に拡大しており、2023年までには「高所得国」になる見込みである。
2021年は中国にとって共産党結成100周年という極めて重要な年である。中国が「独り勝ち」の状況はリーマンショック直後の2009年頃に似ているが、今回も同様の展開になり、中国は10年以内に「最強国」になるのだろうか。
『最強国の条件』(講談社)という興味深い書籍が2011年に出版されている。著者はエール大学教授のエイミー・チュア(中国系女性)である。「寛容」が大国の盛衰を決めるという歴史観に基づいており、過去の世界史においては、優れた多様な人材を引き寄せ、活用した国が台頭し、そのような寛容さを失ったときに没落するというものである。本書はアケメネス朝ペルシャから米国に至るまでの歴史を論じているが、出版当時は日本でも賛否両論が巻き起こったことを覚えている。
「寛容」と聞くとリベラルな印象を思い浮かべるが、本書で言う「寛容」とはそんなに品の良いものではない。人権や多文化主義といった概念とは無縁で、平たく言えば、外国人だろうが何であろうが、使える人材は使った方が勝ちだということである。文化的に同化させることができなくても、最低限、何らかの絆をつくって文句を言わせないようにする。それが「最強国」への最低限の条件だというわけである。
なんとも「身も蓋もない」話だが、2011年当時の著者の認識は、「曲がり角に来ている米国」と「非寛容に見えて、実は多様な人材を使いこなす文化を持つ中国」というものだった。その時から10年を経た現在はどうなっているのだろうか。
「太平天国」から未解決の問題点
一般的に言えば、個人や社会が不寛容になるのは、自分の存在が不安定で危ういと感じられる時である。不安定の要因は、外部から攻撃を受けていたり、内部で大きな変動があったりなどさまざまだが、自己のアイデンティティを守り、凝集力を高めるために不寛容になる。新型コロナウイルスのパンデミックが世界の人々の不寛容さを助長していることは間違いないだろう。2020年の暴力による死亡者数が過去最高となったように、現在の米国の「分断」は目を覆うばかりである。一方、「最強国」の道を順調に進むかに見える中国だが、豊かになればなるほど「不寛容さ」が目立つという奇妙な現象が起きている。
マイク・ポンペイオ米国務長官は昨年12月31日、台湾へ渡航を試み当局に拘束された香港の民主活動家に対し、中国の判所が実刑判決を言い渡したことを非難し、「自国民の脱出を妨げるような政権は、偉大さや世界の指導的立場を主張することはできない。ただの自国民を恐れる不安定な独裁政権に過ぎない」と主張したように、中国政府の「不寛容さ」は、国内だけでなく、台湾や香港、さらには周辺地域にまで深刻な影響を与え始めている。
「急速に大国化へ向かう現在の中国を見るとき、太平天国に現れた中国社会の問題点がなお未解決のまま残っていることがわかる」
このように指摘するのは『太平天国 皇帝なき中国の挫折』(岩波新書)の著者、菊池秀明氏である。太平天国の乱は1850年から14年間続いた内戦であり、戦場となった江南三省(江蘇、安徽、浙江)の被害は大きく、江蘇省だけで死者は2000万人を超えたと言われている。ユダヤ・キリスト教思想の影響を受けた抑圧された民の異議申し立ての結果誕生した太平天国の「不寛容さ」は、その後毛沢東によって階級闘争の理論に結びつけられ、中華人民共和国の建国後も、反右派闘争や文化大革命などで「革命の敵」とみなされた人々に対する迫害を生み出した。西洋社会にとっての普遍的な価値は、中国にとっては近代における「屈辱」の歴史を想起させるものであり、今なお中国が引きずる被害者としてのトラウマから解き放ってくれるものではない。
鄧小平が掲げた「改革開放」以降、しばらくの間「金持ち喧嘩せず」とばかりに寛容さを装ってきた中国だったが、大国になっても傍若無人の振る舞いを変えないことから国際社会の目が厳しくなると、自分と異なる他者を排斥するという不寛容さが再び頭をもたげ始めているのである。自らの不寛容さを克服できなければ中国は「最強国」にはなれないが、非民主的な軍事大国のまま対外的な悪影響を及ぼし続けるという「不都合な真実」となる可能性が高い。
『不寛容論 アメリカが生んだ「共存」の哲学』(新潮選書)の著者である森本あんり氏は、「自分の信念は信念として堅持したまま、自分とは根本的に違う価値観を持つ他者と何とかして平和裡に共存する道を模索する」ことが現実的な寛容のあり方だと結論づけているが、隣国としての日本は、このような「寛容」な態度を他者である中国に対して保ち続けることが唯一可能な選択肢ではないだろうか。