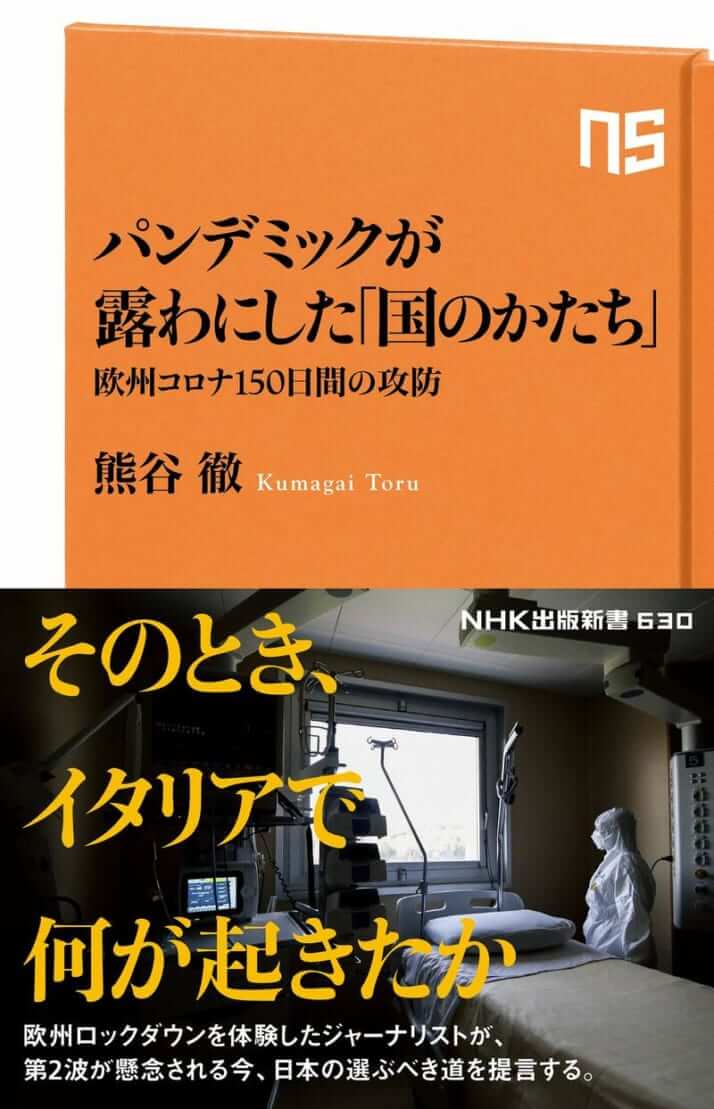【ブックハンティング】「コロナ危機」欧州の敗因ドイツの勝因
新型コロナウイルスの世界的流行は私たちの日常生活を変え、在宅勤務やオンライン授業・会議が当たり前の日常となって久しい。
世界の総感染者数は約3400万人、死者数は100万人を超え、日本の累計感染者数も約8万人、死者数1500人超(世界保健機関=WHO=による)に達した。2002~03年に流行した重症急性呼吸器症候群(SARS)、1918~19年に世界で少なくとも死者5000万人(米国疾病予防管理センター=CDC=による)を出したとされるスペイン・インフルエンザなどとしばしば比較されるが、既に相当のインパクトを与えている。
本書『パンデミックが露わにした「国のかたち」 欧州コロナ150日間の攻防』(NHK出版新書)は、この未曽有の危機において、欧州で初めて集団感染がドイツで確認された本年1月以降の半年余について、感染拡大を阻止するために奔走する欧州各国政府や市民の姿を、ドイツ在住の日本人ジャーナリスト熊谷徹氏が、自身の経験や新聞・テレビなどのメディア報道などを基に描き出したものである。
一時は感染爆発や医療崩壊の最も深刻な事態に陥ったイタリアやスペイン、早期に検査体制の充実を図り、余力のある医療施設を背景に感染拡大の抑え込みに成功したドイツなど、各国が未知のウイルスとどのように闘ってきたのか、現地ならではのエピソードを交えて、最新情勢がまとめられている。
欧州の多くが過小評価
著者は、1月時点で、欧州のほとんどすべての国が新型コロナの危険性を過小評価し、そのことが欧州で約20万人の犠牲者を出し、中国に続く「第2の震源地」となるほどの深刻な事態を招いたとみる。
著者によれば、「新型コロナはアジアの出来事」という市民の認識の下、イタリアで転機になったのは北部ロンバルディア州の州都ミラノで開催された欧州チャンピオンズリーグのサッカーの試合だった。会場には4万人の観衆が詰めかけ、その後、奇妙な空咳や発熱の市民が病院へ続々と詰め掛けたのである。集中治療室(ICU)は間もなく満床になり、高齢者やがんなどの基礎疾患のある患者が相次いで死亡する事態になった。
当初はそれでも通常のインフルエンザと考えられ、病院側はマスクやゴーグルを身に着けずに治療に当たったが、医療スタッフも相次いで感染し、徐々に事態の深刻さに気付いていく。
体調が少々悪くても働く勤勉な北部の人々の気質も、感染拡大に拍車をかけた。
その後、ICUの収容能力を超える患者が押し寄せ、ICUで治療を受けられる患者とそうでない患者の選別もせざるを得ない状況に追い込まれ、医療崩壊の淵に立たされたのである。
南欧のスペインでも、3月8日の国際女性デーに首都マドリードで12万人が集うデモが行われ、この日を境に感染者数が爆発的に増えていった展開は、イタリアとよく似ていた。
こうした深刻な事態は、新型コロナに対する過小評価も大きな要因だったが、著者は、それまでの政策も背景にあるとみる。
イタリアはユーロ危機以降、医療支出を削減し、とくに北部の右派政党レガ(「同盟」)が、国立病院より経済的効率性が高いとして民間病院を優遇し、民間病院の経営者は、ICUを「人員と多額の経費が掛かる金食い虫」という理由で増やさなかったという。そうした事情もあり、今回のコロナ危機では、助かる見込みのある患者を優先的にICUに収容し、患者の選別をせざるを得ない状況に追い込まれたと指摘する。
英国のジョンソン政権も当初、いわゆる集団免疫政策をとるとして、ロックダウンなどの対策をとらず、事態を放置した。だが3月に入り、インペリアル・カレッジ・ロンドンの疫学者らが、何も対策を取らなければ25万~51万人の死者が出る可能性があるという警告を発したのを受け、この政策を放棄し、他の欧州諸国と同様、ロックダウンなどの対策を導入した。言い換えれば、英国はみすみす2カ月程度の時間を無駄にしてしまったのである。
米国でも、国立アレルギー感染症研究所のアンソニー・ファウチ所長がパンデミックに発展することは間違いないと早くから警告していたにもかかわらず、ドナルド・トランプ大統領はこれを軽視し、初動が大幅に遅れ、感染の急拡大が進み、多数の犠牲者を生んだ。コロナ対策の失敗は覆うべくもない。
検査体制や医療施設の余力
対照的に、欧州では第1波を最もうまく乗り切ったと考えられるのはドイツだと著者はみる。他の欧州諸国より被害は少なく、医療崩壊は起きず、ロックダウンは実施されたものの、イタリアなどに比べ、緩やかなものだった。
何より、3、4月頃から検査数が他の欧州諸国より多く、世界で最も早く、多数の市民に検査を実施できる体制を確立し、3月以降に検査数を大幅に増加。第10週(3月初旬)には1週間あたり12.5万件だったが、第20週(5月中旬)には42.6万件と3.4倍増させ、感染者の特定と隔離を進めていった。
感染者数は3月初旬に急増し、1000人の大台を超えたが、ドイツ政府はロベルト・コッホ研究所(ベルリン)と連携し、対策を履行していった。こうした対策を早期に着実に実行したことが、第1波の感染規模を抑えることに貢献したようである。
それに加えてもう1つの理由として、著者はICUの人工呼吸器を備えたベッド数の多さを挙げ、イタリアやフランスのように重症患者がICUのベッド数を上回る事態は起きず、医療体制に余力があったことを指摘する。
さらに、ドイツが第1波を首尾よく対応できた要因として、著者は感染症対策の事前準備と、アンゲラ・メルケル首相の巧みな広報対応の2点を挙げる。今後の対策を考える上でも、恐らく最も重要な点であると考えられる。
著者はまず、メルケル首相が行った3月18日のテレビ演説に着目する(Fernsehansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel)。
メルケル首相は演説で、この危機が「ドイツ統一、第2次世界大戦以来の試練」であると事態の厳しさを訴えた上で、感染拡大を阻止するため、国境封鎖や移動制限、飲食店閉鎖などの措置が不可欠であると説明し、
「こうした制約は、渡航や移動の自由が苦難の末に勝ち取られた権利であるという経験をしてきた私のような人間にとり、絶対的な必要性がなければ正当化し得ないものなのです」
と理解を求めた。
その上で、感染リスクの危険を冒しながら治療の最前線に従事する医師や看護師、スーパーのレジ係や商品の補充担当などに対する心からの感謝を述べたのである。メルケル首相は、状況の厳しさと同時に行き届いた言葉を紡ぐことによって、市民への共感と寄り添う姿勢を示した。
このテレビ演説はドイツ国内だけでなく、日本でも広く報道されたので、ご承知の方も多いだろう。
この頃、首相官邸に程近いスーパーで食品や日用品を買い、市民とともにレジに並んでカード払いするメルケル首相の様子が大衆紙によって報道された。買い置きすべく多めに購入する様子もなく、通常程度の買い物をする首相の姿は、ドイツ市民にも好感をもって受け止められた。
このことは、世論調査においても、メルケル首相は新型コロナ対策で「よく仕事している」と高く評価すると回答した市民が85%に達したことからも裏付けられる。
一般に、政府の対策に市民の協力を得るため、徹底した情報公開と丁寧な説明により正確な情報を共有し、政府と市民、社会が信頼関係を築くことは危機管理対策上、極めて重要だ。政府が市民に対し、日常生活上の判断材料となる正確な情報を積極的に提供することにより、市民や社会が政府に信頼を寄せれば、政府の政策に対する市民の協力は自ずと得やすいからだ。著者も指摘するように、メルケル首相の巧みな広報対応は好首尾の結果に貢献したであろう(2020年7月29日の拙稿『特集「新型コロナと情報」:新型コロナのリスク・コミュニケーション』=名古屋大学情報学研究科公式ブログ『情報玉手箱』=参照)。
次に、感染症対策の事前準備である。
著者も第3章で論じているように、ドイツは2012年以降、中国から世界に感染が広がったSARSへの対応を教訓に、来るべき感染症を想定し、対策を進めていたのである。
たとえば、連邦政府の委託によりロベルト・コッホ研究所などが、自然災害や感染症発生などの非常事態に市民を保護する施策をまとめ、『住民保護におけるリスク分析報告書2012』を連邦議会に提出した。この中で同研究所は、ドイツに大きな被害をもたらすシナリオとして、SARSウイルスの変種である「Modi-SARS」(変種SARS)の世界的流行を想定した。
「変種SARS」は潜伏期間が2~14日間で、発症すると、発熱、乾いた咳、呼吸困難などが起こり得るとし、致死率は1%程度だが、65歳以上は50%と高くなるとされた。お分かりのように、この想定は今般の新型コロナと非常に似ており、あたかも新型コロナの発生を予見していたかのようだ。
ドイツ政府はこのシミュレーションを参照し、対策に当たった。第1波の対策が他国よりうまくいったのは、こうした準備があってのことだった。評者も同意見である。
コロナ危機解明の手掛かりに
本書は、上述のような欧州諸国の主だった初動対策の動きを、現地のエピソードを交えて丹念に追ったものであり、貴重である。
他方、書名から欧州諸国の対応に関する内容を期待したが、イタリアを中心に扱った第1章を除き、ドイツに関わる記述に多くが割かれ、事実上、ドイツ中心の物語である。この点で、欧州全体の対応状況に関する報告を期待する読者にはやや肩透かしの感があるかもしれない。
新型コロナへの対応については、本書のほかにも、震源地となった中国を中心に『中国コロナの真相』(宮崎紀秀著、新潮新書)、日本の動きを中心に『コロナクライシス』(滝田洋一著、日経プレミアシリーズ)など、現地在住や気鋭のジャーナリストによる精力的な出版が相次いでいる。コロナ危機の発生から半年を迎え、ようやく、ある程度のまとまった情報が明らかになってきたということだろう。
これらの著作を読み比べ、丹念に検証しつつ検討することにより、このコロナ危機がどのように世界的に広がり、市民社会で何が起きていたのか、実態解明のための資料になるだろう。
通常の取材やインタビュー調査もままならない中で、いち早く著作としてまとめた本書の著者に敬意を表したい。
Twitterアカウント:https://twitter.com/NakamuraToshiya?lang=ja
ブログ:https://toshiyanakamura.academia.edu/