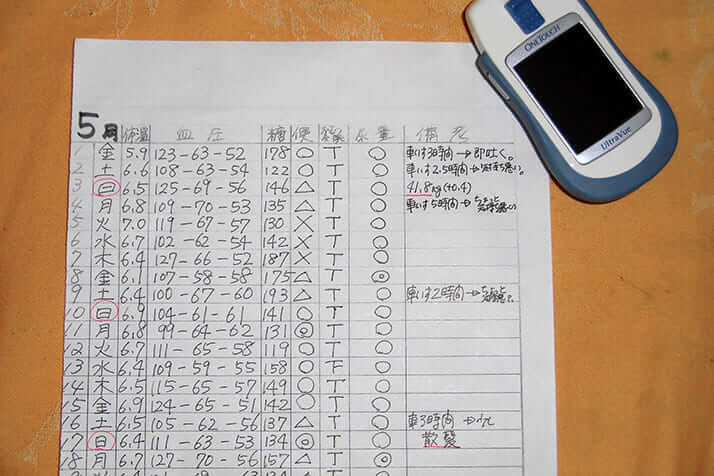床ずれは忘れたころにやって来る 100日ぶりに自宅に戻った妻──在宅で妻を介護するということ(第3回)
68歳の夫が、62歳の妻を家で介護することを決意。最初に待ち構えていたのは、寝たきりの人にはつきものの難敵だった。フリーライター平尾俊郎さんによる在宅介護のレポートである。
***
【当時のわが家の状況】
夫婦2人、賃貸マンションに暮らす。夫68歳、妻62歳(要介護5)。千葉県千葉市在住。子どもなし。夫は売れないフリーライターで、終日家にいることが多い。利用中の介護サービス/訪問診療(月1回)、訪問看護(週2回)、訪問リハビリ(週2回)、訪問入浴(週1回)。在宅介護を始めて1年半になる。
100日ぶりに妻が戻った
2018年12月中旬、ついに女房が家に戻ってきた。救急車で千葉大学病院に運ばれたのが9月初旬だから、転院した茂原の病院と合わせ入院期間は100日程度になる。
介護タクシーを使い、ストレッチャーに横たわった状態でのご帰還となったが、妻は見事に生還した。部屋のドアを開け、そのままベランダに面した陽当たりの良い8畳間に進み、真新しい介護ベッドに横づけした。固定用のベルトを解き、介護タクシーの運転手と2人で慎重にベッドに移した。
「帰ってきたね。どうだ、3カ月ぶりのわが家は。落ち着くだろう」と声をかけたくなる場面なのだが、当の本人は、病院にいたときと変わらず目を閉じて寝ている。当たり前だ。退院の許可は下りたものの、このころの女房は悪いなりに様態が安定しただけ。目を開いている時間が少し増えたが、一日の大半は眠っていた。もちろん言葉を発することなどできない。家に戻ってきたことも、私が夫であることも認知できずにいた。
それでも私は安堵感に包まれていた。こんなに落ち着いた気持ちになるのは何カ月振りだろうか。
この先どう転ぶかわからないか、これが「看取り」につながったところで、それまでの時間を一緒に暮らすことができる。母がそうであったように、消灯時間を過ぎた冷たい病院のベッドで、誰も気づかぬうちに息をひきとることはもうない。そう考えているうちに何だかとても楽観的な気分になってきた。「家に戻ったことできっと良くなる」「春になれば車いすで花見ができるかもしれない」──葬儀の手配をしたことなどすっかり忘れていた。
敷居を隔てたリビングのフローリング床に使い古しのカーペットを敷き、その上に布団を敷いた。ここが私の新しい寝場所だ。上半身を起こせばすぐに家内の顔が見られるし、何か異変があれば気がつくはずだ。その晩は寝酒の助けを借りることなく、すぐに眠りに落ちた。
[1/3ページ]