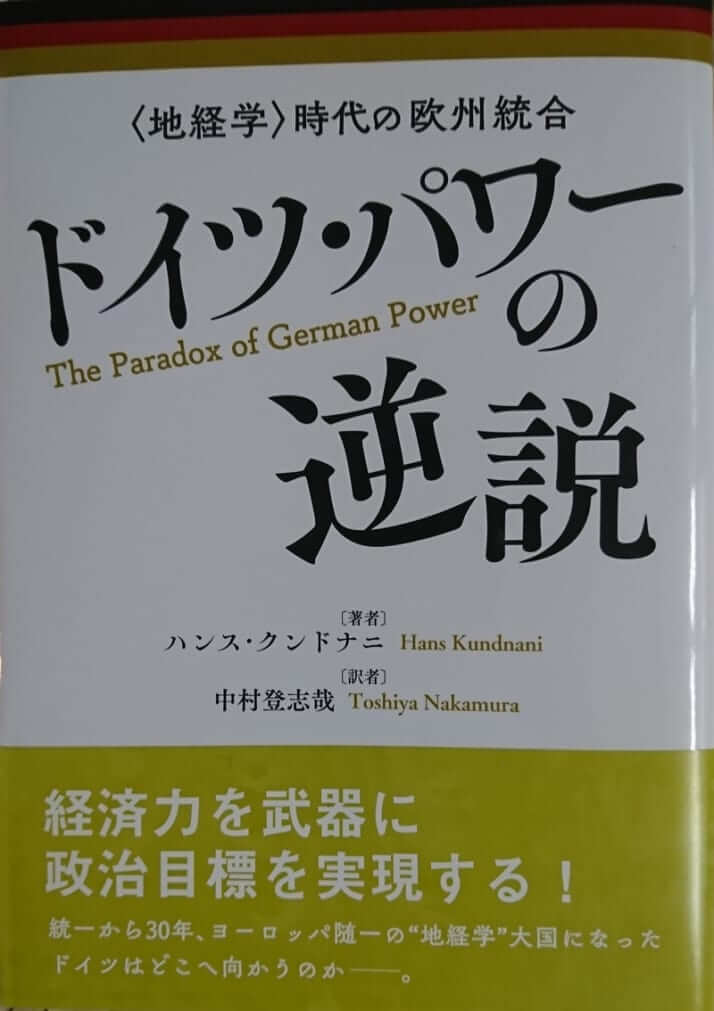【ブックハンティング】「ブレグジット」後EUでのドイツの役割
英国が欧州連合(EU)を離脱した後、欧州はいったい、どんな姿を見せることになるのだろうか。意外に早く平穏を取り戻し、ドイツとフランスが協調する形で、英国抜きの欧州統合に向けた歩みを早めることになるのか。それとも、英国、ドイツ、フランスの3大国のバランスが崩れ、欧州統合の進展の速度を落としたり、英国に続くEUからの離脱国を出したりすることになるのだろうか――。
欧州の今後を考える上で、フランスとともに、欧州一の政治・経済大国であるドイツの動向がカギを握るのは間違いない。
欧州とドイツの関係に焦点を当てた研究書は多数出版されているが、なかでも広く読まれているのが、ハンス・クンドナニ著 『ドイツ・パワーの逆説 〈地経学〉時代の欧州統合』(一藝社、2019年)だ。
同書は、原著がオックスフォード大学出版局から2015年に刊行されたが、翌2016年、中東からの大量難民が欧州に流入した「難民危機」への対応などを加筆した増補版が刊行される一方、ドイツ語等5カ国語に相次いで翻訳出版され、国際的に読者を獲得している。
『フィナンシャル・タイムズ』や『ウォール・ストリート・ジャーナル』等の世界の有力紙のほか、『フォーリン・アフェアーズ』等の有力学術誌でも書評に取り上げられ、今なお本書を取り巻く論争が続くなど、広く反響を呼んだものである。
筆者が同書の翻訳を担当する機会に恵まれたこともあり、同書を読み解きながら、ドイツと欧州の今後を考えてみたい。
「地経学」の概念
著者のクンドナニの詳細な経歴は本書を参照いただくとして、現在は、「英王立国際問題研究所」(チャタムハウス)の上級研究員として、ドイツや欧州の政治・外交問題を専門にする気鋭の研究者である。
本書が広く読まれている背景には、クンドナニが展開している主張にある。
クンドナニによれば、戦後ドイツは欧州の安定に寄与し、欧州一の経済大国となったが、東西統一後、とりわけ2010年のユーロ危機以降においては、自国経済における輸出依存度を徐々に高め、地政学的な利益を経済的手段で実現しようとする政治・外交手法である「地経学」的な大国に変貌。これによって、東西分裂前の、1871年から1945年にかけて持っていた「準覇権国(semi-hegemony)」的立場を手にしたのだと分析する。
欧州における「覇権国」というほどの力はないため、覇権国ではなく「準覇権国」なのであり、それは権力政治的な地政学的意味ではなく、あくまで経済的手段で国益を追求する「地経学」的意味においてであると指摘する。そのことは、新たな「ドイツ問題」の再来を意味し、ドイツは欧州に安定ではなく、不安定をもたらす要因になったと主張するのである。
「地経学」の概念は、上述の定義に基づいて、米国の戦略研究者であるエドワード・ルトワックらが使い、日本においても、ルトワックの著作が翻訳を通して知られるようになった。例えば、武田康裕他訳『エドワード・ルトワックの戦略論』(毎日新聞社、2014年)や、奥山真司訳『日本4.0 国家戦略の新しいリアル』(文春新書、2018年)だ。
そして、『フォーリン・アフェアーズ』が2016年の「本年最高の書」に選定したロバート・ブラックウィル他著『他の手段による戦争―地経学と国政術』(ハーバード大学出版局、2016年)が広く読まれたことにより、地経学的観点からの分析の必要性がいっそう認識されるようになった。
同書では、地経学とは、
「国益を促進あるいは擁護するため、また地政学上有利な成果を生み出すために、経済的な手段を用いること。また、他国の経済活動が自国の地政学的目標に及ぼす諸効果」
と定義されている。
「準覇権国」への変貌
日本のシンクタンクにおいても、地経学を切り口とする研究が進められるようになってきている。
例えば、日本再建イニシアティブ著『現代日本の地政学-13のリスクと地経学の時代』(中公新書、2017年)や、日本国際フォーラム編『JFIR WORLD REVIEW Vol.2 特集 地経学とはなにか』(2018年)はその好例だ。
それらの研究で指摘されているように、日本では、「地経学」とは多くの場合、「中国問題」を意味している。中国の台頭により、アジア太平洋地域の諸国にとって最大の貿易相手国になったため、中国は経済的つながりを交渉の武器に使うようになり、いまや「一帯一路」のような壮大なスローガンを掲げて、地経学的政策を進めているという。
そして、トランプ米政権下で進む米中貿易摩擦とは、中国が実践している「地経学」に対して、米国が同じく「地経学」的手法で対抗していくことに他ならないと指摘する。そうした地経学的手法を、欧州ではドイツが近年とってきたというのがクンドナニの見方なのである。
冷戦下の西ドイツ時代、ヴィリー・ブラント政権(1969~74年)が「接近による変化」構想を基に共産圏に対する東方外交を展開したが、その構想名に倣えば、ドイツは現在、「貿易による変化」を信じ、ロシアを国内的には民主主義に、対外的には協力に向かわせる一番の方法を経済的な相互依存を高めることだと考えてきたという。それゆえに、ロシアによるクリミア半島併合は、戦略的な衝撃であった。
ところが、ドイツは、対ロシア経済制裁を科しても、このような戦略的衝撃に際してさえ、防衛費の大幅な増額や軍事能力の改善、軍事ドクトリンの変更に踏み切る可能性は低いとクンドナニはみている。
ロシアよりもはるかに大きな市場を持つ中国についても、対ロ政策と同じ前提に立ち、経済的相互依存が高まれば、権威主義体制を民主主義に、国際社会における「責任あるステークホルダー」に変化させることができる、とドイツはみているというのがクンドナニの見立てである。
他方で、新しい形のドイツ・ナショナリズムも出現し、このナショナリズムは、輸出型経済、「平和」の概念、および刷新された「ドイツの使命」に基づいている。このため、ドイツは戦後、外交政策上、常に西側と歩調を合わせて行動し、独自の行動をとらないことを是としてきたにもかかわらず、今や独自の立場をとることに躊躇がなくなってきている。
その結果、「西側」との関係に波紋を広げていると分析するのである。
そして、特にユーロ危機以降、自国経済における輸出依存度を徐々に高め、輸出相手国である中国との関係を深める中で、地政学的な利益を経済的手段で実現する「地経学」的な準覇権国に変貌したのだ、と結論付けている。
右派ポピュリストの急伸
このような、ドイツを地経学的な準覇権国と位置付けるクンドナニの見方は、はたして内外の専門家からどう評価されたのだろうか。
日本とともにドイツを、多国間主義と民生を重視し、国外における武力行使を忌避することを理念とする「シビリアン・パワー」と位置付け、ドイツの外交政策にも大きな影響を与えてきたドイツの国際政治学者ハンス・マウルは、今もドイツがシビリアン・パワーとしての特徴を維持しているとみて、クンドナニの主張を次にように批判する。
マウルによれば、クンドナニが用いる証拠の多くは、2003年から2013年、中でも2009年から2013年の「キリスト教民主・社会同盟」(CDU・CSU)、「自由民主党」(FDP)の連立政権期のものであり、中国との「戦略的パートナーシップ」と称する経済関係の急速な深化等を背景に、輸出産業のほか、ユーロ圏においては銀行をはじめとする経済界の利益を図る外交政策が推進されていた時期だと指摘する。
ところが、この時期はユーロ危機への対応を含む例外的な外交を迫られた時期である上、クンドナニは、軍事力に代わって影響力を行使するための手段として経済力だけを想定し、議論を単純化して考えており、外交の重要性を無視していると批判する。そして、ドイツのその後の外交政策は再び、シビリアン・パワーのそれに戻ったと反論するのである。
ドイツでは、2015年に中東から百万人を超す難民が入国し、難民による犯罪も発生したことから、アンゲラ・メルケル首相に対する批判が高まった。その結果、2017年の連邦議会選挙では政府与党が大敗し、反難民を訴える欧州懐疑主義の右派ポピュリスト新党「ドイツのための選択肢」(AfD)が急伸し、いまや野党第1党の座を占める。
その後も、政府与党は州議会選挙で相次いで敗北し続け、連立与党の「社会民主党」(SPD)では、連立離脱の党内世論が燻り続ける。
EU新体制が発足したが
メルケル首相は2018年10月、CDU党首をアンネグレート・クランプ=カレンバウアー現国防相に譲り、欧州安定の礎と言われてきたメルケル時代も終わりを迎えつつある。
ドイツだけでなく、フランスやオーストリアなど、欧州諸国で近年、欧州懐疑主義の右派ポピュリスト政党が急伸し、加えて英国のEU離脱は欧州統合構想にとって大きな転換点である。
他方で、「EUはドイツの乗り物。英国が離脱するのは賢明だ」と述べるドナルド・トランプ米大統領は(2017年1月、英紙『タイムズ』とのインタビュー)、欧州の安全保障への関与に対する信頼感を失わせ、米欧関係の弱体化の可能性を感じさせる。
米独関係について言えば、最新の世論調査(「ピュー研究センター」と独「ケーバー財団」による世論調査、2019年11月25日発表)では、米独関係を「良好」と思う米国市民は75%、「悪い」と思うのは17%に対し、ドイツ側では「良好」は34%に過ぎず、「悪い」が64%と、3人のうち2人が「悪い」と考えていた。つまり、米独両国の市民間で認識の差が大きく、ドイツ市民が対米関係を悲観している姿が浮かぶ。
興味深いのは、今後協力関係をさらに深めたいと考えている国としては、ドイツ側では、トップのフランスに次いで「日本」が69%と第2位に挙げられていることだ。日本は、米国側でも、協力関係をさらに深めたい国として英国、フランスに次ぐ第3位(71%)に入っており、両国から日本に寄せられる期待は大きい。
ドイツはクンドナニが言うように、政治的・経済的目標を達成するために経済的手段を用いる地経学的な欧州の準覇権国家としての性格をさらに強めていくことになるのか。それとも、マウルらが言うように、一時的にはそう見えたとしても、シビリアン・パワーとして進化を遂げていくのか。
もしクンドナニが言うような性格をドイツが強めていった場合、欧州はどんな姿になっていくのか。
アジアとの関係においても、ドイツは中国と「戦略的パートナーシップ」をうたい、緊密な関係を構築しているが、その関係はさらに強化されていくことになるのか。
そして、リベラル国際秩序の中で、ドイツはどのような役割を果たすことになるのか――。
12月1日、欧州委員長にウルズラ・フォン・デア・ライエン前国防相が就任し、清しきにEUの新体制が発足した。ドイツ出身者の就任は、EUの前身である「欧州経済共同体」(EEC)の初代委員長ヴァルター・ハルシュタイン(1958~67年)以来初めてだ。ドイツ出身者が欧州の顔になることが果たして欧州安定に貢献するのか、あるいはユーロ危機の時のようにドイツへの反発を強めてしまうことになるのか。
名実ともに欧州を率いることになったドイツが今後どんな動きを見せるのかは、欧州情勢のみならず、国際情勢のカギを握ることになる。
【シンポジウムのお知らせ】
下記の要領で2件、筆者の中村登志哉氏が登壇するシンポジウムが開催されます。【1】では、本稿でご紹介している書籍の筆者が基調講演で登壇するほか、「ヨーロッパの部屋」でお馴染みの渡邊啓貴氏も登壇します。【2】でも、書籍筆者の講演があります。
ぜひ奮ってご参加ください。
【1】「ブレグジット後のヨーロッパの行方」
基調講演:英王立国際問題研究所上級研究員 ハンス・クンドナニ氏
"Europe after Brexit- Revisit of German Question?"
討論:渡邊啓貴・帝京大学教授、東京外国語大学名誉教授
福田耕治・早稲田大学教授、同大学EU研究所所長
中村登志哉・名古屋大学教授
進行:中村英俊・早稲田大学准教授、同大学イギリス政治外交研究所所長
日時:2019年12月5日(木) 16:30-18:00 (開場16:20)
会場:早稲田大学政治経済学術院3号館 3-305教室
(地下鉄東西線早稲田駅より徒歩10分)
主催:早稲田大学地域・地域間研究機構EU研究所、同イギリス政治外交研究所
共催:グローバル・ガバナンス学会
備考:入場無料、事前登録不要
【2】国際パブリック・レクチャー“Paradox of German Power - Implications for Japan”
講演:英王立国際問題研究所(チャタムハウス)上級研究員 ハンス・クンドナニ氏
討論:中村登志哉・名古屋大学教授
進行:井原伸浩・名古屋大学准教授
日時:2019年12月4日(水) 15:00-17:00(開場14:45)
会場:名古屋大学情報学研究科棟1階 第4講義室
(地下鉄名城線名古屋大学駅1番出口より徒歩3分)
主催:名古屋大学グローバルメディア研究センター
共催:グローバル・ガバナンス学会、早稲田大学
備考:入場無料、事前登録不要
Twitterアカウント:https://twitter.com/NakamuraToshiya?lang=ja
ブログ:https://toshiyanakamura.academia.edu/