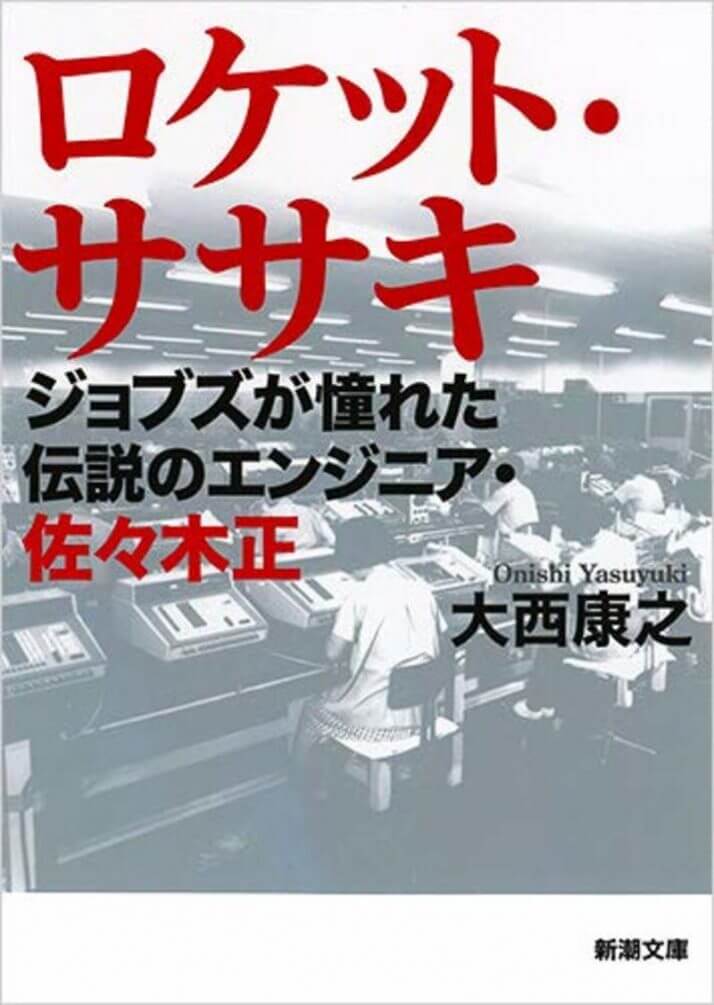『ロケット・ササキ』外伝(3・了)「コンピューター」と格闘を続けた「浅田篤」
浅田篤が早川電機工業(現シャープ)に入社したのは1955年。社員数はまだ1300人で、創業者の早川徳次が誕生日の社員を社長室に呼び、紅白饅頭を手渡すような家族的な雰囲気が残っている時代だった。朝鮮戦争の特需で国内の景気は上向き、皇太子(今上天皇)ご成婚の中継を自宅で観よう、というので白黒テレビが爆発的に売れた。
「会社の未来を語る会」
日本で初めてテレビを量産した早川電機は大いに販売を伸ばしたが、当時のテレビは部品の品質が安定せず、よく故障した。販売網も整備できていない早川電機は、本社から浅田たち若い技術者を顧客の所に送って故障に対応した。
皇太子ご成婚で家庭への普及が本格化したとはいえ、まだ主な買い手は旅館や銭湯である。奮発して買ったテレビが映らなくなると、顧客は怒るというより困り果て、浅田たちが駆けつけると「よく来てくれた」と歓迎された。田舎の温泉旅館に修理に行った時には宿の主人が「こんな遠くまで申し訳ない」とタダで1泊させてくれたこともある。
当時、NHKの放送は午前11時30分から午後1時30分までの2時間と、午後5時30分から午後10時までの2回。この時間に現場に行かないと、直してもちゃんと映るかどうか確かめられない。2時間では間に合わないので、主に修理は夜になる。午前中を移動に当てて現場で待機し、夜になると客先でテレビを直す。その日は現地に泊まり、次の日には別の場所へ。
「ワシら、こんなことをするため会社に入ったんやない」
体裁良く「修理工のドサ回り」をやらされた浅田たちは、日増しにフラストレーションを溜めていった。いつから始まったか定かでないが、1958年頃から早川電機の若い技術者たちは、修理出張から戻ると本社の近所の小料理屋「富田屋」に集まり、愚痴を言い合うようになった。
だがそこはさすがに技術屋である。富田屋での集まりは、単なる愚痴にとどまらなかった。
「だいたい、メーカーのくせに、うちには研究所がない。これでは新しいもんなど作られへん」
「研究所なんか作って、何すんねん」
「俺はこんなことがしたい」
「こんなもん作ったらおもろいやん」
富田屋での会合は、いつしか「会社の未来を語る会」になっていった。会合が始まって半年ほどたったある日、それが徳次の腹心、専務の佐伯旭の耳に入った。
「君ら毎晩、集まっとるらしいやないか。何か不満でもあるんか」
首謀者の1人として部屋に呼ばれた浅田は、まっすぐに佐伯の顔を見ていった。
「今はテレビで儲かっても、そのうち売れんようになります。テレビの次に売れる未来商品を開発せなあかんと思いますんや」
浅田たち、若い技術者の純粋な顔を見た佐伯は、しばらく腕を組んで思案した。
「君らの言うことも、もっともや。分かった、ワシに任せてくれ」
「人間より馬鹿なんだね」
佐伯は1960年、世界で初めてブラウン管による電送・受像に成功した浜松高等工業学校(現・静岡大学工学部)の高柳健次郎助教授の愛弟子、笹尾三郎を研究室長に迎えて研究開発室を立ち上げた。
開発テーマは6つ。半導体、医療機器、超音波、太陽電池、電子計測機、そして電子卓上計算機である。テーマごとに第1から第6まで研究室が作られたが、第6の電卓は室長のなり手がいなかった。コンピューターはまだ学問としても産業としても歴史が浅く、それを学んだ技術者が社内に1人もいなかったからだ。
「言い出しっぺのお前がやれ」というわけで、浅田にお鉢が回ってきた。浅田は大阪大学工学部でコンピューター理論の研究をしていた尾崎弘のところに押し掛け、尾崎が翻訳中だった米国の研究者の論文の校閲と引き換えに、コンピューターを教わる約束を取り付けた。
浅田たち第6研究室の面々は毎日、尾崎の研究室に通い、昼間は大学院生、夜は尾崎本人からコンピューターの手ほどきを受けた。半年間、猛勉強した後、1年がかりで試作機を作り「HAYAC(ハヤック)1」と名付けた。しかし机いっぱいの面積で、高さは人の背ほどもある巨大な計算機は「かける1」しかできず、お披露目の席で徳次に、「コンピューターといっても人間より馬鹿なんだね」と笑われる始末である。
だが、徳次と佐伯はそれから4年、浅田たちにコンピューターとの格闘を続けさせた。「まだか」と聞くことはあっても「やめろ」とは1度も言わなかった。なかなか結果が出せない浅田は経営陣の忍耐力を心の底から「ありがたい」と思った。
そして1964年、ついにフル・トランジスタの電卓「CS-10A」の発売にこぎつけた。それまで2桁の割り算を入力すると1分近くガチャガチャと大きな音を立てていた機械式の計算機に比べ、瞬時に音もなく答えを出す電卓は大評判になり、53万5000円という、当時の乗用車並みの価格にもかかわらず注文が殺到した。
現れた「半導体の第一人者」
それでも、浅田たち開発陣に喜びはなかった。全力を出し切り、「これ以上、何をしていいのか分からなくなっていた」のである。早川電機が可能性を示したことで、電卓市場にはソニー、キヤノンなど大企業や中小ベンチャーがこぞって参入し、激烈な開発競争が始まった。豊富な開発資金と分厚い人材を武器に追ってくる大資本に対抗するための力も知恵も、早川電機には残っていなかった。
万策つきて呆然としている浅田たちの前に現れたのが、神戸工業から移籍した佐々木正である。
「もう、どうしたらいいか分からんのです」
浅田たちは、目の前に現れた「半導体の第一人者」にすがった。
「どれどれ」
CS-10Aの図面を見た佐々木は、開口一番こう言った。
「うん、これはそのうちワンチップになるね」
浅田が作った最初の試作機は4畳半の基盤に1万個のトランジスタを並べたものだった。それを極限まで小型化し、机の上に載るようにしたのがCS-10Aである。
(これがワンチップになるだと。大丈夫かこの人は)
浅田の安堵はその場で不安に変わった。さらに佐々木が続ける。
「ワンチップになって人間の脳に埋め込まれるかもしれんね」
(あかん)
不安は絶望に変わった。
が、佐々木が開発の先頭に立ったシャープは、そこから10年、カシオ計算機との「電卓戦争」を繰り広げ、ついに名刺サイズの電卓を作り上げる。
電卓を小さく薄くしていく過程で佐々木は、プレナー型のIC(集積回路)に代わってMOS(金属酸化膜半導体)のLSI(大規模集積回路)を、ブラウン管のディスプレーの代わりに液晶を採用し、単3電池の代わりに太陽電池を使った。全て量産型の民生品では初めて使われる技術だった。
「情熱を形に変えてくれた」
「そろそろ電卓は終わりだろう。次を考えよう」
佐々木がシャープの開発現場にそう命じたのは1970年代の終わりである。浅田は電卓で先鞭をつけた液晶ディスプレーを携えて任天堂に行った。これが携帯型ゲーム機「ゲームボーイ」の開発を促した。液晶パネルは、ビデオレコーダーでシャープがソニーを猛追した「液晶ビューカム」にも使われ、やがてシャープを大躍進させる液晶テレビの「アクオス」につながっていく。
前回、登場した吉田幸弘はMOS-LSIと液晶ディスプレーを使い、タブレット端末を開発した。商品化には至らなかったが、佐々木が後にソフトバンクを立ち上げる孫正義から買い取った電子翻訳機の技術と融合され、やがて電子手帳の「ザウルス」が誕生する。
「我々には、新しいモノを生み出したい、という情熱があったが、どうすればそれが実現できるのか分からなかった。ドクター(シャープ社内では佐々木をこう呼ぶ)のビジョンと知識と人脈が、我々の情熱に形を与えてくれた」
浅田はシャープにおける佐々木の役割をこう説明する。
ザウルス誕生前夜、佐々木とスティーブ・ジョブズ(アップル共同設立者)の関係が起点となり、ジョブズがアップルを去った後も両社の関係は続き、「個人向け情報端末」の開発で提携している。この時、アップルが開発した「ニュートン」は大きなヒットにならなかったが、インターネットが普及した2000年代、アップルは音楽端末の「iPod」、スマートフォンの「iPhone」、タブレット端末の「iPad」を次々と生み出し、デジタルで世界を変えていく。ニュートンでの経験がその土台になっているのは間違いない。
「ジョブズが憧れた伝説のエンジニア、佐々木正」
その功績は、デジタル革命の歴史に深く刻まれるべきである。