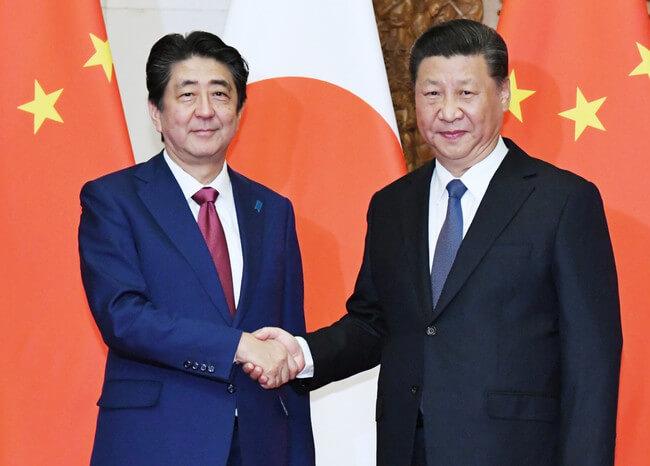「一帯一路」で中国「債務の罠」に蝕まれる世界の実情(上)
中国の習近平国家主席“肝いり”の国家プロジェクト「一帯一路」戦略が、急速に進んでいる。しかし、中国からの巨額の投融資を受けた相手国が債務を返済できず、国家の戦略的資産を中国が獲得することへの警戒が世界的に「債務の罠」として高まっている。政権交代などで事業の見直しを求められるケースも相次いでいる。
こうした状況のなか、習近平政権はどのような方向性で「一帯一路」戦略を進めようとしているのか。
軍事的要衝を獲得
相手国の経済状況が不安定になると、戦略的資産を中国がどのように得るか。その典型例を挙げてみる。
まず、ギリシャの事例で見ることができる。
中国は、事実上のデフォルト(債務不履行)状態に陥ったギリシャを「欧州の玄関口」として、戦略的に極めて重要視していた。
なかでもギリシャ最大の港ピレウス港は、「一帯一路」計画において、中国の海運の重要拠点として位置づけているほか、中国海軍艦艇の寄港地としても重視していると見られる。
中国海運大手「中国遠洋海運集団」は2008年、同港の一部埠頭の運営権を獲得した。ギリシャが財政危機に陥り、公営企業民営化の一環として国家資産の売却を迫られていたタイミングを見逃さず、2016年、埠頭運営会社の株式51%を取得したのである。買収額はわずか2億8050万ユーロ(約360億円)。現在、株式保有率は7割ほどに引き上げられている。
中国は今、ピレウス港と欧州中央を直結する交通の要衝を押さえるため、高速鉄道などへの大規模投資を進めている。
スリランカに目を向けてみよう。ハンバントタ港は、中国による投資のリスクを示す典型的な例だ。影響力拡大を狙う中国の、まさにこれこそが「債務の罠」と指摘する声が多い。
2010年、建設費約13億ドルのほとんどを中国からの融資で賄い、最高で年6.3%という金利で返済に窮した。その結果、2017年12月に港湾運営会社の株式の70%を中国国営企業に貸与し、リース料として約11億2000万ドルを受け取ることで合意させられる羽目となる。貸与期間は99年間。中国に売却したのも同然となった。
中国は、資源安全保障という観点から、「真珠の首飾り」と呼ばれる海上交通路確保の戦略上でインド洋を見据えており、これまで中国海軍はたびたび、潜水艦をスリランカやパキスタンに寄港させてきた。また、地政学上の要衝であるジブチで大きな海軍基地を建設したことからも、中国海軍がハンバントタ港を軍事的視点で捉えているのではないかとの疑念は今も消えていない。
では、スリランカはなぜやすやすと「債務の罠」に陥ったのか。
それは、2018年における同国の債務予想が国内総生産(GDP)の約8割と言われる財政状態が背景にある。インフラ投資で借金を重ねてきたからだ。国際通貨基金(IMF)も債務返済のために資産売却を奨励しており、1週間に数便しか利用されていないマッタラ・ラジャパクサ国際空港も売却の候補として挙がっている。同空港は、建設費約2億ドルの大部分を中国輸出入銀行が融資しており、売却先はインドなのか中国なのか注視されている。
つまり、罠と承知でインフラ整備、貿易、雇用に目がくらんだと見ることもできる。
中国が接近著しいオマーンはどうか。
財政状態が懸念された2017年1月、南部のドゥクム港の整備に約2億6500万ドルの融資を中国から受けることで合意した。
また、中国は107億ドルを投じて「工業団地」をドゥクム港周辺に建設することで2016年に合意していたが、注目されているのは、ホテルや製油関連施設の建設という名目でドゥクム港周辺の広大な土地の使用を中国側に認めた点だ。
ドゥクム港はアラビア海に位置する、アジアと欧州・中東を結ぶ拠点だ。米英軍の補給基地もある要衝である。
中国にとって、有事の際に原油を運ぶシーレーン(海上輸送路)にあたるホルムズ海峡が米軍により封鎖される懸念は常につきまとう。しかし、ホルムズ海峡が封鎖されても、ドゥクム港が利用できればそのリスクは軽減される。
ドゥクム港は大型艦船の修理が可能なドックも備えられており、中国が港周辺の土地を押さえた狙いは、将来的に艦艇の補給や修理など軍事的に利用する可能性が指摘される。
ちなみにこうした「工業団地」は、中国が投資を促進する狙いから「海外経済貿易合作区」と呼ばれ、建設中を含めると、すでに50カ国、118カ所に上る。
インド洋の島国モルディブ。同国も、インド洋の地政学的要衝に位置する。
同国で中国が主体となった事業で有名なのは、国際空港と首都マレを結ぶ橋(総工費約2億ドル)だ。そこには赤い英文字で大きく「中国とモルディブの永遠の友情」と記されている。中国が支援をしたという意味だ。総工費の過半は中国が賄った。
モルディブでは9月の大統領選で、野党モルディブ民主党のイブラヒム・ソリ氏が、親中派で中国依存をどっぷりと深めてきた現職アブドゥラ・ヤミーン氏を破った。中国がからむ事業での汚職と過度なインフラ整備が政権交代につながったとされる。
ソリ氏はインドと関係が近い。ソリ氏は選挙後、「中国との事業契約をすべて見直す」と表明した。中国との契約の全容は明らかではないが、対中債務はGDPの4分の1を超え、それをいかに減らすかが課題となっている。
モルディブの事例は、南アジアにおいて親中派が選挙などで下野すると、「一帯一路」をめぐって中国とインドとの綱引きとなる典型だ。
モルディブの大統領選では、インドの情報機関は数千万ドルを投じ、ソリ氏の勝利のために暗躍したと言われている。インド洋を自国の勢力圏と見なすインドにとって、モルディブの対中接近は安全保障上の脅威と映るからだ。
米国の外交関係者は、「今後、中国はソリ政権の追い落としをはかるのではないか。モルディブの島に軍港を建設することをあきらめないだろう」と指摘する。
友好国でも拡大するリスク
中国と極めて近い関係のパキスタンまでも、「一帯一路」事業の対中債務問題が大きな政治問題として浮上している。
インド洋に面したパキスタンは、「一帯一路」の中央に位置する。中国が安全保障戦略上、極めて重視しているのがパキスタンのグワダル港である。
グワダル港は中国が建設した深水港で、中国企業が2017年から40年間リースすることで合意している。
同港と中国西部の新疆ウイグル自治区カシュガルをパイプライン、道路、鉄道、送電網、通信網で結んでいる。有事の際には中国のタンカーがマラッカ海峡を通らなくても、同国で設置したパイプラインが有効な役割を果たすほか、中国軍の海外派兵の際にはインド洋に出やすくする狙いと見られる。
このように、中国にとってパキスタンは、対インド戦略でも重要なパートナーなのだが、シェイク・ラシッド・アハメド鉄道相が10月1日、「鉄道事業の予算を20億ドル減らす」と発表したのだ。
減らしたのは、カラチからペシャワル間の鉄道(1870キロメートル)の改修事業で、当初予算は82億ドル。ラシッド鉄道相はさらに42億ドルまで減らしたい考えも示した。
パキスタンでは、中国は「一帯一路」計画で約630億ドルを拠出するとしていたが、さすがにパキスタン内外から「債務漬けとなるリスクがある」と懸念の声が上がっていた。
パキスタンはインダス川流域でのダム建設事業(総工費約140億ドル)で2017年、中国からの融資を断ったことがあるが、債務漬けへの懸念がここにきて大きく表面化したのは、8月に新たに就任したイムラン・カーン首相の考えとされる。このままでは対中債務の返済ができず、スリランカのように国家資産を“接収”される羽目になるのではないか、との危機感を抱いた判断という。
パキスタンの対外債務は900億ドルを超え、うち4割超が対中債務とされている。10月11日、パキスタンはついにIMFに支援を求めたと表明した。80億ドル規模と見られている。
ちなみに同国は23日、サウジアラビアから60億ドル相当の経済支援を受けることで合意したことも明らかにした。サウジにとっては、例のジャーナリスト殺害事件で浴びている世界からの批判に対し、友好国を増やしたい思惑があるのだろう。
まだある。先ほども少し触れたが、中国軍数千人が駐留し、兵器などを格納する広大な地下空間まで建設したとされる中国軍基地のある、ジブチ。同国は産業もなく、財政基盤が極めて弱い。
中国は、ジブチをパキスタン、スリランカ、モルディブと同様、安全保障上の戦略拠点として位置づける。中国紙は「ジブチの中国軍基地は、中国海軍が遠方展開するための支援拠点となる」と明解だ。ちなみに、中国紙はこれまで軍の戦略拠点を世界的に拡大することを示唆する記事を掲載してきたことがある。
これまでにも中国は、ジブチ~エチオピアを結ぶ鉄道などに巨額の援助をしており、ジブチが受けている融資の9割は中国からである。この鉄道は、エチオピアで中国企業が生産した繊維や軽工業製品を国外に輸出するルートだ。
また、ジブチとイエメンとの間のバブ・エル・マンデブ海峡は、年間2万数千隻が往来する資源安全保障上の要衝であり、ジブチの脆弱な財政に目を付けた中国は、ジブチ港を民営化させ、その株式の23%を取得して主導権を握った。すでに中国の支援で建設した新港は、中国海軍が一部、使用しているとも言われる。
このように、財政基盤が弱い国で中国の「債務の罠」への懸念が指摘されているわけだが、米シンクタンク「世界開発センター」が2018年3月に発表した債務調査によると、中国からの借金漬けリスクがある国として、上記で挙げたジブチ、モルディブ、パキスタンに加え、キルギス、ラオス、モンゴル、モンテネグロ、タジキスタンの国名を挙げており、スリランカ同様の事態が起こると懸念されている。
しかし、実は債務漬けリスクはこれらの国だけにとどまらず、ますます拡大しているのが実態で、さらに懸念は広がっているのである。(つづく)(野口 東秀)