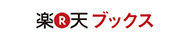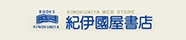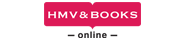NHK「あさイチ」で話題になった特集「死後離婚のリアル」 亡き配偶者の親族とは縁を切りたいと思った時
「昨今、『姻族関係終了届』を出す人が年々増加しています。配偶者側の親族との関係を解消するという意思表示の届けです。『死後離婚』と呼ばれるようですが、正確には『離婚』ではなく、配偶者との関係にも実子との親子関係にも影響はありません」
7年前に突然死で夫を亡くし、配偶者と死別した境遇を「バツイチ」ならぬ「没イチ」と呼ぶ小谷みどりさん(第一生命経済研究所主席研究員)は、著書『没イチ パートナーを亡くしてからの生き方』の中でそう説明する。
NHK「あさイチ」で話題となった「死後離婚」。小谷さんの説明の通り、亡き配偶者の親、きょうだいなど親族と縁を切ることだが、ショッキングなネーミングに出演者や視聴者からは少なからず疑問の声が上がった。
一般に言う「離婚」は、役所に「離婚届」を出すことで配偶者との婚姻関係が終了し、同時に配偶者の親族との姻族関係も終了する。ところが、配偶者が亡くなった場合は、「死亡届」を役所に提出すると婚姻関係は消滅するが、配偶者側の親族との姻族関係はそのまま継続される。
「ここ数年、姻族関係終了届を出す人が急増している背景には、核家族化が進んでいることが挙げられると考えられます。一緒に住んでいなければ、配偶者の両親を家族だとは思いにくいこともあって、配偶者が亡くなった後に、舅や姑、兄弟姉妹とは付き合いたくないとアクションを起こす人が増えているのではないでしょうか」
番組内で挙げられた死後離婚の主な原因は介護、遺産トラブル、不仲、お墓の4つだった。普段行き来がなかった義父母などの介護は回避したいと思う場合や、故人の遺産分配で問題が生じた場合、亡くなった夫の生家の墓守をしたくない、そもそも親族たちと同じお墓に入りたくない場合などもある。不仲については小谷さんも身近でこんな経験者がいた。
「夫が亡くなった後、夫が結婚以前から付き合っていた女性とずっと関係を続けていたことが発覚し、そのことを知っていたのに見て見ぬ振りをしていた義母を許せないと、姻族関係終了届を出した女性もいます」
小谷さんによると、姻族関係終了届の手続きは至って簡単。定型書類はなく、A4の紙に必要事項を書いて本籍地、もしくは住居地の市区町村にその紙を提出するだけ。配偶者が死亡した後であれば提出期限はなく、何年後でもかまわない。さらに亡き配偶者の親族側に了解をとる必要もない。
「かつては、長男家族が親と同居するという3世代家族が一般的でした。その頃、夫が亡くなった時に夫の両親がまだ健在であれば、夫の妻はそのまま義理の両親の世話を見ながら生活をするのが、当たり前だとされていました。……夫が亡くなったからといって、『はい、さようなら』と、舅や姑を見捨てることは許されない社会だったことを思うと、結婚の考え方も大きく変わったなあと思います」
番組内では、亡くなった夫の遺産を頼ってきた義父母とのトラブル、もともと関係が悪かった義父母に遺骨も分けてもらえなかったケースなど、伴侶を亡くしてダメージを受けた上に、追い打ちをかけるような問題を抱えた当事者の例が紹介された。
さまざまな事情で死後離婚に踏み切ったり、悩んだ末に踏みとどまったり、という人は実はかなり多いことがわかる。しかし、いずれにしても、配偶者との死別が事の始まりということに変わりはない。
「配偶者、パートナーがいれば、いずれどちらかが必ず没イチになる」とは、小谷さんが頻繁に発信している言葉だ。その真意は、「死後離婚」が決してフィクションの中の話ではない以前に、伴侶との死別も他人事ではないことを気づいてほしいからだという。転ばぬ先の杖の一本に、「つれあいとの死別で一人になる自分」シミュレーションも加えていいのかもしれない。